
資産運用といえば「新NISA」や「不動産投資」など、選択肢が増えてきました。でも実際、自分に向いているのはどちらなのか悩みますよね。
「ローンを組む不動産投資は勇気がいる…」「NISAって本当に儲かるの?」そんな疑問や不安を抱えている方に向けて、本記事では目的別・属性別・金融機関別など、あらゆる角度から2つの選択肢を徹底比較します。
「自分にはどちらが合っているのか知りたい…」という方は、お気軽にご相談ください。あなたに合った資産運用の選択肢をご提案します。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- 不動産投資と新NISAの基本をおさらい
- 不動産投資とは?
- 新NISAとは?
- 【目的別】あなたに合うのは不動産投資と新NISAどっち?
- 目的①:資産を増やしたい人
- 目的②:老後資金を準備したい人向け
- 目的③:相続資産を活用したい人向け
- 目的④:高収入・高資産層向け
- 目的⑤:インフレ対策したい人向け
- 不動産投資と新NISAの収益シミュレーション
- 不動産投資の例
- 新NISAの例
- 不動産投資と新NISAを併用するという選択肢
- 目的が異なるからこそ、併用が効果的
- 分散投資によるリスクヘッジが可能に
- 不動産投資と新NISAの「よくある質問Q&A」
- 不動産投資は副業になる?会社にバレない?
- NISAだけで老後資金は足りる?
- ローンを組めない場合の不動産投資は?
- 両方やるなら、どちらから始めるべき?
- まとめ
不動産投資と新NISAの基本をおさらい
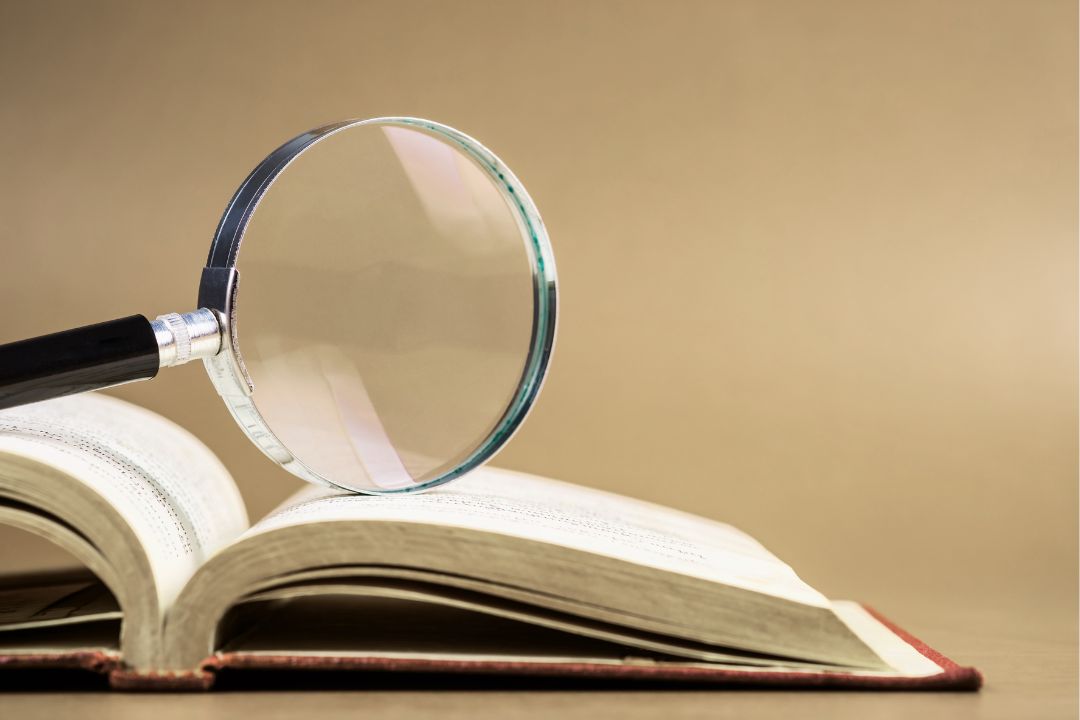
「不動産投資」と「新NISA」は、どちらも資産形成の手段として注目されていますが、仕組みもリスクも大きく異なります。
まずはそれぞれの特徴をざっくり確認しておきましょう。
不動産投資とは?
不動産投資は、家賃収入や売却益を得ながら、ローンや節税なども活用できる実物資産型の投資です。
| 項目 | 内容 |
| 収益の種類 | 家賃収入(インカムゲイン)と売却益(キャピタルゲイン)の2つ |
| 必要資金 | 物件価格の10〜20%程度の自己資金が必要(+諸費用) |
| 資産拡大 | ローンを活用することで、自己資金以上の投資が可能 |
| 節税効果 | 減価償却や損益通算により、所得税・住民税を抑えられるケースもある |
| リスク要因 | 空室・修繕費・災害・金利上昇など、管理と事前の対策が必要 |
| 向いている人 | ある程度まとまった資金がある人や、金融機関からの信用がある人(融資利用)で、長期保有によって安定収入を得たい人 |
■メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|
|
新NISAとは?
2024年から新制度でスタートした新NISAは、少額から始められる非課税制度として、投資初心者にも人気の制度です。ほったらかし運用や分散投資に向いており、資産をコツコツ増やしたい人に適しています。
| 項目 | 内容 |
| 制度の概要 | 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用して年間360万円まで投資可能。非課税保有限度額は最大1,800万円。 |
| 投資対象 | 上場株式、ETF、投資信託など(成長投資枠/積立投資枠) |
| 運用スタイル | 少額から始められ、積立による長期・分散投資がしやすい |
| 非課税の仕組み | 運用益・売却益・配当益がすべて非課税に |
| 流動性 | いつでも売却可能で現金化しやすい |
| 向いている人 | 少額から始めたい人、ほったらかし投資をしたい人 |
■メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|
|
【目的別】あなたに合うのは不動産投資と新NISAどっち?

2つの投資法は性質がまったく異なるため、目的によってベストな選択肢が変わってきます。
「資産を増やしたい」「老後資金を準備したい」など、5つの代表的な投資目的に合わせて、最適な運用方法を具体的に紹介します。
目的①:資産を増やしたい人
このタイプにおすすめなのは「不動産投資」です。
年利回り5%以上を狙える収益物件に、自己資金を活かしてローンを組めば、短期間で元手以上の資産形成を目指すことも可能です。
物件選びと運用次第では、自己資金の数倍規模の資産を10年以内に築けるケースもあり、NISAよりも資産が増えるスピードは格段に速くなります。
一方、新NISAは年3〜5%程度の堅実な運用が魅力ですが、年間360万円という投資枠の上限があるため、短期間で資産を大きく増やすには向いていません。
例:30代・会社員・副業にも興味がある人/40代前半・事業拡大を考える個人事業主
目的②:老後資金を準備したい人向け
このタイプは、「新NISA」と「不動産投資」のどちらもおすすめです。
将来の生活資金を「着実に確保していきたい人」には、新NISAが適しています。
資産の値動きはあるものの、制度として非課税のまま積み立てを続けられる仕組みが整っており、収支管理もシンプルに行えます。
「いつまでに、いくら準備できそうか」が見通しやすく、計画的に準備したい人にとって心強い選択肢です。
一方で、老後の収入源を「自分で生み出したい人」には、不動産投資も有力です。
ローン返済後は家賃収入がそのまま生活費にあてられるため、運用がうまくいけば年金の上乗せとして安定した収益源になります。
ただし、物件管理や突発的な支出が発生する可能性もあるため、高齢期の負担を軽減するには、管理会社との連携など事前の備えが不可欠です。
40代・会社員・子育てがひと段落して将来設計を考え始めた人/50代・定年が見え始めた会社員・公務員
目的③:相続資産を活用したい人向け
このタイプにおすすめなのは「不動産投資と新NISAの併用」です。
不動産に資産を組み替えることで、現金よりも相続税評価額を抑えられる可能性があります。
とくに相続税の圧縮効果を狙うなら、収益性のある中古物件や一棟アパートを検討する価値があります。
一方で、余剰資金がある場合は、家族名義のNISA口座での資産形成も並行して進めるのが効果的です。
不動産で「資産を守り」、NISAで「資産を分散・移行」する。
相続対策として両者を目的に応じてバランスよく組み合わせることが、もっとも合理的な選択といえるでしょう。
例:30〜50代・不動産を相続した人/50代・親からの資産移転を考え始めた人
目的④:高収入・高資産層向け
このタイプにおすすめなのは「不動産投資」です。
高収入の方は所得税率も高く、節税対策をしながら資産を増やす戦略が求められます。
不動産投資では、減価償却を活用して課税所得を圧縮し、手元に残るキャッシュを最大化できるのが大きなメリットです。
法人化すればさらなる節税余地が広がり、資産管理会社を通じて家族への資産移転にもつなげられます。
一方、新NISAは非課税とはいえ、年間360万円・生涯1,800万円という投資枠があるため、高額資産を一気に動かしたい人にはスケールが合いません。
大きな資産を持つ人ほど、不動産投資で節税と資産形成を同時に実現する価値が高まります。
例:年収1,000万円以上の40代・会社役員/資産5,000万円以上保有の経営者・富裕層
目的⑤:インフレ対策したい人向け
このタイプにおすすめなのは「不動産投資と新NISAの併用」です。
不動産は実物資産であり、物価上昇に連動して家賃や資産価値が上がる可能性があるため、インフレに強い投資先のひとつです。
さらに、新NISAを活用してインフレ連動型のETFや投資信託に投資すれば、金融資産でも物価変動に備えることができます。
どちらか一方では不安という方でも、現物+金融のハイブリッド運用でリスク分散と将来の購買力維持が可能です。
とくにインフレが長期化する局面では、「お金の価値を守る」ための手段として、この2つの使い分けが効果を発揮します。
例:30〜50代・資産保有者/現金比率が高い投資未経験者/経済ニュースに関心が高い会社員や自営業者
不動産投資と新NISAの収益シミュレーション

気になる2つの選択肢について、以下の条件でシミュレーションしてみました。実際には、運用する物件やその後の戦略(買い足し)、積立金額や期間によって収益性は大きく異なります。
不動産投資を始めるなら、どの価格帯・どんな入居者層をターゲットにするかが重要です。また、新NISAであれば、毎月いくらを何年間積み立てるかによって将来の資産額が大きく変わります。
それぞれの運用方法に合った金額設定の目安として、ぜひ参考にしてみてください。
不動産投資の例
不動産投資では、以下の条件で試算してみました。
- 物件価格:1,000万円
- 自己資金:200万円(頭金+諸費用)
- 借入金額:800万円
- 返済期間:20年
- 金利:2.0%(元利均等返済)
- 月々返済額:約40,500円
- 家賃収入:月7万円(年間84万円)
- ランニングコスト(管理費・修繕積立・固定資産税など):月1.5万円(年間18万円)
■ローン返済中(1~20年目)
| 項目 | 金額 |
| 年間家賃収入 | 84万円 |
| 年間経費(管理・税) | 18万円 |
| 年間ローン返済額 | 約48.6万円 |
| 年間キャッシュフロー | 約17.4万円 |
20年間で手残り(返済額と経費を引いた実質収益)は、約348万円となります。
※実際には、敷金・礼金や更新料の設定、修繕費の支出で変動があります。
■ローン完済後(21年目以降)
ローン返済がなくなることで、家賃収入から経費を差し引いた年間約66万円がそのまま手元に残ります。
| 期間 | 手残り合計 |
| ローン返済中20年 | 約348万円 |
| 完済後10年 | 約660万円 |
| 合計 | 約1,008万円 |
このように、不動産投資はローン返済中は控えめなキャッシュフローながらも、完済後に安定収入が大きく残るのが特徴です。
途中で売却すれば、「売却益」「元本回収」「キャッシュフロー」という複数の利益も狙えるため、NISAよりも「スピード感のある資産増加」が期待できる選択肢といえます。
加えて、キャッシュフローや元本の蓄積を活用して途中で物件を買い足すことで、資産規模をさらに加速的に拡大することも可能です。
新NISAの例
新NISAでは、毎月の積立額・年利・運用期間をそれぞれ変えた複数パターンでシミュレーションしてみました。
つみたて投資の魅力は、時間を味方につける「複利効果」にあります。運用期間が長くなるほど、利息が利息を生み、資産が雪だるま式に増えていくのが特徴です。
たとえば、月1万円の積立でも、年利5%で30年続ければ約830万円まで資産が育ちます。将来のライフプランに合わせて、自分に合った運用スタイルを見つけてみてください。
■毎月1万円で積立した場合
| 積立パターン | 元本 | 運用収益 |
月1万円×20年間 | 240万円 | 328万円 |
月1万円×20年間 | 240万円 | 367万円 |
| 月1万円×20年間 (年利5%) | 240万円 | 411万円 |
■毎月3万円で積立した場合
| 積立パターン | 元本 | 運用収益 |
| 月3万円×20年間 (年利3%) | 720万円 | 985万円 |
| 月3万円×20年間 (年利4%) | 720万円 | 1,100万円 |
| 月3万円×20年間 (年利5%) | 720万円 | 1,233万円 |
■積立期間を30年間に延ばした場合
| 積立パターン | 元本 | 運用収益 |
| 月1万円×30年間 (年利3%) | 360万円 | 583万円 |
| 月1万円×30年間 (年利4%) | 360万円 | 694万円 |
| 月1万円×30年間 (年利5%) | 360万円 | 832万円 |
| 月3万円×30年間 (年利3%) | 1,080万円 | 1,748万円 |
| 月3万円×30年間 (年利4%) | 1,080万円 | 2,082万円 |
| 月3万円×30年間 (年利5%) | 1,080万円 | 2,497万円 |
不動産投資と新NISAを併用するという選択肢

目的が異なるからこそ、併用が効果的
不動産投資は「毎月の安定収入」や「節税・相続対策」に強みがある一方、新NISAは「少額からの資産形成」や「非課税による長期的な資産の増加」に適しています。
このように目的が異なるからこそ、併用することで収入と資産形成をバランスよく進めることができます。比重をどちらに置くかは、ご自身の資産状況や将来設計に応じて柔軟に調整していくのがポイントです。
分散投資によるリスクヘッジが可能に
不動産投資は空室や修繕といった実物資産特有のリスク、新NISAは相場変動や元本割れといった金融市場のリスクがあります。
また、急に現金が必要になった場合、不動産は売却まで時間がかかる一方で、新NISAはすぐに換金できる点も大きなポイントです。
2つの異なる資産クラスに分散投資することで、それぞれのリスクを相互に補完し、資産全体としての安定性を高めることができます。
不動産投資と新NISAの「よくある質問Q&A」

不動産投資や新NISAに興味はあるけれど、いざ始めようとすると「これって大丈夫?」「自分にもできるの?」といった不安が出てくるものです。
ここでは、実際によく寄せられる質問をピックアップし、それぞれの疑問にわかりやすくお答えします。気になっていたポイントがクリアになれば、安心して一歩を踏み出せるはずです。
不動産投資は副業になる?会社にバレない?
原則として、不動産投資は「副業」とみなされることがありますが、会社によっては就業規則の副業禁止に該当しないケースもあります。
ポイントは「事業的規模かどうか」。5棟10室以上の規模になると税務上は事業扱いとなるため、注意が必要です。
また、不動産収入があると、翌年の住民税が増えるため、その情報が会社に通知されることで副業がバレることがあります。
不安がある場合は、事前に就業規則や人事担当者に確認しておくと安心です。
NISAだけで老後資金は足りる?
目標額や運用年数によりますが、NISAだけで老後資金すべてをカバーするのは難しい場合もあります。
年間360万円の投資枠をフル活用し、年5%の運用が20年続いたとしても、1,000万〜2,000万円程度の資産形成が目安です。
かつて話題となった「老後2,000万円不足問題」もありましたが、近年は物価高の影響や長寿化、また少子化による社会保障の不安定化もあり、2,000万円でも足りないという見方が広がっています。
そのため、NISAだけに頼るのではなく、複数の手段を組み合わせた資産形成が重要になってきています。
【参考①:副業・兼業|厚生労働省】
【参考②:No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁】
【参考③:金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」】
ローンを組めない場合の不動産投資は?
現状でローン審査に通らない場合でも、少額の現金で購入できる中古物件や地方物件を検討する方法があります。
また、不動産クラウドファンディングやREITといった「小口不動産投資」を活用するのも一案です。
信用力や収入に不安がある場合は、まずはNISAなどの金融資産運用で実績を積むのも効果的です。資産や信用を徐々に築き、いずれ融資を受けられる体制を整えましょう。
両方やるなら、どちらから始めるべき?
資金力や投資経験によりますが、多くの方にとっては「新NISAから始める」のが現実的です。
少額からスタートでき、損失リスクも比較的限定的。運用の感覚を身につけるには適した入り口です。
一方、すでにまとまった資金がある、もしくは融資が通る状態であれば、不動産投資から始める選択肢もあります。
収益性と節税効果を見込める分、リスク管理ができる人にとっては大きなリターンも狙えます。
まとめ

「不動産投資」と「新NISA」は、どちらも資産形成に有効な手段ですが、性質も必要な資金もまったく異なります。
短期間で資産を大きく増やしたい人や、節税効果を重視する人には不動産投資が向いており、手間をかけずに将来の資金をじっくり育てたい人には新NISAが適しています。
また、目的やライフステージによっては、両方を組み合わせて使うことでリスク分散と安定性を両立することも可能です。
大切なのは、「どちらが良いか」ではなく、「自分に合っているのはどちらか」。本記事を参考に、ぜひご自身の資産形成の方向性を見つけてみてください。
「自分にはどちらが合っているのか知りたい…」という方は、お気軽にご相談ください。あなたに合った資産運用の選択肢をご提案します。





コメント