
「親から土地を相続したけれど、使わずに固定資産税だけ払っている」──そんな方は多いのではないでしょうか。
実は、更地のまま土地を持っていると古家付きの土地よりも固定資産税が6倍高くなると言われています。しかも、使っていない土地ほど相続税評価額が高くなりやすく、将来の税負担が大きくなる恐れもあります。
一方で、土地をうまく活用すれば評価額を下げることができ、収益を生みながら納税資金を準備することも可能です。
この記事では、土地活用が相続税対策として有効な理由から、具体的な方法、評価減の仕組み、そして失敗を防ぐポイントまでを分かりやすく解説します。土地を持つすべての方に知っておいていただきたい内容です。
相続や土地活用について「何から始めればいいかわからない」と感じている方は、ぜひ一度弊社までご相談ください。専門スタッフが、あなたの土地の状況やご家族の事情に合わせて、最適な相続対策をご提案いたします。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- 相続税対策で土地活用が有効といわれる理由
- 基礎控除の縮小で課税が拡大
- 更地のままでは評価額が高くなる
- 「貸家建付地」にすると評価額を下げられる
- 土地活用は「節税」だけでなく「納税資金の準備」にもなる
- 相続税対策で活用される主な土地活用方法7選
- ① アパート・マンション経営
- ② 駐車場経営(コインパーキング)
- ③ 定期借地・事業用定期借地
- ④ 太陽光発電・資材置き場などの短期活用
- ⑤ 医療・介護施設などへの貸地
- ⑥ トランクルームなど小規模活用
- ⑦ 法人化による土地保有(会社設立)
- まだある!土地活用以外で相続税評価を下げる方法
- 共有名義で持つと、1人あたりの評価が下がる
- 小規模宅地等の特例を併用する
- 節税だけでは危険!土地活用で失敗する典型パターン
- 相続税対策を成功させる3つのステップ
- ① 相続財産の全体像を把握する
- ② 専門家に相談する
- ③ 相続後を見据えた「出口戦略」を設計
- まとめ|節税+収益+流動性を兼ね備えた土地活用を
相続税対策で土地活用が有効といわれる理由

まずは、なぜ土地活用が相続税対策として注目されているのか、その背景と仕組みを確認していきましょう。
基礎控除の縮小で課税が拡大
2015年の税制改正で、相続税の基礎控除額は大幅に引き上げられました。
- 改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人
- 改正後:3,000万円+600万円×法定相続人
(参考:国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)」)
その結果、都市部を中心に「土地を持っているだけで課税対象になる」ケースが増えています。
たとえば、路線価60万円/㎡の土地を100㎡相続するとしましょう。この場合の評価額は、「 60万円 × 100㎡ = 6,000万円 」です。
この土地を相続人2人で受け継ぐ場合、基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円です。
6,000万円 − 4,200万円 = 1,800万円 が課税対象になります。
相続税は一律ではなく、課税対象価格によって税率が異なります。
課税価格(1人あたり) | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(出典:国税庁「相続税の速算表」)
まず、相続税は「相続人の法定相続分」で按分して計算します。
1,800万円 ÷ 2人 = 900万円/人
この900万円を表に当てはめると、税率は10%。
→ 900万円 × 10% = 90万円(1人あたり)
2人分で合計約180万円の相続税が課されます。
更地のままでは評価額が高くなる
土地の相続税は、実際の市場価格ではなく「路線価」で評価されます。そして、その評価額を左右する大きなポイントが、その土地に住宅が建っているかどうかです。
住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」という軽減措置があり、200㎡以下の部分については固定資産税が6分の1に減額されます。しかし、更地のままでいたり、空き家のまま適切な管理を怠ったりすると、この特例が受けられず、評価額がそのまま満額で課税されます。
(参考:固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置)
「貸家建付地」にすると評価額を下げられる
「土地活用でアパートを建てると節税になる」と聞いたことはありませんか。実はそれには、きちんとした仕組みがあります。
アパートや賃貸住宅を建てて他人に貸す土地にすると、その土地は「貸家建付地」と呼ばれるようになります。
この状態では、借地権や借家権といった第三者の権利が発生するため、土地の所有者が自由に使えなくなり、その分だけ土地の評価額が下がるのです。
国税庁によると、貸家建付地の評価は次のような式で計算されます。
貸家建付地の評価額 = 自用地評価額 × {1 −(借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)}
上記だけでは少し難しいので、解説を交えてみていきましょう。
たとえば、さきほどの路線価60万円/㎡の土地(100㎡)を想定すると、用地評価額は 6,000万円です。
この土地をアパートとして他人に貸している場合、「借地権割合を60%」「借家権割合を30%」「賃貸割合を100%」としましょう。
- 借地権割合(60%):その土地を借りて使う人(入居者)にどの程度の権利価値があるかを示す割合です。都市部ほど高く、所有者の自由度が低いほど評価が下がります。
- 借家権割合(30%):建物を借りて住む入居者(借家人)の権利の強さを示します。通常は30%とされています。
- 賃貸割合(100%):その土地のうち、どのくらいの部分を実際に貸しているかを表します。全部貸していれば100%です。
6,000万円 × {1 −(0.6 × 0.3 × 1.0)} = 6,000万円 × (1 − 0.18) = 4,920万円
つまり、貸家建付地にするだけで評価額が約18%下がることになります。土地の評価が下がるということは、その分だけ相続税の課税対象も減るということです。
(参考:No.4614 貸家建付地の評価|国税庁)
土地活用は「節税」だけでなく「納税資金の準備」にもなる
土地を貸したり、アパートを建てたりすることで、相続税評価額を抑えながら家賃収入が入る仕組みを作ることができます。この収入は、将来の相続時に納税資金として備えることが可能です。
つまり、保有する不動産を現金化せずに、資産を守る手段としても有効です。土地活用は「節税」「収益」「納税資金確保」の3つを同時に叶える方法なのです。
相続税対策で活用される主な土地活用方法7選

では、具体的にどのような土地活用の方法があるのでしょうか。以下で代表的な7つの活用方法を紹介します。
① アパート・マンション経営
相続税対策として最も一般的なのが、アパートや賃貸マンションを建てて貸す方法です。先述のとおり、建物を建てて人に貸すことで、土地は「貸家建付地」として評価され、相続税の対象額を抑える効果があります。
また、固定資産税や管理費などの維持コストを家賃収入でまかなえば、「節税」と「安定収益」を同時に実現できます。
一方で、空室リスクや修繕費の負担があるため、長期的な収支シミュレーションが欠かせません。エリアの入居需要、金融機関との融資条件、建築コストなどを総合的に試算することがポイントです。
② 駐車場経営(コインパーキング)
アパートを建てるほどの資金をかけずに始められるのが駐車場経営です。
舗装や精算機などの初期費用はかかりますが、更地のままよりも収益性が高く、柔軟な活用が可能です。
ただし、駐車場は「住宅用地の特例」や「貸家建付地の評価減」が適用されないため、固定資産税や相続税の評価額は更地扱いになります。
節税というよりは、「将来的な土地活用までの一時的な収益確保」として取り入れるのが現実的です。
③ 定期借地・事業用定期借地
「アパートを建てる資金はないけど、なにか土地活用したい」──そんな方に向いているのが定期借地契約です。
たとえば、商業施設やマンションの建設用地として土地を50年ほど貸す「一般定期借地権」、あるいはオフィスや店舗などに10〜20年貸す「事業用定期借地権」があります。
契約期間が終われば土地が返ってくるので「収益を得つつ、将来はまた自分の資産に戻す」という運用が可能です。
こちらも借地権を設定することで、相続税評価額が下がる効果も期待できます。
ただし、定期借地は事業者にとって使いづらい側面もあるため、すぐに借り手が見つかるとは限りません。
また、定期借地契約には法的な制約や契約更新不可のルールなど、一般の賃貸契約とは異なる点が多くあります。そのため、実際に貸し出す前には、不動産会社や税理士、司法書士などの専門家に相談しながら進めましょう。
④ 太陽光発電・資材置き場などの短期活用
遊休地(所有しているが利用されていない土地)を短期的に収益化する方法として、「太陽光発電」や「資材置き場」としての活用もあります。
初期投資は必要ですが、固定収入を得ながら土地の維持費をまかなえる点がメリットです。
ただし、これらは「貸家建付地」や「住宅用地の特例」の対象外です。
課税対象額の縮小というよりも、どちらかというと所得税の節税(減価償却)や安定運用の観点から検討する方法といえます。
太陽光発電については、多くの自治体が条例を制定しています。景観や自然環境への配慮など、設置場所での規制をきちんと調べるようにましょう。
⑤ 医療・介護施設などへの貸地
近年増えているのが、クリニックや介護施設向けに土地を貸す方法です。
長期契約で安定した地代収入が得られるうえ、社会的にも需要が高く、地域に貢献できる点も魅力です。
借地契約を結ぶことで土地の評価額が下がる場合もありますが、契約内容によっては返還時のリスクや再利用の制限が生じることがあります。
事業者の信用力や契約期間、用途制限などを慎重に確認しておきましょう。
⑥ トランクルームなど小規模活用
「土地が狭くてアパートも駐車場も難しい」という場合は、トランクルームなど小規模活用が選択肢になります。都心部であれば、駐輪場もよいでしょう。
狭小地や変形地でも設置しやすく、初期費用を抑えて手軽に収益化できる点が魅力です。
ただし、収益は限定的であり、管理費やメンテナンスコストを差し引くと利益が残りにくいケースもあります。
周辺需要をしっかりリサーチして、適切な料金設定と管理体制を整えることが大切です。
⑦ 法人化による土地保有(会社設立)
土地を個人で所有せず、不動産管理会社を設立して法人で保有する方法もあります。会社を通じて賃貸経営を行うと、相続時の評価額を抑えやすくなるのが法人化の大きなメリットです。
なぜ評価が下がるのかというと、相続の対象が土地ではなく「会社の株式」になるからです。
株式の価値は、会社全体の資産から借入金などを差し引いた「実際に残る資産額」で計算されます。そのため、土地をローンで購入していたり、建物の減価償却が進んでいたりすると、結果的に株式の評価が土地の時価より低くなるのです。
また、家族で株式を分けて持つ場合は、1人あたりの持ち分が小さいほど評価が下がる仕組みもあります。
相続や土地活用について「何から始めればいいかわからない」と感じている方は、ぜひ一度弊社までご相談ください。専門スタッフが、あなたの土地の状況やご家族の事情に合わせて、最適な相続対策をご提案いたします。
まだある!土地活用以外で相続税評価を下げる方法
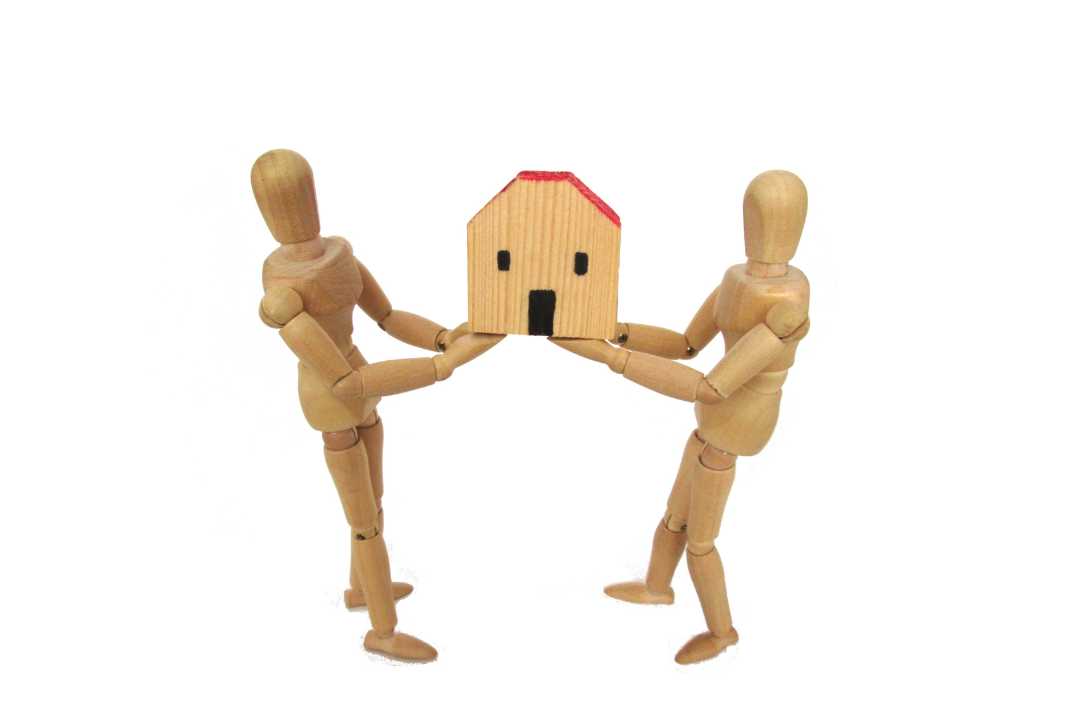
ここまで紹介してきたように、アパート経営や定期借地などの土地活用は、相続税評価額を下げる有効な手段です。
しかし、実はそれ以外にも評価額を抑える方法があります。
本章では、「土地をどう活用するか」ではなく、「どう所有し、どう制度を使うか」という視点から、代表的な2つの方法を紹介します。
共有名義で持つと、1人あたりの評価が下がる
土地を家族で共有名義にしておくと、それぞれの持分ごとに評価されるため、単独で所有するよりも1人あたりの評価額を抑えられる可能性があります。
国税庁の評価基準でも、共有の場合は「各人の持分に応じて評価する」とされており、単独で土地を自由に売却・利用できないことから、実質的に価値が低く見なされるケースがあります。
ただし、共有にすると売却や再開発が難しくなる、相続人間で意見が合わないなどトラブルの火種になることも。将来の分割や売却のルールを事前に決めておくことが大切です。
小規模宅地等の特例を併用する
もうひとつ、ぜひ知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」です。
これは、被相続人(亡くなった方)の自宅や事業用地、賃貸用地などについて、一定の面積まで相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
区分 | 減額割合 | 面積上限 |
居住用 | 80%減 | 330㎡まで |
事業用 (貸付事業以外の事業用宅地等) | 80%減 | 400㎡まで |
貸付事業用 | 50%減 | 200㎡まで |
(出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」)
たとえば、相続時に4,000万円の自宅土地(330㎡)があった場合、この特例を使えば評価額は実質800万円(▲80%)になります。
節税効果は非常に大きく、他の土地活用と併用することでさらに負担を軽減できます。
ただし、
- 相続開始3年以内に取得した土地は原則対象外(3年ルール)
- 賃貸用地は相続時点で実際に貸している必要あり
といった細かな要件があるため、戦略的に動く必要があるでしょう。
節税だけでは危険!土地活用で失敗する典型パターン

相続税の節税を目的に土地活用を始めても、結果的に資産を減らしてしまうケースは珍しくありません。
多額の借入をしてアパートやマンションを建てたものの、いざ始めてみると、思ったより入居が決まらずローン返済だけが重くのしかかることがあります。
さらに年数が経つと、屋根や外壁、給排水設備の修繕が必要になり、数百万円単位の出費が発生することも。家賃収入だけでは足りず、気づけば相続税のために残していた貯蓄を取り崩す羽目になることさえあります。
土地活用は「建てれば安心」「節税できれば成功」ではありません。10年後、20年後まで見据えた長期的な事業計画が、相続対策を成功に導くカギです。
相続税対策を成功させる3つのステップ
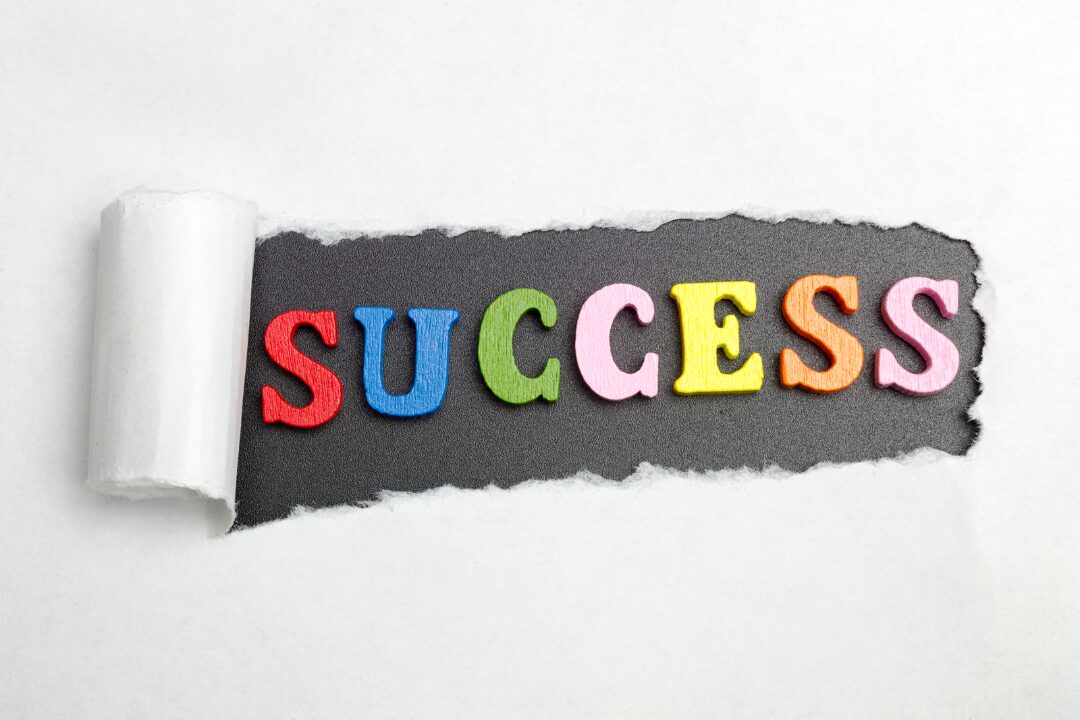
相続税の節税戦略を考えるうえで重要なのは、
- 資産全体の見える化
- 専門家の活用
- 将来を見据えた設計
という段階的なステップを踏むことです。この3つのステップを意識すれば、無理のない形で節税・資産保全・家族間トラブルの防止を同時に実現できます。
① 相続財産の全体像を把握する
相続対策の最初のハードルは「そもそも親の資産がどのくらいあるのか分からない」ということではないでしょうか。いくら親子でも、現金や不動産、保険、投資などお金の話はなかなか切り出しにくいものです。
しかし、ここを避けて通ると、いざ相続が発生したときに混乱する原因になります。
まずは「相続対策をしておきたい」「後々子どもが困らないように」といった「親の安心感につながる会話」から始めてみましょう。
話しづらい場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなど第三者を交えて話すとスムーズに進みます。
資産がある程度見えてきたら、現金・預貯金・土地・建物・保険などを一覧化し、実際に相続税のシミュレーションを行ってみましょう。「どの資産に相続税がかかりそうか」「どの土地をどう活用すべきか」が、具体的に見えてくるはずです。
② 専門家に相談する
相続税対策は、自分だけで考えるにはあまりにも複雑です。
税金以外にも、不動産の評価や登記の手続きなど分野が違う専門知識がいくつも絡みます。
相談の中心になるのは税理士ですが、登記や名義の変更が必要なときは司法書士の力も必要です。また、状況によっては家族信託で将来の認知症リスクに備える必要性もあるでしょう。
「家族にどう資産を残していくか」まで一緒に考えられる複数の相談先を選ぶことが、相続対策の大きな一手になります。
③ 相続後を見据えた「出口戦略」を設計
相続税対策を成功させるうえで忘れてはいけないのが、相続後を見据えた出口戦略。あらかじめ「何年後にどう使うのか」という出口の方向性を決めておくことが大切です。
たとえば、10年後に売却して老後資金に充てたいのか、子どもに引き継いで賃貸経営を続けたいのか。その答えによって、今とるべき土地活用や法人化の方法はまったく違ってきます。
将来の市場や家族構成は変わっていくものです。だからこそ、「何年後にどうしたいか」を決めてから逆算して柔軟な対策を立てることが、結果的にムダのない相続対策につながります。
まとめ|節税+収益+流動性を兼ね備えた土地活用を

相続税対策において大切なのは、「節税になるから」といった一面的な判断ではなく、節税・収益・流動性の3つをバランスよく両立させることです。
土地をどう活かすかで、相続税の負担も、将来の資産の残り方も大きく変わります。アパート経営や定期借地などの活用だけでなく、共有名義や小規模宅地等の特例、法人化といった制度面も上手に組み合わせることで、「無理なく・賢い相続対策」が可能になります。
そして何より大切なのは、早めに動き出すこと。
親と資産の話をするのは気が重いかもしれませんが、「将来困らないために今話しておく」その一歩が、家族の負担軽減につながります。
節税だけでなく、「残す人」「受け継ぐ人」双方が納得できる形を目指して、今日からできることを少しずつ始めていきましょう。
相続や土地活用について「何から始めればいいかわからない」と感じている方は、ぜひ一度弊社までご相談ください。専門スタッフが、あなたの土地の状況やご家族の事情に合わせて、最適な相続対策をご提案いたします。





コメント