
不動産の承継は、親世代と子世代で全く異なる「悩みのポイント」があります。
親側は「そろそろ自分は引退したい」「元気なうちに引き継ぎたい」と思うもの。一方で、子側は引き継いだ「その先」の不安を抱えがちです。
この記事では、その「親と子が持つそれぞれの不安」を丁寧にほどきながら、家族みんなが納得しやすい承継の進め方をまとめました。
なお、以前は親世代の視点で書いていましたが、今回は子世代(受け継ぐ側)のリアルな悩みも織り交ぜて解説しています。
もし「どこから手をつければいいか分からない」「家族で話をまとめられる自信がない」などの不安があれば、どうぞお気軽に弊社へご相談ください。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- アパート承継で多くの家族がつまずく「5つの問題」
- ① 収支関係が分からない問題
- ② 兄弟で誰が継ぐか問題
- ③ 遺産分割がまとまらない問題
- ④ 建物・修繕履歴状態が不明問題
- ⑤ 相続税の納税資金が足りない問題
- アパート承継の全体像|3つの三本柱で整理
- ① 権利の承継
- ② 運用の承継
- ③ 財務の承継
- アパート承継方法の選び方
- 相続
- 生前贈与
- 家族信託
- 共有(兄弟相続)
- アパート承継後の90日間でやるべきこと|実務ロードマップ
- 【0〜7日】管理会社・金融機関への連絡
- 【8〜30日】契約関係の引継ぎ・入居者周知
- 【31〜60日】収支確認・修繕計画の見直し
- 【61〜90日】税務書類・確定申告準備
- 兄弟で承継する場合の揉めない8つのポイント
- アパート承継の失敗事例
- 相続後に大規模修繕で想定外の支出が発生したケース
- まとめ|アパート承継は「方法選び」よりも「準備力」
アパート承継で多くの家族がつまずく「5つの問題」
いざ家族が集まってアパートの話し合いをすると、みなさんほぼ必ずといっていいほど同じところでつまずきます。誰が悪いわけでもなく「専門知識が足りない」という理由がほとんどです。ここでは、弊社にもご相談が多い5つの問題を解説します。
① 収支関係が分からない問題
まずは、「そもそも収支がいくらなのか分からない」という問題。
親が管理会社に任せきりで、いざ相続の話になると「結局、このアパートは黒字なのか?利回りはどれぐらいなのか?」が説明できないのはよくある話です。
不動産経営は「家賃収入=儲け」ではありません。
実際には、修繕費・固定資産税・管理費・保険料・ローン返済など、毎月・毎年いろいろなお金が出ていきます。
収支が見えないままだと、
- 修繕にいつのタイミングで、いくら必要なのか
- ローン返済がどのくらい残っているのか
といった大事な判断もできず、話が前に進みません。
まずは、通帳・管理会社からの送金明細・保険の控えなど、お金の流れを全て「見える化」することが最初のステップです。
② 兄弟で誰が継ぐか問題
次に出てくるのが、「誰がアパートを引き継ぐのか」という問題。
兄弟それぞれ仕事や家族、住まいの状況が違います。遠慮し合ったり、逆に押し付けられるように感じたりと、意外とデリケートなようです。
「引き継ぐ」と聞くと、すべてを一人で担うものだと誤解されますが、方法はそれだけではありません。
- 名義を引き継ぐ人
- 経営を中心で担う人
- 事務作業を協力する人
など、経営に関する役割を分担することもできます。兄弟間で「誰が一任するか」と考えるから、つまずいてしまうのです。
まずは、兄弟それぞれが「どの程度だったら関われるか」を素直に出し合い、「任せる」「手伝う」のバランスを整理しましょう。
③ 遺産分割がまとまらない問題
そして多くの家族が悩むのが、「遺産分割の話がまとまらない」という問題。
これは、不動産が現金のようにキレイに分けられないがゆえに起こるトラブルです。どうしても「もらう人」と「もらわない人」の間で不公平感が出やすくなります。
遺産分割がまとまらない理由は、ほとんどの場合で以下の2つです。
- 物件がいくらなのか分からない
- 継がない兄弟にいくら渡せばいいのか分からない(資金が準備できない)
この2つが曖昧なまま話し合いを始めてしまうと、意見がまとまりません。
まずは、「正確な評価額を出すこと」が大前提です。評価額の算出には、相続税評価や収益還元法などを使いますが、これには専門知識が必要です。
不動産会社や税理士などの第三者に入ってもらい、客観的な数字を出すところからスタートしましょう。
そしてもう一つの問題が「継がない兄弟に代償金をどう支払うか」。
- 手元の貯金で払えるのか
- 銀行で借りればいいのか
- それとも分割で兄弟に返していくのか
といった「支払い方」まで現実的に考えなければなりません。代償金は「金額」と「支払い方法」の両方が決まって、はじめて話がまとまります。
これらの要点を冷静に整理して、支払い金額や方法を家族で共有できると、遺産分割は一気に進みやすくなります。
④ 建物・修繕履歴状態が不明問題
さらによくあるのが、「建物が今どんな状態なのか分からない」という問題。
親が長年見てきたアパートについて、
「外壁はいつ塗り替えたか?」
「給湯器をいつ変えたか?」
といった細かい履歴を記録していないケースがあります。
家族と話し合いをする前に、管理会社の点検内容、修繕の領収書、設備交換の記録などの情報をまとめておきましょう。
⑤ 相続税の納税資金が足りない問題
最後に、「相続税の支払いに必要なお金が足りない」という問題。
アパートの相続で、思っていた以上に相続税がかかることは珍しくありません。
相続税の概算を把握しておらず、「納税のために物件を売らざるを得ない」という本末転倒な事態は避けたいものです。
納税には現金を用意する必要がありますが、貯蓄から支払うのが難しい場合には、借入や定期積立の解約なども視野に入れてみましょう。
アパート承継の全体像|3つの三本柱で整理
アパート経営を子へバトンタッチするには、「権利」「運用」「財務」の3つを整理する必要があります。この3つがそろって初めて、スムーズな承継ができます。
① 権利の承継
最初に整理すべきなのが、「誰の名義にするか」という権利の部分です。アパートの所有権は、単に「持ち主になる」という意味だけではありません。
売却・建て替え・大規模修繕など、物件に関わる最終決定をする権利です。
ここが複数人の共有名義になると、売るにも建て替えるにも、共有者全員の承諾が必要になります。
また、兄弟が遠方にいればそのたびに連絡と手続きが必要です。関係があまり良くない場合は、そもそも承諾を得ることすら難しいこともあります。
これまでも、物件を相続する兄弟で「共同名義」にすることで、多くのトラブルが発生しています。
つまり、所有権の持ち方ひとつで、売却のしやすさや将来の選択肢が大きく変わるということです。
② 運用の承継
名義が決まっても、実際に負担が大きくなるのは「運用」の部分です。
アパート経営には、入退去対応、家賃管理、修繕の判断、管理会社とのやり取りなど、日々の細かな業務がつきものです。
黒字を維持するには、不動産投資の根本的な知識と理解が必要になります。
親が「長年の感覚」でこなしていた作業を、いきなり子世代が同じようにできるとは限りません。
承継では、
- 運営のどこまでを自分が担い、どこから管理会社に任せるか(業務の線引き)
- 家賃設定や募集条件をどう判断するのか(エリア市況の理解)
- 修繕判断や日々の管理で迷ったときの判断基準をどう共有するか
こうした実務の整理が必要です。
③ 財務の承継
アパート経営を引き継ぐには、「数字の理解」が必須です。ローン返済中の物件であれば、尚更です。
毎月の返済額や残債などを把握していないと、継いだあとに家計を圧迫する可能性があります。
家賃収入がどれだけあっても、修繕費や税金に備えられていなければ黒字は続きません。
財務の承継では、
- 家賃収入をどれだけ修繕積立に回すか(キャッシュフロー管理)
- 利回りの考え方や、黒字・赤字の見極め方
- ローン残高と返済計画の整理
- 建物の耐用年数を踏まえた出口戦略(売却・建て替え)
こうした「不動産投資でお金が回り続けるための基本」を整理することが重要です。
アパート承継方法の選び方
アパートの引き継ぎ方は、家族の状況や物件の状態、税金の負担によって最適解が変わります。
ここでは、代表的な4つの承継方法を分かりやすく整理しながら、どんな家庭にどの方法が向いているのかを解説します。
相続
相続は、アパートの引き継ぎ方法として一番選ばれるパターンです。
親が元気なうちはこれまで通り運営を続けてもらえますし、亡くなった後に名義を移すだけなので、慌てて準備する必要がありません。
一方で、相続税の支払い方や兄弟間の意見がまとまっていないと、思った以上に調整が大変になることもあります。
区分 | 内容 |
メリット |
|
デメリット |
|
相続を選ぶときは、相続税の見通し・兄弟間の合意・物件状態の把握の3つがそろっているかどうかがポイントです。
生前贈与
生前贈与は、親が元気なうちにアパートの名義を移す方法です。アパート経営のやり方を直接学べるため、引き継ぎ後もスムーズに運営ができるでしょう。
ローンが残っている場合は金融機関の承認が必要になるため、ここは注意ポイントです。
区分 | 内容 |
メリット |
|
デメリット |
|
生前贈与は、「親がまだ判断できるうちに承継を進めたい」「兄弟間の調整を早めに終わらせたい」という家庭に向いています。
家族信託
認知症になると売却や修繕の判断ができなくなり、物件が「動かせない資産」になる可能性があります。
家族信託は、その事態を避けるために運用の決定権だけを子に移せる仕組みです。
区分 | 内容 |
メリット |
|
デメリット |
|
ただし、信託契約が曖昧だと機能しないため、内容を熟知した専門家と一緒に内容を詰めることが必要です。
共有(兄弟相続)
兄弟全員で「共有名義」にする方法は、一見すると公平に見えます。
しかし、実務では注意が必要です。
共有にすると、売却・建て替え・大規模修繕などは全員の承諾が必要になります。
関係性が悪化してしまうと、承諾すら得られず、売却したくても手放せなくなってしまいます。
区分 | 内容 |
メリット |
|
デメリット |
|
共有は、「兄弟間の関係が良好」かつ「長期的な協力が確実に見込める」という家族に向いています。
現状、すでに「兄弟関係が悪い」「協力的でない」という家族にはおすすめできません。
もし「どこから手をつければいいか分からない」「家族で話をまとめられる自信がない」などの不安があれば、どうぞお気軽に弊社へご相談ください。
アパート承継後の90日間でやるべきこと|実務ロードマップ
アパートを引き継いだ直後は、思った以上にやることがあります。最初の1週間は関係先への連絡、1か月目は契約関係の整理、2か月目はお金と建物のチェックと続きます。
実務で混乱しやすいポイントを時系列でまとめたので、順番に進めてみてください。
【0〜7日】管理会社・金融機関への連絡
■管理会社へ名義変更と緊急連絡先を伝える
承継後、まずは正式にオーナーを変更した旨を管理会社へ伝えましょう。同時に、新オーナーの連絡先・メール・振込口座を共有します。
「誰に連絡すればいいか」が把握できていないと、緊急時のトラブル対応が止まってしまいます。変更後、最初にやるべき大事なステップです。
■金融機関へ相続発生の報告と手続き確認(※ローン返済中の場合のみ)
- 相続が発生したことを担当者へ早めに報告する
- 金融機関から提示される「必要書類リスト」を受け取り準備を進める
- 名義変更や返済の引継ぎ手続きのスケジュールを確認する
相続が発生したら、金融機関にはできるだけ早く連絡を入れておくと安心です。
連絡を入れると、銀行側から戸籍関係・遺産分割協議書・印鑑証明など、揃えるべき書類の一覧が提示されます。この段階では、名義変更そのものよりも「いつ・どんな書類が必要か」の確認作業が中心です。
団信(団体信用生命保険)については、加入者(被相続人)が亡くなった時点で「保険会社が判断を行う段階」に入ります。金融機関に伝えた後は、今後の案内を待ちましょう。
ローンの残高がどう処理されるかなど、銀行側の確認を待ちながら進めることになります。
【8〜30日】契約関係の引継ぎ・入居者周知
■賃貸借契約の引継ぎと重要書類の確認
承継後は、まず物件に関する「契約書一式」を手元で整理しましょう。
- 管理委託契約(不動産会社とオーナーで締結)
- 賃貸借契約書(入居者とオーナーで締結)
- 設備保証書
- 火災保険
など、前オーナーが締結していた書類を確認し、必要に応じて更新・名義変更を行います。特に賃貸借契約は、今後の入居者とのやりとりに関係する重要書類です。
敷金の預かり状況、家賃振込日、特約事項などをしっかり把握しておくことで、後のトラブル防止になります。
■入居者への周知(管理会社経由でOK)
入居者へは、管理会社を通して「オーナー変更のお知らせ」を送付します。
突然の変更は不安を招きやすいため、
- 名義変更が完了したこと
- 今後の連絡窓口は変わらないこと
- 家賃振込先に変更がある場合はその案内
を丁寧に伝えることがポイントです。この周知をしておくと、スムーズに新体制へ移行できます。
【31〜60日】収支確認・修繕計画の見直し
■収支の現状を「新オーナー目線」で見直す
この時期は、物件の収支状況を詳しく確認しましょう。
- 家賃収入の入金状況
- 管理費・修繕費・保険料などの支出
- 前オーナーの確定申告書(あれば)
これらを照らし合わせ、どの程度の黒字・赤字になっているのかを把握します。
承継直後はバタバタして忙しいので、やることが終わったら取り掛かってみましょう。
■修繕計画の見直しと優先順位づけ
収支を把握したら、次は建物の状態を管理会社と一緒にチェックします。
建物全体の大規模修繕から室内の内装リフォームまで、近い将来で修繕が必要になりそうな部分をリスト化しましょう。
- どの箇所から修繕するか
- どの程度の費用か
- いつ実施するのか
を見える化します。
修繕は、準備次第で数十万円単位の差が出るため、早めに方向性を決めておくことが安定経営につながります。
【61〜90日】税務書類・確定申告準備
■必要書類の整理と、税理士への引継ぎ(任意)
相続した不動産は、翌年の確定申告で「不動産所得」として申告します。
ただし、確定申告の時期(2〜3月)は毎年決まっているため、相続のタイミングによっては“1年以上先の申告”になる場合もあります。
そこで、この61〜90日の期間では、「いざ申告の時期になったときに困らないよう、今から土台を整える」 というイメージで進めていきます。
準備しておく資料は、たとえば次のとおりです。
- 前オーナーの収支データ(わかる範囲で)
- 管理会社が作成する年間収支報告書
- 修繕費・保険料などの領収書
- 相続に関する資料(固定資産税評価・路線価・遺産分割の内容など)
これらの書類が整理されていると、申告作業がスムーズです。
税理士へ依頼する予定がある場合は、このタイミングで一度相談しておくと、書類の抜け漏れを防げます。
また、税理士は年末ぐらいから確定申告に向けて繁忙期に入ります。直前の依頼は断られてしまう可能性がありますので、余裕を持って相談するようにしましょう。
もし「どこから手をつければいいか分からない」「家族で話をまとめられる自信がない」などの不安があれば、どうぞお気軽に弊社へご相談ください。
兄弟で承継する場合の揉めない8つのポイント
兄弟でアパートを引き継ぐ場合、トラブルを防ぐコツは「最初の話し合いで方向性をそろえること」。
兄弟間の衝突を避け、スムーズに承継を進めるには、以下8つのポイントを意識することが重要です。これは、兄弟間で認識をそろえるための「チェックリスト」のようなものです。
兄弟間で揉めない8つのポイント
- 共有名義を避ける
- 経営を担う人を最初に決める
- 代償分割は支払い方法と時期を明確にしておく
- 評価額と費用負担を数字で可視化
- 第三者の専門家を交えて話し合いを中立化
- 承継後の役割を細かく決める
- 売却も選択肢として整理しておく
- 遺言・信託で事前に方針を固定する
兄弟での承継は、最初に方針をそろえておくほどトラブルが起きにくくなります。上記8つを「最初に確認しておくポイント」として共有しておくと、役割や負担があいまいにならず、後からのすれ違いを防げます。
早めに方向性を固めておくことが、兄弟間の円満な承継につながります。
アパート承継の失敗事例
ここで1つ、アパートの引き継ぎ後に発生したトラブル事例を紹介します。
相続後に大規模修繕で想定外の支出が発生したケース
相続して数週間たった頃、管理会社から突然連絡が入りました。「入居者から連絡を受け、雨漏りを確認した」という報告です。
物件は築25年の木造アパート。外観がきれいに見えていたため、家族は誰も屋根の状態を気にしていませんでした。
管理会社によれば、「屋上の防水層が劣化していて、雨水が屋根の内部に入っています。」とのこと。
詳しい点検を依頼すると、雨漏りしていた部屋の真上にあたる屋根部分で、下地(野地板)が明らかに湿って柔らかくなっている箇所が見つかりました。屋根裏を確認すると、断熱材まで水を吸っており、天井に伝っている状態だったそうです。
さらに周囲を調べると、ベランダの防水層にも細かい亀裂があり、そこからも雨水が回り込んでいる箇所が判明。
管理会社からは、「部分的に直しても再発の可能性が高いので、屋根のカバー工法と防水のやり直しが必要です」と説明を受けました。改修費はなんと200万円。
家族にとっていちばんの問題は、「この200万円をどう払えばいいのか」という現実的な課題でした。入居者が困っているため、悠長に検討する余裕もありません。
本当は借入は避けたかったのですが、すぐに現金を用意できなかったため、リフォームローンを利用することに。
結果として、家賃収入が安定する前から毎月の返済が発生。承継直後から資金繰りが苦しくなる「逆スタート」になってしまいました。
このケースは、承継の準備不足がそのまま資金トラブルにつながった典型例です。
まとめ|アパート承継は「方法選び」よりも「準備力」
アパート承継は、どの方法を選ぶかよりも「事前の準備」が結果を大きく左右します。
- 収支
- 建物の状態
- 兄弟間の方針
- 相続税の見通し
これらを早めに整理しておけば、多くのトラブルは防げます。反対に、準備が不足すると、修繕や資金の問題に追われかねません。
まずは現状を正しく把握し、必要な手続きを一つずつ前倒しで進めること。いざというタイミングで焦らないよう、余裕を持って準備していきましょう。
もし「どこから手をつければいいか分からない」「家族で話をまとめられる自信がない」などの不安があれば、どうぞお気軽に弊社へご相談ください。








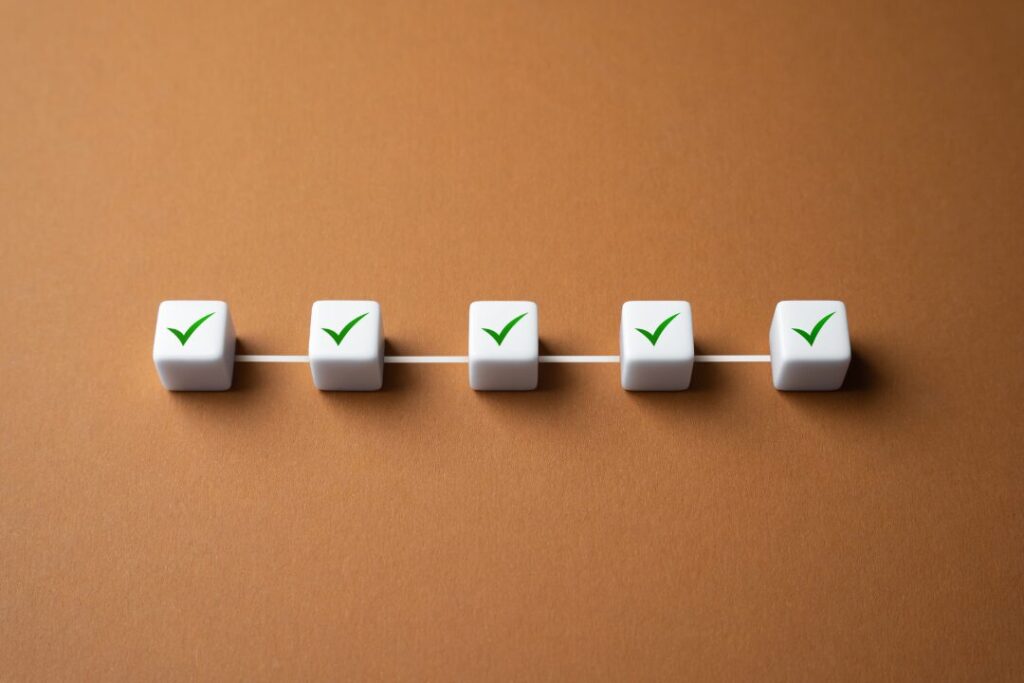
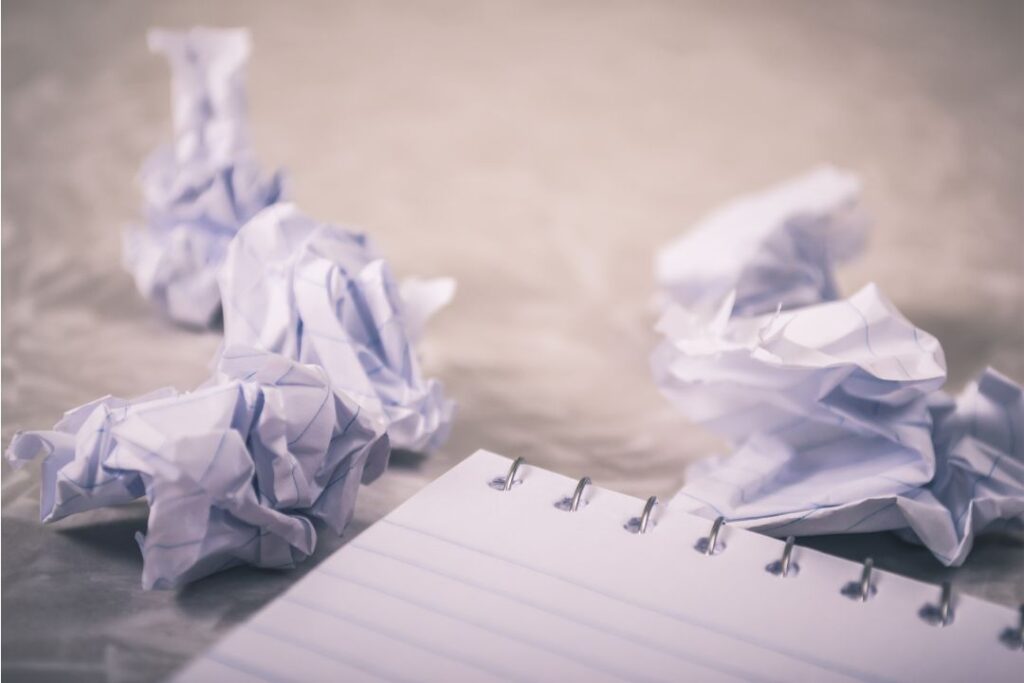

コメント