
土地を売却する際、「測量は必須なのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。
実は、測量は売主の義務ではありません。しかし、測量をしないことで、売却後に「面積が違う」「境界が曖昧で近隣住人と揉めている」といったトラブルが発生するリスクがあります。
特に、境界が不明確な土地や相続で取得した土地などは、事前に測量を行うことでスムーズな売却が可能です。
この記事では、土地の測量が必要となるケースや、測量の種類、費用相場、依頼方法まで詳しく解説します。測量をするかどうか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- 土地売却時の測量は必須?
- 測量とは何か
- 測量士と土地家屋調査士の違い
- 測量は売主の義務ではない
- 土地の測量が必要なケースとその理由
- 1.境界が不明確な土地の売買
- 2.相続した土地の分割
- 3.隣地との境界トラブル防止
- 4.高額取引
- 5.登記簿の面積と異なる
- 3種類の測量図のちがい
- 1.地積測量図
- 2.現況測量図
- 3.確定測量図
- 測量にかかる期間・費用相場
- 所要期間
- 費用目安
- 測量費用が高額になるケース
- 隣接地とトラブルがある
- 隣接地の所有者が多い
- 土地の形状が複雑
- 測量の依頼方法と流れ
- 1.土地家屋調査士に依頼する
- 2.必要書類をまとめる
- 3.隣接地の所有者へ挨拶に行く
- 4.土地の事前調査をする
- 5.隣地所有者の立会いのもと測量する
- 6.境界標を設置する
- 7.測量図を作成・登記を行う
- 隣地の所有者に測量の立ち合いを拒否されたらどうする?
- 筆界特定制度を利用する
- 境界確定訴訟を行う
- まとめ
土地売却時の測量は必須?

冒頭にもお伝えしたように、土地売却時の測量は必須ではありません。
まずは基礎知識として、下記の2点について理解を深めましょう。
測量とは何か
測量とは、土地の面積や境界を正確に測定し、図面に記録する作業のことです。
測量にはいくつかの種類があり、簡易的なものから公的な証明として活用できるものまでさまざまです。一般的に、土地の売買や登記の際には、現況測量図や確定測量図が必要になることがあります。
測量を行うことで、土地の正確な面積や境界線を把握できるため、売却後のトラブルを防ぐことができます。特に、隣地との境界が不明確な場合は、測量を実施し、隣地所有者と合意を取ることで、後のトラブル回避につながります。
測量は専門的な知識や技術、資格が必要なので、土地家屋調査士に依頼して行うのが一般的です。
測量士と土地家屋調査士の違い
土地売却時に測量が必要になると、「測量士」と「土地家屋調査士」という専門職が登場します。
土地を売却する際には、土地家屋調査士に依頼するケースが多く、特に境界確定や登記が必要な場合は、土地家屋調査士が適任です。一方で、地形測量や詳細な土地面積を確認する際には、測量士に依頼することが適切です。
両者の違いをわかりやすくまとめると、以下の通りです。
| 項目 | 測量士 | 土地家屋調査士 |
| 主な役割 | 土地の測量と図面作成 ・基準点測量 ・地形測量 ・土地測量 | 境界確定や登記関連の測量と書類作成 ・境界確定測量 ・地積更生登記 ・表示登記 |
| 活躍するシーン | 公共事業や土木工事、土地の測量 | 不動産登記や境界トラブルの解決 |
| 資格の管轄 | 国土交通省 | 法務省 |
必要に応じて適切な専門家に依頼し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
測量は売主の義務ではない
土地を売却する際、測量は必須ではなく、法律上の義務もありません。つまり、売主が測量をしなくても土地の売買契約は成立します。
ただし、測量を行わないことで、売却後に「面積が登記簿と異なる」「境界線が不明確で隣地所有者とトラブルになる」といったリスクが生じる可能性があります。
特に、境界線が不明確な土地や、登記簿面積と実測面積に差がある土地の場合は注意が必要です。そのような状況下では、測量を行うことで買主の不安を解消し、スムーズな売却につながります。
また、金融機関から融資を受ける場合や、不動産会社が買取を行うケースでは、確定測量図の提出を求められることが多いです。そのため、取引内容によっては、売主が事前に測量を検討することが望ましいケースもあります。
土地の測量が必要なケースとその理由
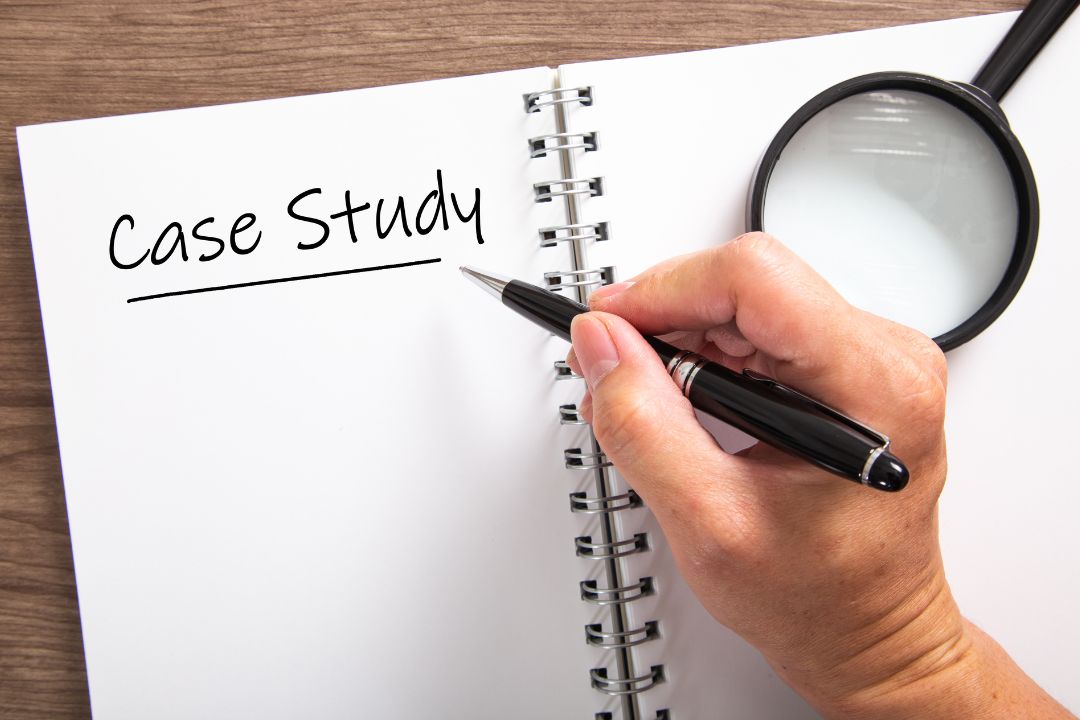
土地を売却する際に、測量を行った方が良い代表的なケースは、以下の5つの状況です。
- 境界が不明確な土地の売買
- 相続した土地の分割
- 隣地との境界トラブル防止
- 高額取引
- 登記簿の面積と異なる
それぞれの概要を解説します。
1.境界が不明確な土地の売買
隣地と土地の境界が不明確な場合、そのまま売却すると買主との間でトラブルが発生する可能性があります。
たとえば、公簿上の面積よりも実際の土地面積が狭かった場合、「騙された!」と買主からクレームを受けることがあります。このケースでは、買主が不安を感じ、契約が進まないこともあります。
また、契約後に発覚してしまうと、買主から損害賠償を求められたり、契約解除を請求されたりするリスクもあるため、売却前に測量を行い、境界を明確にしておくことが重要です。
確定測量を実施し、隣地所有者と合意を取ることで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
2.相続した土地の分割
相続した土地を複数の相続人で分割する場合、測量が必要になることが多いです。
これは、土地の正確な面積を把握しないまま分割すると、不公平な分配になったり、登記手続きがスムーズに進まなかったりする可能性があるためです。
また、相続人同士で境界をめぐるトラブルが発生することもあります。特に、長年手をつけていなかった土地や、元の所有者が測量を行っていなかった場合は、境界が不明確になっていることが多いです。
そのため、分割前に測量を行い、明確な境界を確定させることで、相続人同士のトラブルを防ぎ、スムーズに分割・登記を進めることができます。
3.隣地との境界トラブル防止
隣地所有者との境界線が曖昧なまま土地を売却すると、境界をめぐるトラブルが発生する可能性があります。
これは、「購入後に隣地所有者から境界線の位置が違うと主張された」「境界のずれを指摘され、再測量を求められた」といったケースです。隣地所有者とのトラブルで多いのは、塀やフェンスの所有権争いです。特に、塀やフェンスが隣地に越境している場合や、境界線上に設置されている場合には、どちらが所有しているのかで揉めることが少なくありません。
このようなトラブルを防ぐためには、売却前に測量を実施し、隣地所有者と境界の確認を行うことが大切です。確定測量を行い、隣地所有者と立ち会いのもと境界を確定させることで、売却後の紛争リスクを軽減できます。
境界トラブルは解決に時間がかかることが多いため、事前の対策が重要です。
4.高額取引
売却する土地が高額になる場合、取引の信頼性を高めるために測量を行うことが大切です。
高額な土地取引では、買主も慎重になるため、正確な面積や境界線が不明確な場合、購入を見送られることもあります。
また、金融機関の融資を利用する場合、測量図の提出を求められることが多いため、測量が必要になることがあります。
売却時のトラブルを防いでスムーズに取引するには、確定測量を行い、隣地所有者との合意を得た測量図を用意するのが有効です。
高額取引では買主の不安を解消するためにも、測量を行うことが推奨されます。
5.登記簿の面積と異なる
登記簿に記載された面積と実際の面積が異なる場合、売却時にトラブルの原因となることがあります。登記簿の面積は、古い測量データに基づいていることが多く、実際の土地面積と誤差が生じているケースも珍しくありません。
もし売買契約後に買主が実測を行い、面積の違いが発覚すると、「面積が不足している」として価格交渉や契約解除を求められることがあります。逆に、実際の面積が登記簿より大きい場合は、適正な価格での売却ができない可能性もあります。
代々受け継いでいる土地や田舎の土地などは、特に注意が必要です。その理由は、これらの土地は古い測量方法や簡易な測量で登記されているケースが多く、実際の面積や境界が不明確である可能性が高いためです。
そのため、売却前に測量を行い、正確な面積を把握することで、スムーズな取引が可能です。
3種類の測量図のちがい
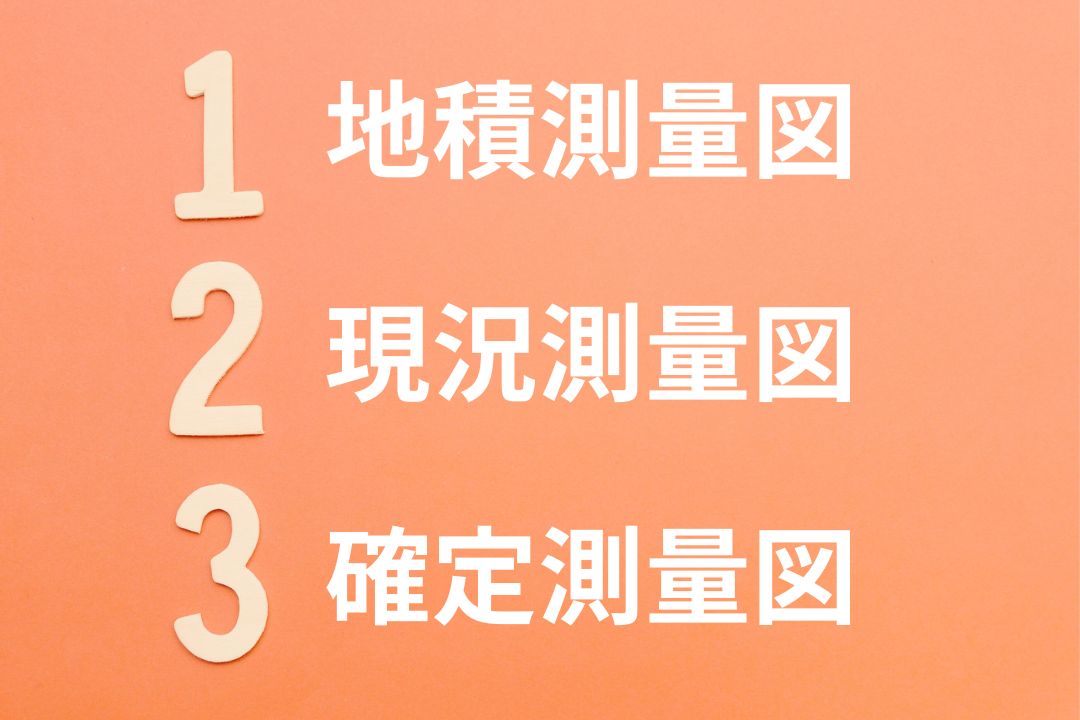
「測量図」と一言で言っても、実は3種類に分けられます。
それぞれの概要を解説します。
| 測量図の種類 | 測量士が作成できるか | 土地家屋調査士が作成できるか |
| 地積測量図 | × | 〇 |
| 現況測量図 | 〇 | 〇 |
| 確定測量図 | × | 〇 |
1.地積測量図
地積測量図は、土地の面積や境界線を正確に測定した図面です。土地の購入や売却、登記の際に必要となることが多く、法的効力を持つ場合があります。
この測量図は、土地の正確な面積や形状を示し、境界線が明確に記載されています。
地積測量図を基に、土地の評価額を算出することができ、法的な手続きにおいて重要な役割を果たします。
2.現況測量図
現況測量図は、名前のとおり土地の「現在の状態」を示す図面です。土地に建物や施設が建っている場合、その位置や状態が描かれています。
境界線や土地の形状も記載されますが、地積測量図ほどの精度はなく、測量の目的が異なります。たとえば、建築計画や道路計画など、土地の現状に基づく情報を提供するために使用されます。
そのため、正確な境界確定を目的とする場合には適していない点に注意が必要です。
3.確定測量図
確定測量図は、土地と土地の境界を確定させるために作成される測量図です。そのため、トラブルを避けるために非常に重要です。
特に土地の境界線で争いが生じた際には、確定測量図が法的に効力を持つ証拠となり、争いの解決に役立ちます。
そのため、売却前には確定測量図を取得しておくことが望ましいです。
測量にかかる期間・費用相場

続いて、測量にかかる期間や、費用相場を解説します。実際に測量を依頼する際の参考にしてみてください。
所要期間
測量にかかる期間は、測量の種類や土地の広さ、地域によって異なります。簡単な現況測量は、数日から1週間程度で完了するのが一般的です。
しかし、地積測量や確定測量などの詳細な測量は、土地の広さや境界の確認作業によって1週間から1ヶ月以上かかる場合もあります。
特に複雑な土地や隣接地との境界確認が必要な場合、期間が延びることがあります。また、登記手続きや役所の承認を待つ時間も含まれるため、余裕を持って計画を立てることが大切です。
費用目安
測量費用は、測量の種類や土地の面積、そして依頼する専門家によって大きく異なります。
たとえば、現況測量は比較的低コストで、数万円程度から始まることが多いです。
一方で、地積測量や確定測量は、土地の面積が広い場合や境界線の確認が難しい場合には、高額になるケースも少なくありません。
特に、売却時に必要となる「境界確定測量」は、土地家屋調査士の独占業務であり、法的な効力を持つ測量結果を作成できるのは土地家屋調査士だけです。
境界確定測量では、隣地所有者が立ち合いのもと署名押印し、境界確定書作成を行います。そのため、その分費用が30~80万円程度と高くなる傾向があります。
また、土地の場所による料金差があるため、費用相場はエリアによって異なるようです。
測量費用が高額になるケース

前章で解説した費用相場の例外として、下記の状況では測量費用が高額になることが想定されます。
- 隣接地とトラブルがある
- 隣接地の所有者が多い
- 土地の形状が複雑
費用が高額になりやすい理由や注意点を解説します。
隣接地とトラブルがある
隣接地との境界線にトラブルがある場合、測量費用が高額になることがあります。
たとえば、過去に境界線が変更されている場合、測量士は詳細な調査を行う必要があり、その分時間と労力がかかります。また、隣接地の所有者と合意形成を図るために、交渉や調整が必要となり、測量作業が長引くケースもあるでしょう。
時間と労力がかかり、隣接地の所有者との交渉も必要な分、一般的な測量よりも高額になることは覚悟しておいてください。
隣接地の所有者が多い
隣接地の所有者が複数人いる場合、それぞれとの協議や確認作業が必要となり、測量費用が高額になることがあります。特に、境界線が複数の土地にまたがっている場合、各所有者の同意を得るために時間が必要です。
このような場合、測量士は複数回の現地調査や確認を行い、境界の確定に時間を要するため、追加料金が発生することがあります。事前に所有者との調整を行うことが、費用を抑えるための鍵です。
土地の形状が複雑
土地の形状が複雑な場合、測量作業が難航し、費用が高くなることがあります。
例えば、土地が不整形で曲線が多い場合や、道路や建物が接している場合など、境界を確定するには精密な測量機器の使用が必須です。
このような場合、時間がかかり、専門的な知識と技術を要するため、費用が上がる傾向があります。土地の形状が複雑であるほど、正確な測量が求められるため、費用が高額になるでしょう。
測量の依頼方法と流れ

測量調査を依頼する際の具体的な流れは、下記のとおりです。
- 土地家屋調査士に依頼する
- 必要書類をまとめる
- 隣接地の所有者へ挨拶に行く
- 土地の事前調査をする
- 隣地所有者の立会いのもと測量する
- 境界標を設置する
- 測量図を作成・登記を行う
それぞれの工程でのポイントを解説します。
1.土地家屋調査士に依頼する
土地の測量を依頼するには、まず土地家屋調査士に相談しましょう。
依頼時には、土地の場所や大きさ、目的に応じて費用や期間の見積もりを受け取ります。測量に関する詳細なアドバイスや手続きの進行もサポートしてくれるため、スムーズに進めることができます。
口コミや過去の実績を確認し、信頼できる調査士を選ぶことが、問題なく測量を終わらせるための鍵です。
2.必要書類をまとめる
測量を依頼する際には、いくつかの必要書類を準備する必要があります。
具体的には、登記簿謄本や地積測量図、過去の測量図、土地の位置を示す地図などが求められるのが一般的です。
これらの書類は、土地の所有権や境界が確定しているかを確認するために必要です。また、境界に関する情報や隣接地の情報も必要となる場合があり、過去の測量記録なども重要です。
事前にこれらの書類を整え、測量士に渡すことで、手続きがスムーズに進行します。
3.隣接地の所有者へ挨拶に行く
測量を行う前に、隣接地の所有者に挨拶をすることが推奨されます。
境界線を確認する際のトラブルを避けるには、隣地所有者と円滑にコミュニケーションをとることが大切です。挨拶を通じて、測量の目的や日程を伝え、協力をお願いすることが円滑な作業を進める鍵となります。
また、挨拶の際に隣地所有者と境界に関する情報を共有することができれば、測量時のトラブルの予防にもつながります。
4.土地の事前調査をする
測量を始める前に、土地の事前調査が行われます。
この調査では、土地の形状や境界線の確認、過去の測量データの収集が行われます。また、隣接地との境界に関する情報や、過去に境界が変更された記録がないかなどを確認します。
事前調査によって、測量に必要な情報を把握でき、測量作業をスムーズに進める準備が整います。この調査が不十分だと、後々トラブルや誤差が生じることがあるため、しっかりと行うことが大切です。
5.隣地所有者の立会いのもと測量する
測量作業は、通常、隣接地の所有者の立会いのもとで行います。
隣接地の所有者に確認を取りながらの作業となるため、境界線に関する誤解やトラブルを防ぐことが可能です。隣地所有者が立ち会うことで、双方の合意のもとで境界を確認でき、後の紛争を避けることができます。
また、立会いによって隣地所有者が測量結果に納得しやすくなり、トラブルを未然に防ぐことができます。
6.境界標を設置する
測量が完了すると、境界標が設置されます。
境界標は、土地の境界を明確に示すための目印となります。この標識は、土地の境界が確定した証として、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。
境界標は通常、測量士が責任を持って設置します。設置場所や方法には法律的な基準があるため、専門知識を持つ測量士が正確に行います。これにより、将来の境界争いを防ぐことが可能です。
7.測量図を作成・登記を行う
測量が終わったら、測量図が作成されます。
測量図は、土地の正確な面積や境界線を示す重要な書類です。この図面を基に、土地の境界が公的に確定し、登記手続きが行われます。
登記により、土地の境界が法的に確定し、所有権が公的に認められます。登記簿に記載された測量図は、土地取引や相続、裁判などで証拠として利用されるため、非常に重要な役割を果たします。
隣地の所有者に測量の立ち合いを拒否されたらどうする?

土地の売却や境界確定の際、隣地所有者に測量の立ち合いを拒否されるケースがあります。
このような場合、境界が不明確なままでは売却手続きが進まず、トラブルが発生するリスクも高まります。
そこで、法的な手続きや制度を利用して境界を明確にする方法が必要になります。代表的な解決策としては、「筆界特定制度」を利用する方法と、「境界確定訴訟」を行う方法があります。
筆界特定制度を利用する
筆界特定制度は、法務局が土地の境界(筆界)を特定するための制度です。
土地家屋調査士や弁護士が代理申請し、登記官が境界を特定して筆界特定書を発行します。
裁判を起こさずに済むため費用や時間が少なく済む一方で、筆界(登記上の境界)と実際の使用境界(所有権界)が異なる場合があるため、解決後もトラブルが続くケースがあります。
境界確定訴訟を行う
境界確定訴訟は、裁判所に土地の境界を確定させるための訴訟を提起する方法です。
裁判所の判決で法的効力を持つ境界が確定されるため、隣地所有者も従わざるを得ません。
ただし、訴訟には時間と費用がかかり、隣地所有者との関係が悪化するリスクもあるため、慎重な判断が必要です。
隣地所有者が立ち合いを拒否した場合でも、法的手続きで境界を明確にする方法があるため、状況に応じて適切な対応を検討しましょう。
まとめ

土地の測量は、売主の義務ではありませんが、特定のケースでは非常に重要な役割を担います。
境界が不明確な土地の売買・相続した土地の分割の際や、隣地とのトラブル防止したいときなどは、特に測量が必要不可欠です。
測量には地積測量図、現況測量図、確定測量図の3種類があり、それぞれ異なる目的で使用されます。また、隣接地とのトラブルや土地の形状が複雑な場合、費用が高額になることがあります。
測量依頼の流れを理解したうえで調整を行い、隣地所有者と協力しながら、スムーズな測量を目指しましょう。





コメント