
「使っていない家を貸せば、家賃収入が得られるかも」という想いから、家を賃貸に出そうと思っているものの、一方で、「何から始めたらいいの?」「トラブルが起きたらどうしよう」といった不安もたくさん抱えている方は多いのではないでしょうか。
とくに、今まで家族と住んできた大切な家を貸し出したり、相続した親の実家を貸し出したりする場合には、「本当に貸し出して大丈夫なのだろうか」「後悔することはないかな」と慎重になってしまうものですよね。
この記事では、家を初めて貸す方が知っておくべき7つの注意点と、後悔や失敗、面倒を避けるための安心のコツを、わかりやすくご紹介します。
一つひとつ対策しておくことで、余計な出費やトラブルを未然に防ぎ、安心して家を貸すことができます。読み終えたころには、安心して貸すために事前にすべきことが明確にわかるようになっているはずです。
ぜひ最後までお読みください。
目次
- 1. 家を貸すメリットは大きいが注意点もあるので事前準備と対策がとても重要
- 2. 家を貸す注意点1:初期費用や維持費用もかかる
- 2-1. 家を貸すときにかかる初期費用
- 2-2. 家を貸すときにかかる維持費用
- 2-3. 家を貸すときにかかる税金
- 3. 家を貸す注意点2:入居者対応・物件管理など大家としてすべきことが多い
- 4. 家を貸す注意点3:あいまいな契約だとトラブルに発展する可能性がある
- 5. 家を貸す注意点4:設備の修理費用は原則として自分(貸主)が負担となる
- 6. 家を貸す注意点5:かならず入居者が見つかるとは限らない
- 7. 家を貸す注意点6:家賃滞納リスクがある
- 8. 家を貸す注意点7:年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要
- 9.【注意点を総括】面倒やトラブルを避けて家を貸すための4つの掟
- 9-1. 費用・税金を加味して長期的なシミュレーションをしておくこと
- 9-2. 信頼できる仲介会社・管理委託会社を選ぶこと
- 9-3.「将来的にどうしたいか」まで考えたうえで判断すること
- 9-4. 不安や面倒を感じたら不動産会社に相談してみること
- まとめ
1. 家を貸すメリットは大きいが注意点もあるので事前準備と対策がとても重要

家を貸すことは、大切な資産を有効に活用できる素晴らしい方法です。
しかし、事前に何も準備をせずに「ただ家賃収入が得られそうだから貸す」という安易な気持ちで貸してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれたり、損をしてしまったりする可能性が高くなってしまいます。
事前に起こりそうなトラブルや費用・税金の金額を知っておくことで、回避する方法や予防策を講じておくことができます。
| 家を貸す7つの注意点 ・家を貸す注意点1:初期費用や維持費用もかかる ・家を貸す注意点2:入居者対応・物件管理など大家としてすべきことが多い ・家を貸す注意点3:あいまいな契約だとトラブルに発展する可能性がある ・家を貸す注意点4:設備の修理費用は原則として自分(貸主)負担となる ・家を貸す注意点5:かならず入居者が見つかるとは限らない ・家を貸す注意点6:家賃滞納リスクがある ・家を貸す注意点7:年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要 |
次の章から、「家を貸すときに気をつけたい注意点」と「それぞれの回避方法」について丁寧にご紹介していきます。安心して一歩を踏み出せるよう、ぜひ参考にしてください。
2. 家を貸す注意点1:初期費用や維持費用もかかる

家を貸すことで家賃収入を得られるのは魅力的ですが、家を貸すことで発生する費用や税金も思った以上にかかるという点には注意しておく必要があります。
物件を貸す際には、初期費用(最初にかかるお金)と維持費用(貸している間にかかるお金)、そして見落としにくい税金もかかります。
2-1. 家を貸すときにかかる初期費用
家を貸し出す前には、物件を魅力的に整えるための準備や、手続きを進めるための費用がかかります。
| 初期費用の相場 ・築浅で条件の良い戸建ての場合:クリーニングと仲介手数料で10万〜30万円程度が一般的 ・築20年以上などで修繕が必要な場合:リフォーム費用がかさんで100万円以上かかることもある |
【初期費用(入居前・入居時)】
| 費用の種類 | 内容 | タイミング | 金額の目安(参考) |
| 修繕・リフォーム費用 | 外壁や屋根の補修、クロス張替え、水回りの交換など。 | 貸し出す前/入退去時 | 数万円~100万円以上 |
| ハウスクリーニング | 入居前の清掃やエアコン洗浄など。 | 入居前/退去後 | 2~5万円程度 |
| 仲介手数料 | 不動産会社に入居者を紹介してもらった際の手数料。 | 入居時 | 家賃1カ月分が一般的 |
家を貸し出す前に不動産会社に相談してリフォームや修繕が必要かどうか相談したり、リフォーム会社に見積もりを取ったりして初期費用を確定してから、正式に賃貸に出す準備を始めると安心です。
2-2. 家を貸すときにかかる維持費用
入居者が見つかったあとにも、オーナーとして毎月・毎年発生する費用があります。継続的に発生するコストなので、長期的なシミュレーションが重要です。
| 維持費用の相場 ・賃料や管理委託の内容、修繕の必要性によって異なるため一概にはいえない ・管理費は、家賃の5~10%程度が一般的 |
【毎月の維持費として定期的にかかる費用】
| 費用の種類 | 内容 | タイミング | 金額の目安(参考) |
| 管理委託費用 | 管理会社に家賃回収やトラブル対応を委託する場合の費用。 | 毎月 | 家賃の5~10%程度 |
| 火災保険料 | 建物にかける火災保険 | 年1回(または数年ごと) | 2万~5万円程度/年程度 |
| 設備修繕費 | 給湯器・エアコン・水回りなどが故障した場合の修理費 | 故障や不具合が発生したとき | 数万円〜20万円以上になることも |
設備修繕費は、物件が古いほど定期的にかかる可能性があります。エアコンや給湯器などの設備の修繕負担はどちらが負うのかなども、事前に決めておくと安心です。
2-3. 家を貸すときにかかる税金
家を貸して収入が発生すると、さまざまな税金がかかることになります。特に、思わぬ税負担で利益が減ってしまわないように、事前に税金の種類や内容を把握しておくことが大切です。
| 税金の相場 ・固定資産税は年間10万円程度が相場 ・所得税は家賃収入に応じて発生する |
【家を貸すときにかかる税金】
| 費用の種類 | 内容 | タイミング | 金額の目安(参考) |
| 固定資産税・都市計画税 | 所有している土地・建物にかかる税金 | 年1回(市区町村から通知) | 年間10万〜20万円程度(地域・評価額による) |
| 所得税・住民税 | 家賃収入に対する課税(確定申告が必要) | 年1回(確定申告時) | 所得によって異なる |
家賃収入を得るということは、事業や副業と同じように課税対象になるということです。所得税や住民税に加え、不動産を持っていること自体に対する税金(固定資産税)も発生します。これらはきちんと確定申告を行う必要があります。
本章で解説したように、「家を貸す=家賃収入を得られる」というイメージだけではなく、意外とさまざまな費用や税金がかかります。「意外と手元に残らない」と感じることもありますので、事前に長期的なシミュレーションをしておくことが大切です。
シミュレーションの仕方などは、のちほど「9.【注意点を総括】面倒やトラブルを避けて家を貸すための4つの掟」のなかで後述します。
3. 家を貸す注意点2:入居者対応・物件管理など大家としてすべきことが多い

「家を貸す相手が見つかって賃貸契約が終われば安心」というイメージの方もいるかも知れませんが、そうではない点に注意が必要です。貸し出しているあいだ、大家(オーナー)という役割はずっと続きます。
家賃の回収や住人からの問い合わせ対応のほか、設備の不具合への対応、近隣となにかトラブルがあったときには、実務的な対応が必要になるケースがあります。
【オーナーとしてすべきこと】
| オーナーの業務 | 内容 |
| 家賃の回収 | ・毎月指定した日に、入居者から事前に決めた家賃の金額が入金されているか確認する ・支払い遅延や不備にすぐ気づけるよう、入金チェックを習慣化する必要がある |
| 家賃滞納時の督促 | ・入居者が期日までに家賃を支払わない場合に、連絡して支払いをお願いする ・直接連絡するのは精神的にもハードルが高いため、苦手な方は管理会社に管理を委託する選択肢も考える |
| 入居者からの問い合わせ対応 | ・設備の不具合や生活トラブル、漏水対応など、入居者からの連絡に対応する ・トラブル内容の把握が難しかったり、夜間や休日に急な連絡が来ると大きな負担になったりすることも。対応窓口を管理会社に任せるとストレス軽減につながる |
| 契約更新管理 | ・契約満了が近づいたタイミングで、入居者に継続意思を確認し、必要な手続きを行う ・契約満了に気づかず、無断更新状態にならないよう早めの連絡と書類準備を心がける必要がある |
| トラブル対応 | ・近隣住民との騒音・ゴミ出しなど、生活上のトラブル解決を解決する ・感情的な対応をしてしまうと逆に悪化することもあるため、第三者的立場で冷静に、記録(メモやメール保存)を残して対応することが大切 |
| 修繕対応 | ・オーナー負担で直すべきエアコンや水まわりなどのトラブルが合った場合に、業者を手配して修理対応をおこなう ・慣れていないと「どの業者に連絡すればよいか」わからず、対応が遅れがちになるため、事前に信頼できる修理業者をリスト化しておくと安心 |
たとえば「トイレの水が流れない」「隣人の音がうるさい」など、入居者からの連絡があれば、その都度対応を求められます。家を貸すのが初めてな方はとくに、管理を自分一人でこなすのは想像以上に大変です。
このような業務が負担になる場合や、時間を取れなくて大変な場合には、信頼できる管理委託会社に、貸している家の管理業務を任せるのがおすすめです。
管理会社の対応力によって満足度は大きく変わりますので、実績や対応内容を比較して慎重に選ぶことが成功のカギになります。管理会社の選び方は、のちほど「9.【注意点を総括】面倒やトラブルを避けて家を貸すための4つの掟」のなかで後述します。
4. 家を貸す注意点3:あいまいな契約だとトラブルに発展する可能性がある

契約内容を曖昧にしたまま家を貸し出してしまうと、後々のトラブルに発展する可能性が高くなります。
空いている家を有効活用するために賃貸に出したのに、「退去してくれない」「家を汚されてしまった」などのトラブルがあると本末転倒です。
トラブルに発展させないよう契約書をしっかり作り込んでおくことが、入居者とのトラブルを防ぐためにとても重要となります。
以下に、絶対に避けたいトラブル事例と契約書での対応策(記載ポイント)をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
【契約内容の甘さでトラブルに発展する例と対策】
| トラブル事例 | 契約書での対応策・記載ポイント |
| 契約書を作成していなかった | 親しい仲であっても、かならず書面で契約書を作成することが重要 家賃の金額や期間、禁止事項、解約条件など全て明文化したうえで、専門家の意見も聞いておくと安心 |
| 退去してくれない(明け渡し拒否) | 「定期借家契約」であることを明記し、「期間満了で退去が必要」と記載する 通知期限・手続きも書面に明確に記載する |
| 家賃滞納 | 支払期日・遅延損害金・契約解除条件・保証会社の利用などを明記しておく |
| 無断で他人を同居させる(又貸し) | 契約者以外の居住禁止、無断同居の違反時対応を記載。契約解除事由とする |
| 騒音など近隣とのトラブル | 騒音・迷惑行為の禁止条項を詳しく記載しておき、違反時の注意・契約解除の流れも明記する |
| ペットを勝手に飼われた | ペット飼育の可否、違反時の罰則・契約解除条件を明記する |
| 室内の無断改装・壁紙の貼り替え | 改装・DIYの事前許可や違反時の原状回復義務を細かく明記しておく |
| 退去時の原状回復トラブル | 原状回復の範囲、経年劣化との違い、清掃費用請求を明記しておく |
| ゴミの分別・収集ルール違反 | ゴミ出しマナーを守らないと近隣とトラブルになりやすいため、自治体のルールに従う義務を契約書で明記しておく |
| 設備の破損・修繕費用トラブル(例:エアコン) | 故意に壊されたり、設備の責任範囲が不明確なことで揉めることがある 設備ごとの責任範囲を明記し、故意・過失による破損は借主負担、経年劣化は貸主負担と記載する |
トラブルを事前に回避するためには、細かいことでもしっかりと契約書で明文化しておくことが大切です。はっきり明文化していないと「とりあえずオーナーが払うしかない」となることが少なくなく、損してしまう可能性があります。
取り決めがあるだけで、万一のトラブル時にもスムーズに対応でき、余計なストレスや費用負担を回避することができます。
賃貸契約書は専門家の力を借りて作成し、トラブルを防ぐ内容にしておくことが安心です。とくに、「退去してくれない」というトラブルを防ぐためには、期限を決めて短期で貸し出すような契約に強い不動産会社に相談すると、経験に基づいた契約書を作成してもらえるためおすすめです。
5. 家を貸す注意点4:設備の修理費用は原則として自分(貸主)が負担となる

貸している家の設備が壊れた場合には、原則として、修繕費用は大家側(貸している側)の負担になります。
たとえば、もともと備え付けられているエアコンが故障したり、排水管が詰まってしまった場合には、入居者に故意や過失がない限り、基本的には大家(オーナー)の負担で修理し、使用できる状態に戻す必要があります。
この点をしっかりと意識したうえで、「どこまでが大家の負担で修理すべき設備なのか」や「入居者の責任となる例外的なケース」をあらかじめ明確に決めておかないと、結果的にあらゆる修繕を大家が負担しなければならない状況になってしまう可能性があります。そのため、契約時にしっかりと取り決めておくことが大切です。
そもそも設備の故障がなぜ大家側の負担になるかというと、賃貸物件の貸主には、入居者が安全かつ快適に生活できるよう、物件の適切な維持管理と修繕をする義務があるからです。この義務については民法606条で明確に定められています。
| (賃貸人による修繕等) 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 |
入居者が故意に壊した場合や、使い方が悪くて壊れた場合、調子が悪いのを放置して悪化させてしまった場合などに責任の所在を明らかにするためにも、こうした内容をしっかりと契約書に盛り込んでおくと安心です。
また、どこまでが設備に含まれるかを契約書にしっかりと記載しておくことも重要です。設備ごとの責任範囲を契約書にしっかり記載しておき、入居者にも明確に説明しておくことで、トラブルを未然に防げます。
築年数が経過している家の場合は、どの設備も古いため、自然と故障リスクが高まります。入居者の求めに応じて修繕する義務があることを考えると、家を貸すよりも売却を検討したほうが良いケースもあります。このあたりをしっかりと事前に検討しておくとともに、修繕費用を収支計画に含めておくことも重要です。
6. 家を貸す注意点5:かならず入居者が見つかるとは限らない

家を貸して入居者が見つかれば家賃収入が当然入ってきますが、募集を出せばかならず入居者が見つかるとは限らない点にも注意するべきです。
家を貸す前には「このくらいの家賃で貸すと年間収入が◯万円で…」と楽観的にシミュレーションしがちですが、実際には、自分が希望する家賃で入居者が決まらないことがあります。そのため、空室リスクを見越した計画を建てておくことが重要です。
また、物件によってはかなり家賃を下げなければ入居者が決まらない場合や、そもそも戸建て賃貸ニーズがない場所で借り手がいないという場合もあります。この場合は、家を貸すために費用をかけて準備しても、赤字になってしまう可能性があります。
たとえば、家賃10万円の物件で入居までに3カ月かかってしまうと、得られると想定していた30万円は入ってこず、管理委託費用だけがかかるということになります。空き家の期間が長引けば、ハウスクリーニング代や固定資産税などを支払った分がそのまま赤字になる可能性もあります。
| 「入居者が見つかるとは限らない」という注意点の対策 ・貸し出す前に不動産会社に相談して、入居需要の有無や家賃相場を確認する ・入居率の高い仲介会社に依頼する ・空室保証のある管理委託契約を検討する |
入居者が見つかる可能性が低そうな場合には、売却などほかの選択肢も検討したほうが良いケースもあります。
たとえば、駅から遠い場所や築年数が古い家は、なかなか決まらないケースもあります。事前に不動産会社に「この家は貸せそうか」「マイナスポイントはあるか」など相談しておくのが安心です。また、入居率の高い仲介会社を選ぶこともポイントです。
さらに、空室になっても一定の家賃が支払われる「家賃保証付き」の契約も検討すると、より安心して貸し出すことができます。
7. 家を貸す注意点6:家賃滞納リスクがある

「借り手が見つかればひと安心」である一方で、思わぬトラブルに見舞われる可能性がゼロではない点に注意が必要です。家を貸すうえで、もっとも困るトラブルのひとつが「家賃滞納」です。
家賃をスムーズに回収できないと、精神的に大きなストレスを受けますし、すぐに追い出すこともできず金銭的な損失が発生する可能性もゼロではありません。借主が居座ってしまった場合、すぐに強制的に退去させることは法律上できません。裁判や強制執行といった時間と費用のかかる手続きが必要になるケースもあります。
管理会社に家の管理を委託をしていない場合には、オーナーが家賃滞納に気づいた時点で、自発的に動かざるを得ません。
| ・自分から入居者(借主)に連絡を取って、家賃の支払いを催促する ・それでも滞納が続けば、法的な手続き(内容証明・契約解除・明け渡し請求など)を自分で進める必要がある |
対応が遅れると滞納が長引き、損害が広がるリスクがあるため、スピーディーな行動が求められます。しかしながら、家賃の催促を直接おこなうのも法的手続きを進めるのも、個人ではとても負担が大きいものです。
家賃滞納リスクを減らすための対策をまとめておくので、事前に対策を行っておくことが大切です。
【家賃滞納リスクを減らすための主な対策】
| 対策方法 | 内容 | メリット | 注意点・限界 |
| 家賃保証会社を利用する | 入居者に代わって保証会社が家賃を立て替えて支払う制度 | 滞納時も家賃がオーナーに支払われるため安心 | 信用審査があるため、入居希望者が落ちる場合も |
| 管理会社と「家賃保証付き管理契約」を結ぶ | 管理会社が家賃保証も込みで契約を請け負う | 対応・督促・立て替えをすべて任せられる | 委託費用は通常よりやや高めになる場合も |
| 連帯保証人を立ててもらう | 滞納時に連絡や支払い請求ができる体制を整える | 万一のときの法的な請求先として活用できる | 連帯保証人の支払い能力にもよる |
| 入居審査を厳しめにする | 安定収入や職業、保証人の有無などをしっかり確認 | 滞納のリスクを未然に防げる | 慎重になりすぎると入居が決まりにくい可能性あり |
| 契約書に滞納時の対応を明記する | 支払い期限、遅延損害金、連絡手段などを細かく記載 | 明文化されていれば対応しやすい | 入居前にしっかり説明し、納得してもらう必要あり |
家賃滞納リスクをできるだけ減らすためには、事前の対策がとても重要です。管理会社もうまく活用しながら、事前にできることを考えておきましょう。
8. 家を貸す注意点7:年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要
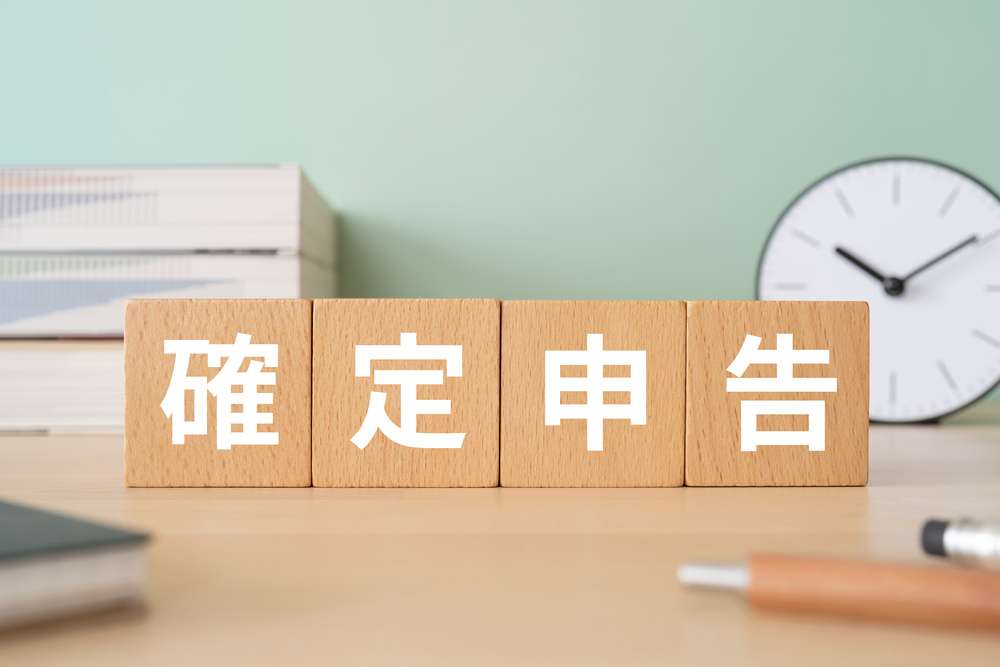
会社員などの給与所得者が家を貸すことにより利益を出した場合、家を貸したことで得られる年間所得(家賃収入−かかった費用など)が20万円を超えると確定申告が必要になります。確定申告書を作成して税務署に提出して、所得税を支払う必要があります。
※給与所得以外の収入が家賃収入以外にもある場合は、それらを合算した年間所得が20万円を超える場合に確定申告・納税が必要です。
| 確定申告の流れ ・STEP1:確定申告の方式を確認・決定する(白色・青色) ・STEP2:確定申告の提出方法を決める ・STEP3:必要書類や添付書類を集める ・STEP4:確定申告書を作成する ・STEP5:毎年3月15日までに確定申告を終える ・STEP6:【還付なしの場合】計算された納税額を期日までに支払う ・STEP7:【還付ありの場合】申告書提出後に銀行口座に還付金が振り込まれる |
確定申告は慣れてしまえばそれほど難しくないものですが、初めて家を貸す人にとっては時間も手間もかかるものです。また、「どこまでを経費として計上できるのだろうか」「減価償却の計算はどうすればいいか」「青色申告と白色申告の違いがわからない」「帳簿の付け方やe-Tax(電子申告)の使い方がわからない」など、迷うポイントがたくさんあります。
直前になって慌てないよう、確定申告に向けて必要な情報をリサーチしておいたり、申告に必要な書類を少しずつ準備しておいたり、早めにe-Taxの環境を整えておいたりして、スムーズに確定申告を終えられるよう準備を整えておくのがおすすめです。
どうしても不安な場合は税理士や管理会社に確定申告の代行依頼することもできるため、念のため申告代行費用を収支シミュレーションに入れておくのも良いでしょう。確定申告代行の費用は、おおむね0.5万円〜5万円程度が相場です。
ルーム・スタイルでも、別途費用は発生しますが、管理委託をお任せいただいているオーナー様の確定申告について、当社が納税管理人となり代理で手続きを行うことが可能です。家の賃貸管理委託と合わせて、ぜひご相談ください。
9.【注意点を総括】面倒やトラブルを避けて家を貸すための4つの掟

ここまで解説したように、家を第三者に貸して家賃収入を得ることにはメリットも大きい反面、注意して置かなければならないポイントもたくさん存在します。
注意点ごとの対策方法はそれぞれの章でお話しましたが、これらを統括すると、以下の4つの掟を守ることが、面倒事やトラブルを避けて家を貸すために重要となります。
| 面倒やトラブルを避けて家を貸すための4つの掟 ・費用・税金を加味して長期的なシミュレーションをしておくこと ・信頼できる仲介会社・管理委託会社を選ぶこと ・「将来的にどうしたいか」まで考えたうえで判断すること ・不安や面倒を感じたら不動産会社に相談してみること |
これから家を貸し出す方は、本章で説明する内容を守ることをおすすめします。
9-1. 費用・税金を加味して長期的なシミュレーションをしておくこと
家を貸す前には、得られる家賃収入だけでなく、かならず費用や税金も加味した長期的な収支シミュレーションをしておきましょう。
前述した通り、家を貸すには、ハウスクリーニング代や毎月管理会社に支払う管理委託手数料、固定資産税など、さまざまな支出が発生します。これらを把握せずに始めてしまうと、「収入があると思っていたのに赤字だった」という結果になりかねません。
たとえば、家賃月15万円で家を貸し出す場合、年間の家賃収入は180万円です。しかしながら、初期費用が合計42.5万円、維持費用が年間合計43万円(管理費や火災保険料、固定資産税、修繕費用など)かかった場合には、180万円−42.5万円−43万円で、利益は94.5万円(月あたり約7.9万円)となります。
この例の場合、家賃は月15万円でも利益は月あたり約7.9万円と、費用が結構引かれるものだなと感じる方も多いかもしれません。このように年間ベースでシミュレーションをしておくことで、楽観的すぎず現実的な見通しを持っておくことができます。
家賃収入だけに注目せず、「手元にどれくらい残るのか?」を可視化してからスタートすることが大切です。
場合によっては、それほど手元に残らないのならば売却も再検討してみたほうが良いケースもあります。もちろん、「赤字になっても自宅の価値を維持するために人に住んでもらいたい」のようなケースもありますが、どの程度の赤字になるかを知っておくことが大切です。
9-2. 信頼できる仲介会社・管理委託会社を選ぶこと
今回注意点として紹介したトラブルやオーナーとしての負担を回避するためには、信頼できる仲介会社・管理委託会社を選ぶことが非常に重要となります。
なぜならば、信頼できる不動産仲介会社や管理会社を選ぶことで、契約トラブルや入居者とのトラブル、入居者がなかなか入らない状態などを大きく減らすことができるからです。
仲介会社・管理会社は入居者募集、家賃回収、トラブル対応など多岐にわたる業務を代行してくれるパートナーです。対応力や客付け力の差によって、入居率やオーナー満足度も大きく変わってきます。
たとえば、入居率90%以上を保っている会社であれば、空室期間も短く済みます。また、滞納や設備トラブルにも迅速に対応してくれる管理会社であれば、オーナーが介入する必要がほとんどありません。
「どこに任せるか」でトラブルや面倒を回避できるかどうかが決まるので、実績や評判をよく確認して選びましょう。
9-3.「将来的にどうしたいか」まで考えたうえで判断すること
貸す前に「この家を将来的にどうしたいのか?」をしっかり考えておくことが重要です。
前述したように、いったん賃貸物件を貸し出してしまうと、普通の借家契約では入居者(借り手)の立場が法的に強く守られているため、簡単に退去させることは難しくなります。退去を前提とするのであれば、通常の賃貸契約ではなく、定期借家契約を結ばなければなりません。
「将来子どもが住むかもしれない」「いずれは売却したい」などの希望がある場合は、それに合った契約形態にしておかないと後で困ることになります。
たとえば、将来自分で住む予定があるなら「定期借家契約」で貸すことで、契約満了時に退去してもらうことができます。逆に長期で貸し続けたい場合は「普通借家契約」の方が適しています。
将来を見据えて「貸すかどうか」「どう貸すか」を決めることが、後悔を防ぐポイントです。
9-4. 不安や面倒を感じたら不動産会社に相談してみること
今回紹介したように、家を貸すことはけっして簡単なことではないため、後悔したくないならば無理して自力ですべて対応しようとせず、不動産会社に相談してみることをおすすめします。
すでに家賃経営に慣れている方であれば、事前の収支シミュレーションや諸々の判断、管理まで自分で行えるかもしれません。しかしながら、「初めて家を貸す」という方が手探りで誰の力も借りずに進めてしまうと、判断を誤ってしまう可能性があります。
たとえば、周辺の家賃相場から「この家も15万円で貸せるだろう」と判断して、リフォームにもお金をかけて準備を進めたとします。いざ賃貸に出そうとしたところ、間取りが特殊でなかなか15万円で借りてくれる人が見つからない、というケースはありえます。
もしも先に不動産会社に賃料査定を依頼していたら、「この間取りだと借りたい人が見つかりにくい」ということに気づけたかもしれません。
このように、不動産のプロの目線ではすぐに気づくことも、慣れていないオーナーでは気づきにくいということがあるかもしれません。
不動産会社に相談すれば、地域の相場だけでなく個別の家の状態・条件に応じて、「いくらで貸せそうか」判断できますし、契約の種類の相談や、貸すべきか売るべきかの判断についてもアドバイスが受けられます。
無理に一人で抱えこもうとせず、専門家の力を借りて安心して進めていくことが、後悔しないために重要です。
まとめ
本記事では「家を貸すときの注意点」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。
◆家を貸す注意点1:初期費用や維持費用もかかる
かかる費用を前もって知っておおき、事前に長期的なシミュレーションをしておくことが大切
◆家を貸す注意点2:入居者対応・物件管理など大家としてすべきことが多い
負担になる場合や時間を取れない場合には、信頼できる管理委託会社に管理業務を任せるのがおすすめ
◆家を貸す注意点3:あいまいな契約だとトラブルに発展する可能性がある
トラブルを事前に回避するためには、細かいことでもしっかりと契約書で明文化しておくことが大切
◆家を貸す注意点4:設備の修理費用は原則として自分(貸主)が負担となる
どこまでが設備に含まれるかを契約書にしっかりと記載しておくことも重要
◆家を貸す注意点5:かならず入居者が見つかるとは限らない
貸し出す前に不動産会社に相談しておくことや、家賃保証も検討するのがおすすめ
◆家を貸す注意点6:家賃滞納リスクがある
家賃保証会社を利用する、家賃保証月管理契約を結ぶなども検討しておく
◆家を貸す注意点7:年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要
どうしても不安な場合は税理士や管理会社に確定申告の代行依頼することもできる
◆【注意点を総括】面倒やトラブルを避けて家を貸すための4つの掟
・費用・税金を加味して長期的なシミュレーションをしておくこと
・信頼できる仲介会社・管理委託会社を選ぶこと
・「将来的にどうしたいか」まで考えたうえで判断すること
・不安や面倒を感じたら不動産会社に相談してみること
「家を貸したいけれど面倒ごとは避けたい」という方は、ぜひルーム・スタイルにご相談ください。





コメント