
「うちは賃貸物件だし、シロアリなんてそうそう来ないだろう」――そう思って油断していると、思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。
シロアリは、建物の構造や用途に関係なく侵入し、繁殖する生き物です。しかも発見が遅れやすく、対応が後手になると資産価値の下落や入居者トラブルに直結してしまいます。
本記事では、賃貸オーナーが押さえておくべきシロアリ対策を、原因・兆候・対処法・費用面からわかりやすく解説します。実際のトラブル例なども交えながら、予防の重要性について考えていきましょう。
「うちの物件も大丈夫かな…?」と不安な方は、物件管理のプロである弊社が、点検・対策までしっかりサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- シロアリは賃貸物件にも発生する?放置のリスクとは
- 賃貸でも発生する理由とは?
- 放置すれば「建物崩壊リスク」にも
- シロアリが好む環境と、発生しやすい物件の特徴
- シロアリが好む典型的な環境
- 知っておきたい「立地条件の罠」
- シロアリ被害のチェックポイントとオーナーの予防策
- シロアリ被害のチェックポイント
- オーナーの予防策
- 賃貸物件でシロアリ発生時の対応・駆除の流れ
- 正しい対応ステップ
- 「価格」だけで業者を選んではいけない理由
- シロアリ予防・駆除にかかる費用目安と考え方
- 予防工事(防蟻)の2種類の工法
- 予防工事の費用目安
- 駆除工事の費用目安
- 経費処理と資本的支出の考え方
- 賃貸ならではの注意点|入居者とのトラブルを防ぐには?
- 修繕義務は貸主にあるのか?
- 入居者に「シロアリ被害を防ぐ生活習慣」を伝えよう
- 防蟻工事の施工には入居者へ配慮しよう
- 予防が最大の対策!資産を守るためにできること
- 定期点検の習慣化
- 空室期間を活用した予防工事
- まとめ|「備え」が空室リスク・資産劣化を防ぐカギ
シロアリは賃貸物件にも発生する?放置のリスクとは

多くの人が「シロアリは、木造一戸建ての問題」と誤解しがちですが、それは大きな誤解です。実際には、賃貸マンションやアパート、さらには鉄骨造やRC造の物件でも被害が報告されています。
賃貸でも発生する理由とは?
木材・湿気・温度の3つの条件が揃うと、シロアリが発生しやすい「好環境」が整います。
物件の構造や用途ではなく、「床下の通気性が悪い」「湿気がこもっている」「築年数が経っている」といった条件が揃うと、たとえ鉄筋コンクリート造でも侵入される可能性があります。
たとえば、浴室や脱衣所の床下、キッチン下の収納、北側に位置する玄関土間周辺などは、湿気がたまりやすく注意が必要です。特に浴室は、長年の使用により床下の木材が常に湿った状態になりやすく、通気口が塞がれている物件では乾燥が間に合わず、シロアリにとって格好の棲み家となります。
加えて、床下に段ボールや木製のゴミ、未処理の建材などが放置されていると、それらがエサとなり被害が加速するケースもあります。湿気の多い空間をいかに作らないか、余分な木材をいかに残さないかが、シロアリ対策の基本です。
放置すれば「建物崩壊リスク」にも
見逃されがちなのは、「進行スピードの早さ」です。
1年も経てば、柱が空洞化し、床が抜ける寸前というケースも珍しくありません。建物全体の修繕費が100万円を超える例もあり、保険でカバーできないことが多いため、結果的に大家の自己負担になるのが現実です。
被害が建物の構造部分にまで及ぶと、部分的な修繕では済まず、床下全体の補強工事や壁の張り替えが必要になることもあります。
一見すると軽微に見える症状でも、実際に解体してみると内部の木材がスカスカだったという例も少なくなく、想定以上の出費になる可能性が高いのです。
シロアリが好む環境と、発生しやすい物件の特徴

ここでは、どんな物件にシロアリが寄り付きやすいのかを解説します。被害に遭いやすい構造や立地を知ることで、予防の第一歩につながります。
シロアリが好む典型的な環境
シロアリが好む典型的な環境は、以下のようなパターンです。
- 床下に湿気がたまりやすい
- 通気口が塞がれている、または風通しが悪い
- 物件敷地に木材・段ボールなどが放置されている
- 築20年以上で防蟻処理が未実施
また、たとえ都市部であっても安心はできません。地下駐車場がある物件では地熱による湿気がこもりやすく、床下換気が不十分だと知らぬ間にシロアリにとって快適な環境ができあがってしまいます。
知っておきたい「立地条件の罠」
旗竿地や三方囲まれた敷地など、風の通りが悪い土地は、建物の構造にかかわらず湿気がこもりやすいです。加えて、隣家や公園に大木があると、そこから羽アリが飛んできて定着するという「越境被害」も起こりえます。
特に春から初夏にかけての羽アリの群飛シーズンには、近隣からの「引っ越し」が起きることもあり、いわば自分の物件の環境だけ整えていても安心とは言えないのです。
さらに注意したいのが、傾斜地や道路より低い位置にある物件です。雨水や湿気が集まりやすく、床下の排水・排湿が追いつかない構造になっている場合、常にジメジメとした状態が続いてしまうため、木材が乾燥しにくくなり、腐朽や虫害のリスクが高まります。
「うちの物件も大丈夫かな…?」と不安な方は、物件管理のプロである弊社が、点検・対策までしっかりサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
シロアリ被害のチェックポイントとオーナーの予防策

「シロアリ被害は気づきにくい」と言われる理由は、その初期症状が非常にささやかで見逃されやすいためです。しかし、些細な変化に早めに気づくことができれば、被害を最小限に抑えることができます。
シロアリ被害のチェックポイント
新築物件の場合、引き渡しから10年間は防蟻工事の保証がついているケースがほとんどです。
注意すべきなのは、その保証期間を過ぎた物件や、中古として購入した物件。オーナーチェンジで引き継いだ場合は、「防蟻処理の履歴があるかどうか」をまず確認しましょう。
もし履歴が残っていなかったり、工事の有無があいまいな場合は、以下のようなポイントをチェックしてみてください。被害の早期発見や再発防止につながる重要なヒントになります。
シロアリ被害の兆候
- 羽アリが室内に発生(特に梅雨前の夕方)
- 床を歩くとフワフワする、沈む感覚がある
- 壁紙の浮き・変色・膨らみ
- 押入れや収納棚の奥がカビ臭い・崩れる
- 建物の外周に蟻道(アリの通り道の土の線)がある
- 木材を叩くと中が空洞のような軽い音がする(ポコポコ・カンカンと響く)
- 床下の木材や畳の下に、細かい粉状のフンや木くずが落ちている
- 建具の立て付けが急に悪くなった(ドアや引き戸が動きにくい)
- 風呂場や洗面所の床がわずかに傾いてきた、沈む感じがある
賃貸オーナーの場合、入居者自身がこうした異常に気づくとは限りません。特に1階の空室や長期間見回りをしていない物件では、シロアリ被害が進行していても誰も報告しないまま数ヶ月が経過してしまうこともあります。
オーナーの予防策
このような状態を防ぐためには、
- 定期的に物件を自ら確認する(特に空室時や水回り付近)
- 管理会社に「シロアリの兆候があればすぐ報告してほしい」と伝えておく
- 入居者にも「異変に気づいたら早めに連絡を」と案内しておく
- シロアリを見つけた場合の応急処置を伝えておく
といった事前の備えが、早期発見と修繕費の圧縮につながります。「早期発見できる体制」をオーナー側から作っておくことが、結果的に物件と収益を守る最大の防御策となるのです。
また、もし羽アリを見つけても、あわてて市販の殺虫スプレーを使うのはおすすめできません。というのも、シロアリは一般的な害虫と違い、専用の薬剤でないと効果がなく、かえって巣を刺激して広がってしまうことがあるためです。
同じく、掃除機で吸い取ろうとするのも逆効果になる可能性があります。排気でまき散らしてしまうこともあるので、応急処置としてはガムテープなどでそっと捕まえるのが安全です。
賃貸物件でシロアリ発生時の対応・駆除の流れ

シロアリの疑いがある報告を受けたとき、「とりあえず様子を見よう」「自分で何とかできるかも」と判断するのは危険です。管理会社や入居者からの連絡を受けた段階で、早期に適切な対応をとることが、被害の拡大を防ぐカギとなります。
ここでは、入居者対応を含めた初動の流れを具体的にご紹介します。
正しい対応ステップ
まず、シロアリ被害が疑われた時は、以下のステップで対応しましょう。
シロアリ被害の確認ステップ
- 入居者や管理会社から連絡を受けたら、すぐに現地を確認する
- 被害箇所を写真撮影し、状況をメモする
- 複数の専門業者に点検を依頼する(無料点検あり)
- 被害報告書・施工見積りを取得する
- 内容を比較・調整して、信頼できる業者に駆除依頼する
「価格」だけで業者を選んではいけない理由
業者を選ぶとき、つい価格に目がいきがちですが、あとから「安物買いの銭失い」になるケースは少なくありません。
チラシを見て、「この料金で済むなら…」と軽い気持ちでお願いしたところ、施工範囲がごく一部に限られていて、現地で「あれも追加、これも別料金です」と説明され、結果的に最初の見積もりの倍近い費用を請求されてしまった事例があります。
最初からしっかり説明してくれる業者を選んでいれば、そんな無駄なやりとりもなかったのに…と後悔していました。
床下は見えない部分だからこそ、ぼったくりや、本来不要なオプションを付けてくる業者がいるという話をよく耳にします。
だからこそ、最初の見積金額だけで判断してしまうと、施工の質やアフター対応まで気が回らず、あとになって不満やトラブルにつながることが多い印象です。
多少費用がかかっても、「再発時の対応」「保証期間の有無」「説明の丁寧さ」などを含めて、総合的に信頼できるかどうかを見極めることが、結果的には安心とコストの両面でプラスになります。
「うちの物件も大丈夫かな…?」と不安な方は、物件管理のプロである弊社が、点検・対策までしっかりサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
シロアリ予防・駆除にかかる費用目安と考え方

シロアリ対策の費用は、「予防」か「駆除」か、そして「施工面積(おもに床下)」によって大きく変わります。
一般的には、1㎡あたり1,500〜3,000円程度が相場とされており、延床面積や施工内容に応じて総額が決まります。
予防工事(防蟻)の2種類の工法
防蟻工事には、大きく分けて「土壌処理」と「木部処理」の2種類の工法があります。
土壌処理は、建物の基礎部分の地面に薬剤を注入・散布し、シロアリが建物に侵入できない「バリア」をつくる方法です。一方の木部処理は、被害が出やすい床下の柱や土台などの木材に、薬剤を直接処理する方法です。築年数が経過した物件では、木部処理がよく用いられます。
| 土壌処理 (薬剤を地面に注入) |
|
| 木部処理 (建物の木材に薬剤を塗布・注入) |
|
予防工事の費用目安
施工費用には地域差や業者ごとの差がありますが、一般的な目安は以下のとおりです。
| 土壌処理 | 約1,500~2,500円/㎡ |
| 木部処理 | 約1,200~2,000円/㎡ |
一般的な施工業者では5年保証が多く、まれに10年保証プラン(やや高額)を用意している会社もあります。
駆除工事の費用目安
| 駆除工事の内容 | 費用の目安 | 備考 |
| 被害箇所のスポット駆除 | 5万〜10万円程度 | 小規模な被害。薬剤注入やベイト剤の設置で対応可能なケース |
| 床下全面の駆除・薬剤処理 | 10万〜20万円程度 | 被害が広範囲に及ぶ場合。木部・土壌ともに処理することも |
| 構造部分まで被害が進行した場合 | 50万〜100万円以上 | 床や柱の補修、大工工事、リフォームが必要なケースも含む |
| 駆除+再発防止の保証付き施工 | 上記に+3万〜5万円程度 | 一定期間の保証(例:5年)や、再発時の無償対応がつくことも |
経費処理と資本的支出の考え方
基本的に、賃貸経営に必要な修繕は「経費」としてその年の所得から差し引くことができます(いわゆる損金処理)。
たとえば、すでにシロアリ被害が出ていて、柱の補修や床の張り替えを行う場合は「修繕費」として処理でき、節税にもつながります。
一方で注意したいのが、「予防目的の施工」です。
「今後のために薬剤を撒いておこう」といった施工が大掛かりになると、「資本的支出」と見なされる可能性があります。これは建物の価値や耐久性を高めるための支出とされ、一括で経費にできず、数年に分けて減価償却していく必要があり、税務処理がやや複雑になります。
つまり、「予防だから安心」と思っていた施工が、経費にできず税務署から指摘される可能性もあるということです。無駄なく物件を維持していくためにも、税理士や管理会社と相談しながら、「予防」と「修繕」の線引きを意識することが大切です。
賃貸ならではの注意点|入居者とのトラブルを防ぐには?

物件が賃貸である以上、シロアリ被害が発生した際や施工時には入居者への説明や対応が欠かせません。「責任の所在」や「施行中の配慮」をめぐってトラブルが起こることもあるため、事前の備えが必要です。
修繕義務は貸主にあるのか?
民法では、「大家(貸主)は、建物をきちんと使える状態に保つ義務がある」と決められています。
そのため、たとえば建物の老朽化や換気不足が原因でシロアリが発生した場合は、基本的に大家が対応する責任があります。
ただし、入居者に明らかな落ち度があるケース(例:木材をたくさん室内に積んでいたなど)では、費用を一部負担してもらえる可能性もあります。
とはいえ、現場では「誰のせいか」をはっきりさせるのが難しいことが多く、トラブルを避けるためにも大家が対応した方がスムーズに収まるケースが多いというのが実情です。
入居者の落ち度に対して責任を問いたい場合は、あらかじめ契約書にシロアリ被害に関する条文を盛り込んでおくと安心です。たとえば「室内での木材保管の禁止」などを明記しておくことで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
入居者に「シロアリ被害を防ぐ生活習慣」を伝えよう
シロアリは、湿気とセルロース(紙や木材に含まれる成分)を好む性質があります。
賃貸住宅では、「入居者の何気ない習慣」が原因でシロアリが発生し、トラブルへと発展することも。そこで、入居時の案内や掲示などで注意喚起しておくと安心です。以下は、入居者に伝えておきたい「やめてほしい行動」の一例です。
- 段ボールを長期間床に置きっぱなしにしない
- 本や雑誌を床に直置きしない
- 木製家具を壁や床に密着させたままにしない
- 観葉植物を直接床に置かない
- 室内に未処理の木材を保管しない(DIY用など)
- 庭やバルコニーにウッドチップや丸太、廃材を放置しない
- 湿気のこもる場所の換気を怠らない(特に水回りや押入れ)
- 羽アリや蟻道(ありみち)を見かけたのに放置しない
防蟻工事の施工には入居者へ配慮しよう
シロアリ対策の工事は、物件を守るために欠かせないものですが、入居者にとっては突然の薬剤散布に不安を感じることもあります。
「どんな薬剤を使うのか」「体に影響はないのか」「においは残らないか」など、気になるポイントは人それぞれです。だからこそ、施工の前に、使う薬剤の種類や安全性、施工の日時や内容についてきちんと説明することが大切です。
場合によっては、一時的に換気が必要だったり、においが気になる時間帯があったりすることもあるため、その点も事前に伝えておくと安心です。
予防が最大の対策!資産を守るためにできること

ここまで読んで「やっぱり駆除が大変そうだな」と思われたかもしれません。しかし、筆者が最も強調したいのは、「シロアリは予防できる」という事実です。
ここでは、大家ができる予防対策を具体的に紹介します。
定期点検の習慣化
賃貸物件では、「築10年を超えたら年1回の床下点検」をルール化することをおすすめします。結果として、羽アリが出る前に兆候を察知し、5万円以内の処置で済んだケースが複数ありました。
信頼できる業者による定期点検をルーティンにすることで、コストも被害も最小限に抑えられます。
空室期間を活用した予防工事
空室が出たタイミングは、防蟻処理の絶好のチャンスです。床下への薬剤散布、防湿シート設置、換気口のメンテナンスなどを原状回復工事と同時に実施することで、工事費の圧縮にもなります。
実際、あるオーナーは空室時に防蟻処理を実施し、その履歴をしっかり残しておいたことで、売却時に買主から「管理状態が良い物件だ」と高く評価され、スムーズな売却につながったというケースもあります。
予防は、「将来の資産価値」にも大きく影響するのです。
まとめ|「備え」が空室リスク・資産劣化を防ぐカギ
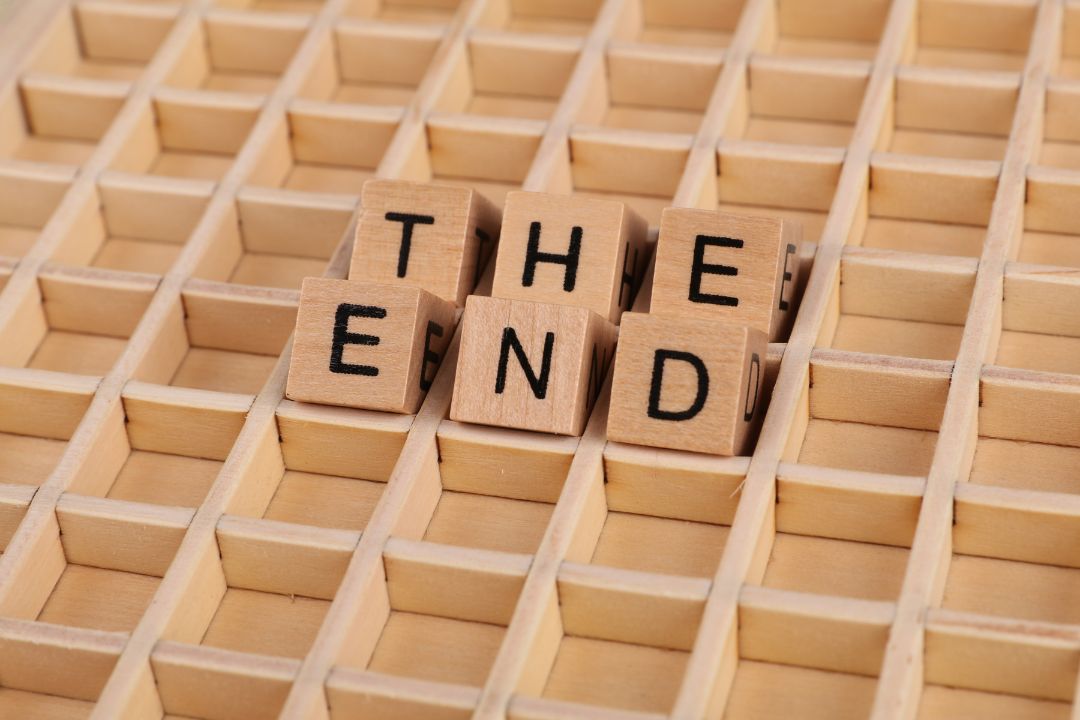
この記事では、賃貸物件におけるシロアリ対策について、発生の仕組みや被害の兆候、具体的な駆除方法、そして費用の目安まで詳しく解説しました。
シロアリは木造に限らず、RC造や鉄骨造でも被害を及ぼす可能性があり、放置すれば資産価値の低下や重大な修繕コストにつながります。
だからこそ、日頃の点検や湿気対策、そして空室期間を活かした予防処理が重要です。
また、入居者とのトラブルを防ぐためには、施工時の丁寧な説明や契約書への備えも欠かせません。
「備えておけばよかった」と後悔しないためにも、シロアリは“予防が最も効果的な対策”であることを忘れずに、今できる対策から始めていきましょう。
「うちの物件も大丈夫かな…?」と不安な方は、物件管理のプロである弊社が、点検・対策までしっかりサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。






コメント