
「申込みが入ったのに、急にキャンセルされた…」そんな経験はありませんか?
オーナーにとって賃貸申込後のキャンセルは、心理的にも実務的にも大きな負担です。再募集の手間や広告費、空室期間中の家賃収入の損失など、見えない損害が積み重なります。
近年は、複数物件への「仮押さえ」や「同時申込」も珍しくなく、申込後のキャンセルが頻繁に発生しています。場合によっては、申込から入居直前まで進んでいたのに、突然キャンセルされるというケースも。
本記事では、キャンセルが発生した場合にどう対応すればよいかに加え、事前にできるトラブル予防策や法的観点からの正しい知識までを、オーナー目線で解説していきます。
キャンセル対応やトラブル防止策でお困りの方は、お気軽にご相談ください。再募集やトラブル予防の体制づくりについても、専門スタッフがサポートいたします。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- 賃貸申込後キャンセルは法的に可能?不可能?
- 申込書の法的位置づけとは?
- 重要事項説明の有無が大きな分かれ目
- 契約成立後は原則キャンセル不可
- 申込後キャンセルでキャンセル料は請求できる?
- キャンセル料が請求できるケース
- キャンセル料が請求できないケース
- 裁判例と実務での扱い
- 申込金や手付金は返還義務がある?
- 申込金の法的性質とは?
- 手付金との違い
- 返還が必要なケースと不要なケース
- 重要事項説明書・賃貸借契約書作成前後の対応方法
- 重要事項説明前のキャンセル対応
- 契約書作成後のキャンセル対応
- こんなキャンセル理由でもキャンセル料は取れる?実例集
- 転勤・転職によるキャンセル
- 家族の反対によるキャンセル
- より良い物件が見つかったケース
- 審査結果を理由としたキャンセル
- 悪質なキャンセルへの対応
- 申込後のキャンセルトラブルを未然に防ぐには
- 申込時にしっかり流れを説明する
- 規定を明文化した申込書面を作成する
- 管理会社との連携を強化する
- キャンセル連絡を受けた時の対応フローチャート
- ①キャンセル理由をヒアリングする
- ②申込後の進捗状況を確認する
- ③書面でのやり取りを行う
- ④キャンセル料の請求可否を確認する
- キャンセル後の空室対策・再募集
- まとめ|キャンセル対応の精度を上げて、空室リスクを最小限に
賃貸申込後キャンセルは法的に可能?不可能?
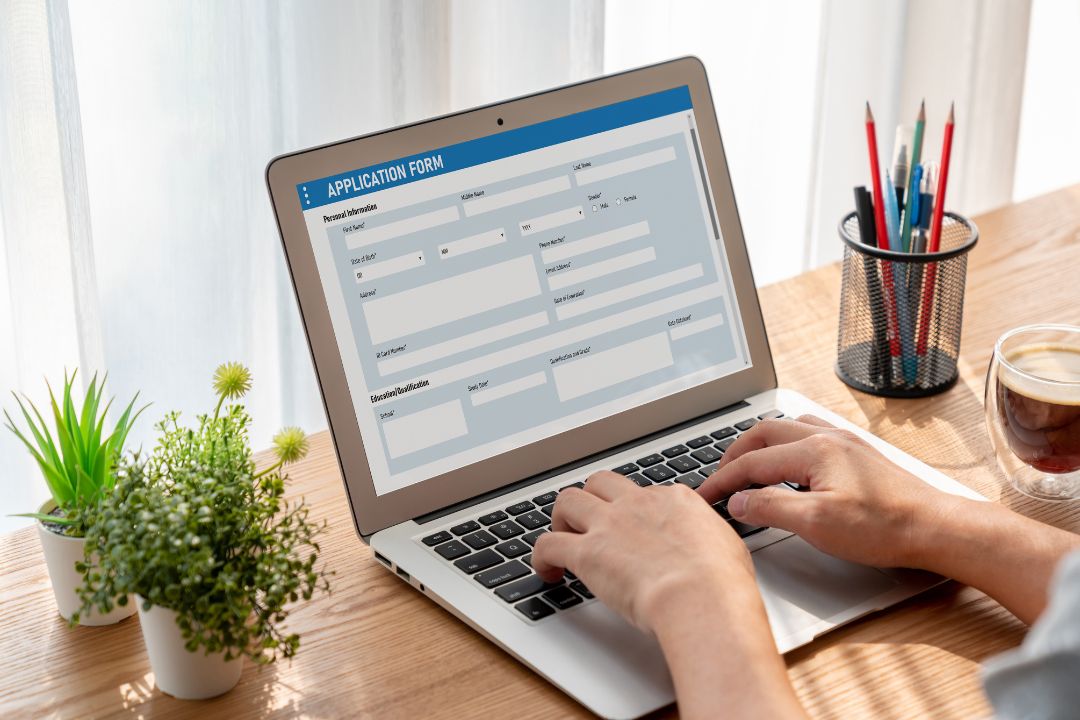
賃貸借契約において、入居申込書の提出後にキャンセルされると、落胆してしまうオーナーは多いでしょう。では、そのキャンセルは法的に認められている行為なのでしょうか?
この章では、宅建業法や判例を踏まえて、申込みと契約の違い、キャンセルの可否、そして重要事項説明のタイミングによって変わる扱いについて、わかりやすく解説します。
申込書の法的位置づけとは?
賃貸契約における「申込書」は、単なる借主の意思表示に過ぎません。
宅地建物取引業法上の取り扱いでは、実は「申込書の提出=契約成立」とはみなされません。つまり、申込段階ではまだ契約上の義務は発生しておらず、キャンセルも法的には可能とされるのが原則です。
重要事項説明の有無が大きな分かれ目
賃貸契約の成立には、「重要事項説明」の実施が必要不可欠です。
この説明を受け、書面に記名押印したうえで契約書が交わされていれば、法的にも契約が成立しており、正当な理由なくキャンセルすると損害賠償の対象になることもあります。
反対に、重要事項説明前のキャンセルは、「申込撤回権」の範囲とされ、借主が自由に撤回できるのが実務の通例です。
契約成立後は原則キャンセル不可
通常、賃貸借契約は「重要事項説明書の交付・説明」を経たあとに「契約書の締結」という流れで進みます。この契約書の締結後は、キャンセルは原則不可です。
契約者は、「やっぱり気が変わった」「他に良い物件を見つけた」といった身勝手な理由では解約できず、貸主は損害賠償を請求できる余地があります。
ただし、損害賠償を請求できる「余地がある」というだけで、必ずしも請求が認められるとは限りません。実際に請求するためには、いくつかの法的条件を満たす必要があります。
申込後キャンセルでキャンセル料は請求できる?

申込者が一方的にキャンセルしてきた場合、「せめてキャンセル料くらいはもらいたい」と思うのがオーナーとしての正直な気持ちでしょう。では、実際にキャンセル料を請求することは可能なのでしょうか。
キャンセル料が請求できるケース
基本的に、契約前のキャンセルに対してキャンセル料を請求することは難しいとされていますが、「一定の実害が発生していること」と「キャンセル料の事前明示」があれば、請求の根拠は生まれます。
たとえば以下のような場合、キャンセル料請求が認められる可能性があります。
- 申込時に「キャンセル時は実費負担が生じる」と説明・明記していた
- オーナー側が広告停止・他の内見を断るなど、損害が発生していた
- 契約直前でのキャンセルで、再募集までに空白期間が生じる
ただし、こうした主張を通すためには「説明の明確化」「書面での証拠」「実際の損害金額の根拠提示」が不可欠です。
キャンセル料が請求できないケース
一方で、以下のような場合はキャンセル料の請求が難しく、トラブルに発展しやすくなります。
- 申込書にキャンセル料の記載がない、または不明確
- 入居審査中や契約前の段階で、まだ確定ではなかった
- 口頭だけの説明にとどまり、証拠が残っていない
宅建業法において「不当な金銭請求」は禁じられているため、契約前段階のキャンセル料設定は慎重に行う必要があります。根拠のない一律の請求は、信義則違反や損害賠償請求を受けるリスクもあります。
裁判例と実務での扱い
実際の裁判では、「キャンセルによってオーナーに損害が発生していたか」が問われています。
たとえば、ある判例では、広告停止や他の内見拒否による機会損失を理由に、数万円のキャンセル料が認められた事例があります。ただし、請求額が高すぎたり、証拠が乏しかったりした場合は、認められない傾向が強いです。
実務上は「せいぜい数千~数万円程度」、しかも「事前明示されていること」が重要なポイントとなります。
申込金や手付金は返還義務がある?

キャンセル時に問題となりやすいのが、「申込金」や「手付金」の扱いです。実際に返還義務があるのかどうかは、金銭の性質や契約の有無によって異なります。
申込金の法的性質とは?
一般的に「申込金」は、申込意思を示す際に預かるお金ですが、契約前であれば原則として「全額返金が必要」です。
これは宅建業法における「契約締結前の預かり金」の扱いに基づいており、不当に返還を拒むと業法違反に問われるリスクもあります。
手付金との違い
一方、「手付金」は契約成立後に交わされる金銭であり、契約の履行確保・違約時の損害担保としての性質を持ちます。
契約締結後に借主が解約する場合、手付金を放棄すれば解約が可能(手付解除)とされています。つまり、手付金=契約の成立後、申込金=契約前の仮預り金という位置づけになります。
返還が必要なケースと不要なケース
| 返還が必要 | 申込金であり、契約未締結の場合 |
| 返還しなくてよい可能性あり | 契約締結済みで、かつ手付金として扱われている場合 |
ただし、申込金と手付金の違いが曖昧なまま預かっていると、トラブルの原因になります。「いつ、どの段階で、何の名目で預かったお金か」を記録し、借主にも書面で説明することが重要です。
キャンセル対応やトラブル防止策でお困りの方は、お気軽にご相談ください。再募集やトラブル予防の体制づくりについても、専門スタッフがサポートいたします。
重要事項説明書・賃貸借契約書作成前後の対応方法

キャンセル対応は、「どの段階でのキャンセルか」によっても大きく対応が異なります。具体的にどのような対応をすべきか、その方法を紹介します。
重要事項説明前のキャンセル対応
重要事項説明の前段階、つまり「申込直後」や「入居審査中」のキャンセルは、借主の自由意思による撤回が可能です。
この時点では法的な契約関係が成立していないため、オーナーとしては「キャンセルを未然に防ぐ対策」が必要になります。
- 申込書にキャンセル条件や損害負担の明記をする
- 仲介業者からの複数申込や仮押さえを避けてもらう
仲介業者の中には、自分の成績のためだけに、顧客が内覧を希望するほぼすべての物件を先回りして仮押さえしてしまう担当者も存在します。こうした事態を防ぐには、勤務先や年収など、申込書に顧客の情報をできるだけ細かく記載してもらうようにしましょう。
入居意欲が高い人ほど「他の人に取られたくない」という思いから、仲介業者に自ら進んで個人情報を伝える傾向があります。反対に、希望度が低い入居者は情報提供を渋るため、その反応がひとつの判断基準にもなります。
契約書作成後のキャンセル対応
重要事項説明が完了し、契約書も締結済みであれば、借主がキャンセルしても「契約解除」として扱えます。この段階であれば、違約金や手付放棄といった対応もしやすく、契約書に違約条項を明記しておくことで、オーナーはより有利な立場を確保できます。
理想をいえば、申込当日に重要事項説明まで済ませられるのが望ましいでしょう。そのためには、仲介業者と連携し、オンラインで重要事項説明書を即時印刷できるようログイン環境を共有しておくと効率的です。
とはいえ、実務ではシステム環境が整っていない場合や、入居希望者の予定が合わない場合もあります。そのような場合は、重要事項説明書と契約書を回収するまでの期間管理が重要です。期間が長くなるほど、他の物件に流れる可能性が高まります。
申込後は「〇日以内に契約書を回収する」といった期限を明確に設定し、迅速に手続きを進めることが契約成立の鍵です。
キャンセル対応やトラブル防止策でお困りの方は、お気軽にご相談ください。再募集やトラブル予防の体制づくりについても、専門スタッフがサポートいたします。
こんなキャンセル理由でもキャンセル料は取れる?実例集
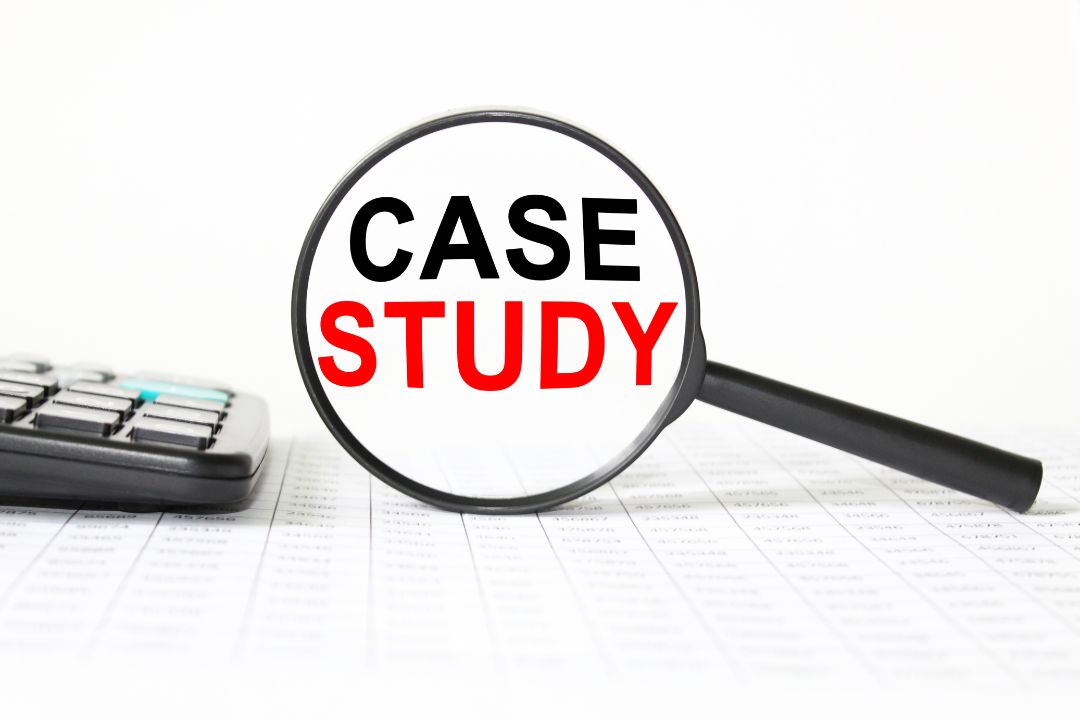
実務では、申込者からさまざまな理由でキャンセルが申し出られます。ここでは、よくあるケースとその対応方法、キャンセル料の可否について解説します。
転勤・転職によるキャンセル
「急に転勤が決まってしまった」「転職先が変わったので通勤が困難になった」といった事情によるキャンセルは比較的多いです。このようなケースでは、借主に落ち度はなく、社会的にも理解されやすいため、キャンセル料を請求することは原則難しいと考えられます。
ただし、申込書に「契約直前のキャンセルに関しては、実費を請求することがある」と明記してあれば、実費相当額の請求は可能な余地があります。
家族の反対によるキャンセル
「親に反対された」「同居予定者と意見が合わなくなった」という理由でのキャンセルも散見されます。この場合、契約直前の段階であれば、再募集の機会損失が発生していることを主張して、一定の実費負担を求めることは可能です。
とはいえ、感情的なトラブルにもつながりやすいので、請求する場合は、法的根拠や説明責任を明確にしつつ、書面による対応が望ましいです。
特に、入居希望者が18歳〜20歳未満の場合は、親が直接対応に出てくることも珍しくありません。そのときは、損害金請求がなぜ妥当なのかを丁寧に説明できるよう準備しておきましょう。契約の経緯や発生した損害の内容を整理し、契約書や重要事項説明書に基づいて説明することで、相手にも納得してもらいやすくなります。
より良い物件が見つかったケース
内見後に申込をしたものの、数日後に「他にもっと条件のいい物件があった」と言ってキャンセルされる例も多くあります。このようなキャンセルは、契約前であれば拒否はできないものの、実際には「二重申し込み」や「仮押さえ感覚」の可能性もあるため、仲介業者との連携で事前に防止する工夫が必要です。
勝手な都合によるキャンセルについては、仲介業者に損害金を請求する旨を申込書に明記し、あらかじめ仲介業者から同意書を受け取っている管理会社もあります。
審査結果を理由としたキャンセル
入居審査に通らなかった場合のキャンセルは、借主の責任ではないため、キャンセル料の請求はできません。
オーナーの判断より前に審査で落ちるケースとしては、ほとんどが家賃保証会社の審査に通らない場合です。保証会社の審査が通らない入居希望者は、家賃滞納のリスクが高い可能性があります。そのため、無理に入居させようとせず、早めに募集を切り替えるなど、割り切った対応が望ましいでしょう。
ただし、「審査結果を待たずに、勝手に辞退した」「虚偽の申告があった」など、借主側に問題があった場合は、実費相当の請求も検討できます。
悪質なキャンセルへの対応
「何度も申込とキャンセルを繰り返す」「申込金を支払う素振りだけで時間稼ぎをする」など、明らかに悪質と判断されるケースでは、法的措置も視野に入れましょう。
また、勝手な都合によるキャンセルなので、より良い物件が見つかったケースと同様、仲介業者への請求も検討すべきです。
申込後のキャンセルトラブルを未然に防ぐには

キャンセル対応に追われないためには、「そもそもキャンセルされない工夫」を最初から仕込んでおくことが何より重要です。
申込時にしっかり流れを説明する
入居申込の際に、以下のような説明を丁寧に行い、入居希望者にも申込に対する責任を持ってもらうことが重要です。
- 申込後は広告を停止し、他の申込を断っていること
- 契約直前のキャンセルはオーナー側に損害が出ること
- キャンセル料の可能性や申込金の返金条件
これらを口頭だけでなく、書面(申込書や説明資料)として残しておくことで、後のトラブル回避につながります。
規定を明文化した申込書面を作成する
申込書には、以下のような内容を盛り込んでおくと安心です。
- キャンセル時の取扱い(損害が出た場合は実費請求の可能性がある旨)
- 契約予定日
- 申込金の性質と返金の可否
- 仲介業者とオーナーの連絡フロー
不明確な記載や曖昧な表現は避け、明文化された文言を採用しましょう。心配な方は、専門家に確認したうえで用意しましょう。
重要事項説明の中にキャンセル時の取り扱いを補足として組み込んでおくと、契約前後どちらのタイミングでもトラブル予防になります。
管理会社との連携を強化する
自主管理の場合は、申込者との連絡を一貫して記録に残しておきましょう。
管理会社に委託している場合は、「申込受付時の個人情報の記載範囲」や「キャンセル発生時の連絡ルール」などをあらかじめ取り決めておくと、トラブル時の判断もスムーズになります。
キャンセル連絡を受けた時の対応フローチャート

仲介業者や入居者からキャンセル連絡を受けた際に慌てないために、対応手順をあらかじめ明確にしておきましょう。
①キャンセル理由をヒアリングする
- 感情的にならず、まずは冷静に事情をヒアリング
- 書面(メール・LINE・FAXなど)でのキャンセル意思の確認を要請
- 申込書や説明書面の控えを確認
初期対応次第で、後のトラブル防止につながります。せっかく申込があったのにキャンセルとなれば残念ですが、まずは理由をしっかり確認することが大切です。
例えば「他物件への乗り換え」「家族の反対」「条件面の不一致」など、背景によって今後の対応策も変わります。仲介業者側にも対応の不備や責任があると感じた場合は、次回以降のためにも、良し悪しの線引きやルールを明確にしておくと安心です。
②申込後の進捗状況を確認する
- 契約書の作成・締結状況
- 入居審査の進行状況
- 広告停止や内見断りなど、オーナー側の実害の有無
それにより、「実費請求の可否」や「再募集の開始タイミング」が変わってきます。
③書面でのやり取りを行う
電話や口頭でのやり取りは誤解を招きやすく、証拠にもなりません。
キャンセルする日付、理由、物件名、号室、氏名などを記載した「キャンセル通知」は、必ずメールまたは書面でやり取りしましょう。FAXであれば受信日時が書面に残りますし、メールでも受信日時が記録されます。これらの確認が取れた時点で、部屋を再び募集可能な状態にし、速やかに再募集を開始しましょう。
これは、万一訴訟になった場合にも役立ちます。
④キャンセル料の請求可否を確認する
キャンセル料を請求できるかどうかは、理由や契約の進み具合によって変わります。まずは状況を整理し、「このケースは請求できるのか」を冷静に見極めたうえで動くことが大切です。
また、以下のような場合は、早めに弁護士への相談を検討しましょう。
- 悪質なキャンセルで明らかに損害が出ている
- キャンセル料の支払いを拒否されている
- 申込金の返還トラブルに発展している
- 申込者がやり取りに際して高圧的・威圧的になっている
申込者が消費者センターなど外部機関に相談する可能性もあります。相手の感情が高ぶっている状況で強引に話を進めると、かえって解決が難しくなるケースも少なくありません。
冷静かつ柔軟なやり取りを心がけ、必要に応じて第三者の力を借りながら進めましょう。
キャンセル後の空室対策・再募集

キャンセルが確定したら、できるだけ時間を空けずに再募集を行うことが、空室期間を短くする最大のポイントです。
たとえば、以下のような準備を常に整えておくと、キャンセル発生後すぐに募集を再開できます。
- ポータルサイトに即時掲載できるよう、募集図面・物件情報を最新版に更新しておく
- 室内写真や動画を最新の状態で保存しておく
- 前回の広告掲載媒体・掲載内容を控えておき、すぐ再掲載できるようにする
- 内見可能日や鍵の手配状況を把握しておく
- 仲介業者と共有できるシステムに募集資料を一元管理しておく
また、キャンセル前に「その部屋は空いていますか?」と問い合わせがあった仲介業者には、キャンセルが出たタイミングで電話連絡するのも効果的です。「キャンセルが出ました」と一報を入れるだけで、タイミング次第ではそのまま申込につながるケースもあります。
まとめ|キャンセル対応の精度を上げて、空室リスクを最小限に

本記事では、申込後キャンセルが起きた際の対応フローに加え、以下のポイントを解説しました。
- 宅建業法の観点をふまえたキャンセル料の可否
- トラブルになりやすいケース別の対応方法
- 申込書や説明の工夫による事前対策
- 管理会社や仲介業者との連携強化
- キャンセル発生後の再募集の迅速化
申込後のキャンセルは、残念ながらどれだけ丁寧に運用していても一定の確率で発生します。
しかし、「防げるキャンセル」と「不可抗力のキャンセル」を見極め、事前に打てる手を打っておくことで、空室リスクや損害を最小限に抑えることが可能です。
「またキャンセルか…」と嘆く前に、対応の仕組みを見直し、再発防止とオーナーとしての安心運営につなげていきましょう。
キャンセル対応やトラブル防止策でお困りの方は、お気軽にご相談ください。再募集やトラブル予防の体制づくりについても、専門スタッフがサポートいたします。





コメント