
2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務付けられました。不動産の所有者が誰かを明確にし、後々のトラブルを避けるための重要な法改正です。 しかし、改正点や手続きの方法をよく理解できていない方もいるかもしれません。
そこで、この記事では、相続登記の義務化に伴う改正ポイントと、名義変更手続きの流れや費用、それを怠ることのデメリットを解説します。 最後には、遺産相続が難航していてすぐに登記ができない場合など、罰則を免れる対策についても説明していきます。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- 【2024年】不動産における相続登記(名義変更)の義務化
- 相続登記とは何か
- 相続登記の義務化の開始時期
- 相続登記が義務化された理由
- 3年以内に所有権の名義人変更が必須
- 相続登記の義務化による5つの改正ポイント
- 1. 相続登記の義務化
- 2. 罰則は10万円以下の過料
- 3. 相続人申告登記制度の新設
- 4. 遺産分割後の名義変更登記も義務化
- 5. 相続登記の簡素化
- 相続不動産の名義変更をしないデメリット5選
- 1. 不動産の売却・贈与・賃貸ができない
- 2. 空き地の有効活用ができない
- 3. 金融機関からの借入ができない
- 4. 差し押さえの可能性がある
- 5. 時間が経つほど手続きが複雑になる
- 不動産相続で自分で名義変更申請をする方法
- 1. 登記事項証明書(謄本)を取得する
- 2. 遺言書の確認をする
- 3. 遺産分割協議書を作成する
- 4. 登記必要書類を準備する
- 5. 登記申請書を法務局へ提出する
- 不動産の名義変更にかかる費用
- 1. 登録免許税
- 2. 必要書類の取得費や各種手数料
- 3. 士業への報酬
- 相続登記の義務化による罰則を免れる方法
- 1. 相続放棄という選択肢をとる
- 2. 新制度「相続人申告登記」をする
- まとめ
【2024年】不動産における相続登記(名義変更)の義務化

今回の法改正により、親や兄弟が亡くなった場合、不動産を受け継いだ相続人は相続登記が必須となりました。相続人の手間やコストが増える形となりましたが、少子高齢化で空き家が増える中で必然的な取り組みです。
まずは、相続登記の義務化における概要や背景について解説しましょう。
相続登記とは何か
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その所有権を兄弟や子など相続人に移転する手続きのことです。この場合の所有者とは、実質的にそこで居住していた人ではなく、登記簿謄本に記載されている名義人になります。
これまで相続登記は任意だったので、全国的に名義変更を行わないケースが散見されていました。
しかし、今回の改正によって相続登記を行うことで、対象不動産の権利が誰にあるのかが明らかになり、さまざまなトラブル解消が期待されています。
相続登記の義務化の開始時期
相続登記の義務化は、2021年(令和3年)に法律が決まり、2024年(令和6年)4月1日から正式に施行しました。
しかし、実際には2024年3月31日以前に相続で取得した不動産(土地・建物)も対象となり、相続人には登記義務が課されます。
「2023年に相続したから、登記義務は課されない」という訳ではありません。
相続登記が義務化された理由
相続登記が義務化された理由は、日本中に所有者不明の不動産が非常に多く点在しているからです。
これは空き家を増やしたり、老朽化が進んだ危険な建物を放置したりと、周辺環境の悪化が拡大するなどの社会問題となっています。また、公共・民間ともに事業発展を妨害してしまい、人々の安全・快適な暮らしを保護できなくなってしまいます。
このような状態を改善するために不動産の所有者と話し合いをしたくても、相続登記がされていないと誰に伝えたらいいのか分からないのです。
3年以内に所有権の名義人変更が必須
では、今回の改正で相続登記は具体的にどのように定義されたのでしょうか。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。 出典:法務省ホームページより |
法務省ホームページでは上記のように定めており、相続で取得したことを「知った日」から3年という期限内に手続きを行うことを義務付けました。
遺産分割協議に時間がかかったとしても、多くの人は3年の猶予があれば申請できるでしょう。
まだ時間があるからと後回しにしてしまい、3年が経過してしまわないよう注意してください。
相続登記の義務化による5つの改正ポイント

本章では、より具体的に今回の改正ポイントを掘り下げていきます。
- 相続登記の義務化
- 罰金は10万円以下の過料
- 相続人申告登記制度の新設
- 遺産分割後の名義変更登記も義務化
- 相続登記の簡素化
主要の変更項目は上記の5点です。以下で1つずつ解説しましょう。
1. 相続登記の義務化
先述の通り、2024年4月1日より不動産の名義変更・相続登記が義務化されることとなりました。これまで相続登記(名義変更)は任意だったことから、手間や費用を考えて手続きを行わないケースが多かったようです。
しかし、登記名義人の不一致が原因で起こる問題が後を絶たず、かねてより法改正が必要とされていました。
今回の義務化で、相続人は相続発生後3年以内に登記を完了させなければならなくなります。適切な手続きを行わず、期限を逃すと罰則が設けられるようになったため注意が必要です。(後述)
2. 罰則は10万円以下の過料
正当な理由がないのに相続登記(名義変更)を怠った場合、発覚すると10万円以下の過料を科される可能性があります。
また、登記名義人の氏名・住所に変更があった場合、2年以内に登記手続きをしなければ、5万円以下の過料対象となる点も付加されました。
いずれにしても、今回の義務化では「登記名義人を把握できる状態にすること」が法改正の意図です。
3. 相続人申告登記制度の新設
新たな追加点として「相続人申告登記制度」が新設されました。これは、相続人全員の合意が得られない場合でも、一定の手続きに従い、代表相続人が登記を行えるようにするための制度です。
これにより、相続人間の協議が長期化している状況でも、3年の期限内に相続登記を進めることが可能となります。
紛争の解決やトラブル回避のための大きな一歩と言えるでしょう。
4. 遺産分割後の名義変更登記も義務化
上記3のケースでは、遺産分割協議の結論が出ていない状況です。
遺産分割の結論が出た際、「相続人申告登記制度」を利用して登記した名義人と正式な相続人異なる場合は、再度名義変更登記をしなくてはなりません。一時的な仮登記を、正式な状態に訂正するというイメージです。
この場合は、「遺産分割協議で確定した不動産の相続人」に登記義務があり、遺産分割の日から3年以内に行う必要があります。
5. 相続登記の簡素化
相続登記の手続き自体がより簡素化されるため、利用者にとっては分かりやすく、スムーズな流れで名義変更が行えるようになります。大きく分けると以下の2つのシーンで適用されます。
被相続人による遺言書が残されている場合
故人の遺言書が残されている場合、相続登記には法定相続人(全員)と遺言執行書のもと執行者の協力が必要でした。
しかし、今回の改正では遺言書による相続人が単独で行えるようになります。
上記4に該当するシーンの場合
一度、法定相続人全員の名義を登記した後でさらに名義変更をする場合、相続人が単独で行えるようになりました。
以前のように法定相続人全員の協力がなくても登記可能なので、相続登記にかかる負担が軽減されています。
相続不動産の名義変更をしないデメリット5選

相続登記をしないことによる問題点は、過料という罰則だけではありません。
ここでは、名義変更を怠った場合の具体的なデメリットについて解説します。名義変更をしっかり行わないと、財産管理が困難になるだけでなく、最悪の場合、財産を失ってしまうこともあり得ますので、注意が必要です。
1. 不動産の売却・贈与・賃貸ができない
まず、相続登記を怠ると、対象不動産の売却や贈与、賃貸に出すことが難しくなります。
売買や賃貸で不動産会社が携わる際、謄本で取得した売主情報を重要事項説明書で説明する義務があります。
ここで売買・賃貸の依頼者と、登記名義人が一致していなければ、不動産会社に取り扱ってもらえないでしょう。
例えば、売買では買主に所有権移転ができないなどの問題があるからです。これによって、せっかく買主が現れたタイミングで売却することができず、損失を生み出してしまう可能性があります。
2. 空き地の有効活用ができない
日本では空き家問題がとても深刻化していますが、相続登記をしていなければ所有者が分かりません。
そして、空き地もまた同様です。せっかく新築住宅や商業施設の建築にふさわしい用地があったとしても、事業者はこれらを有効活用できません。
日本全体の発展が制限されてしまい、購入希望者たちは条件に最適な不動産と出会えなくなります。
3. 金融機関からの借入ができない
相続不動産を担保に金融機関からの借入を行いたい場合、名義変更がされていないと、その不動産を正式な担保として認められません。故人名義のままでは、不動産を担保にしたローンや資金調達ができないため、資金繰りに大きな障害が生じることでしょう。
生活資金や転職、事業運営など、幅広い資金需要において大きなハンデとなってしまいます。
4. 差し押さえの可能性がある
特に大きなダメージとなるのが、不動産を差し押さえされてしまう可能性があることです。
例えば、兄弟二人が法定相続人で、兄は不動産、弟は現金を相続することで遺産分割協議が確定したとしましょう。
本来であれば、不動産を相続した兄に相続登記の義務が課されます。しかし、ここで相続登記を怠ってしまうと、弟が差し押さえになった場合、対象不動産が兄弟の共有物とみなされ差し押さえられる可能性が高まります。
このような事態を防止するためにも、相続登記は必ず行っておきましょう。
5. 時間が経つほど手続きが複雑になる
長い間登記が行われていない不動産を売却するとなると、手続きがとても大変になります。
最後に登記されている名義人から、その親族の関係性を遡らなくてはならず、全ての相続人とやりとりをする必要性が出てきます。場合によっては、共有持ち分を有する人物が、10人以上になることも珍しくありません。
仕事の傍ら、これら全ての人のアポイントを取り、承諾を得ることは非常に大変な作業です。
不動産相続で自分で名義変更申請をする方法

ここまでを読み、相続登記の重要性やリスクについて理解できたことでしょう。
では、実際に不動産の相続登記はどのように行えば良いのでしょうか。
- 司法書士、弁護士に依頼する
- 自分で手続きをする
具体的には上記2通りのいずれかの方法になります。代理人が登記をする場合は、司法書士や弁護士といった専門資格を有する人のみ認められており、誰にでも依頼できるわけではありません。
今回は自分で手続きをする方法について紹介しましょう。
1. 登記事項証明書(謄本)を取得する
まずは、法務局で不動産の登記事項証明書を取得しましょう。通称、登記簿謄本と呼ばれるものです。
登記簿謄本は、土地・建物の「住所」ではなく「地番」から取得します。住居表示実施地区では、住所と地番が異なる場合があるため、事前に地番を把握しておく必要があります。
登記簿謄本では、対象不動産における過去の権利履歴が閲覧可能です。ここでは最下部に記載されている、最新の名義人が誰かを確認する必要があります。
2. 遺言書の確認をする
次に、被相続人の遺言書の有無を確認しましょう。
通常、故人の資産に対して、法律で相続割合が定められています。家族がいる場合には配偶者が1/2、残りの1/2の持ち分を子供たちで平等に分割します。
しかし、この法定相続割合は遺言書によって変更が認められているため、正式な相続割合を確定するために確認が必要なのです。
3. 遺産分割協議書を作成する
1.2を経て、遺産分割における話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
これには遺産分割協議での合意内容を細かく記した上で、相続人全員分の署名と実印が必要になります。遺産分割協議書は国で指定するテンプレートなどは存在せず、書式自体は自由です。
遺産分割協議書は相続人自身で作成することも可能ですが、不安な方はこの部分だけ専門家に依頼することも1つの手です。
- 行政書士
- 司法書士
- 弁護士
- 税理士
依頼できるのは上記のような士業を営む人ですが、信託銀行などの資産管理を行う専門機関でも可能です。
遺産分割協議書の作成をしないと、口約束での「言った」「言わない」というトラブルにつながりかねません。相続人間でのトラブル回避のためにも、必ず作成しておきましょう。
4. 登記必要書類を準備する
遺産分割協議書の作成が完了したら、次は相続登記で必要となる書類を準備していきましょう。
必要な書類は、以下のものが考えられます。
相続登記の必要書類一覧(全共通)
- 登記申請書
- 不動産の固定資産評価証明書(または納税通知書+課税明細書)
※登記を士業へ委任する場合は、委任状が必要。
相続登記の必要書類一覧(遺産分割協議による場合)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の付票)
- 遺産分割協議書
- 登記事項証明書
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員分の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 遺言書(作成している場合のみ)
主に上記の書類一式が必要とされていますが、ケースバイケースで追加書類を求められる場合があります。
ちなみに、権利証(登記済権利証)や登記識別情報通知が必要だと誤解されている方が多いですが、相続登記ではこれらの書類は必要ありません。
これらの書類を探すことで時間をかけてしまい、登記期限を過ぎてしまわないよう十分注意してください。
5. 登記申請書を法務局へ提出する
最後は、登記申請書の作成と提出です。登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
登記の目的や原因、相続人などの必要情報を記入していきましょう。
現在、以下の2通りの申請方法があります。
- 書面申請(登記受付窓口)
- オンライン申請
書面での申請をする場合、管轄の窓口へ提出する必要があります。管轄の窓口がどこか分からない方は、以下のサイトで探してみてください。
また、令和2年1月14日よりオンライン申請が可能となり、パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールすることで書類作成、提出ができるようになりました。
参考:不動産登記の申請書様式について:法務局 (moj.go.jp)
不動産の名義変更にかかる費用
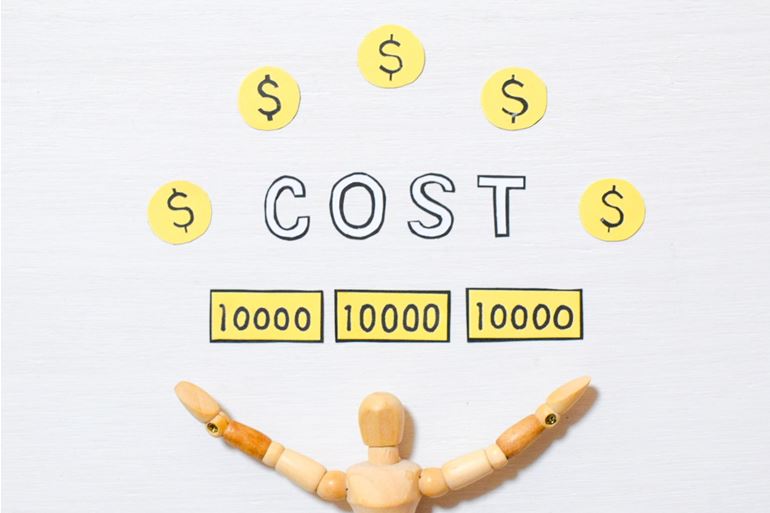
不動産の名義変更を行うに当たって様々な費用が伴いますが、多くの方が気になるのはその具体的な金額でしょう。
相続登記に要する費用には、登録免許税、必要書類の取得費、士業への報酬などがありますが、これらは手続きや不動産の価値、また市町村によっても異なるため、事前にリサーチしておくことが肝心です。
1. 登録免許税
まず、全ての相続登記で必ず発生するものが登録免許税です。いわば登録料のようなイメージの税金です。
登録免許税は、対象不動産の価値に応じた額が設定されており、相続登記の際には不動産の評価額を基準に算出されます。
| 登録免許税の算出法 |
|---|
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4% |
登録免許税は、対象不動産すべてを合算しなくてはなりません。
例えば、土地・建物を相続する場合、2つの不動産の固定資産税評価額を合計し、0.4%を乗じる必要があります。
ただし、千円未満は切り捨てとなります。
2. 必要書類の取得費や各種手数料
名義変更の手続きでは、必要書類の取得や手数料もかかります。
例えば、遺産分割協議書の作成を専門家へ依頼するとその手数料が必要ですし、登記事項証明書(謄本)や戸籍謄本、住民票などを取得するにも一定の費用が発生します。
さらに、遺言書が残されていれば検認手続き(裁判所への申し立て・確認)も必要となり、こちらにも手数料が生じるでしょう。
それぞれの書類取得や手続きに関して、どれくらいの費用が見込まれるのか事前に確認し、準備しておくことが大切です。
3. 士業への報酬
相続登記自体を司法書士、弁護士へ一任する場合、これらの報酬も必要です。
報酬は3~12万円程度となっており、案件ごとに金額が異なります。例えば、共有持分として複数の相続人がいる場合など、登記内容が複雑であればあるほど、費用は高くなります。
士業へ依頼を検討している場合は、何社かに見積もりを取ってみると良いでしょう。
相続登記の義務化による罰則を免れる方法
今回の相続登記の義務化では、以下で定める正当な理由がある場合に限り、罰則を免除されます。
(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合 (2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合 (3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合 (4)相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 (5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 参考:法務省「相続登記の申請義務化について」 |
しかしながら、正当な理由としてこれらを立証するのは現実的には非常に困難です。
さまざまな事情により相続登記が難しい場合、罰則を避けるにはどうすればよいのか、いくつかの対策を探ってみました。
1. 相続放棄という選択肢をとる
相続を望まない方は相続放棄をすることで、登記義務からも逃れることが可能です。
放棄をする場合、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この手続きをすることで、遺産だけでなく、相続登記の義務そのものからも解放されることになります。
ただし、一度放棄をすると取り消すことはできませんので、決定には慎重な判断が必要です。
2. 新制度「相続人申告登記」をする
新制度である「相熵人申告登記」を利用することも罰則を避ける手段の一つです。
この制度は「相続人全員が誰であるかを登記しておくもの」で、登記時点で具体的な遺産分配については決まっていなくても構いません。相続人申告登記を行うことによって、他の相続人が不正に登記を行うことを防ぎつつ、登記義務を果たすことができます。
これによって罰則の対象外となるため、安心して相続問題に対処する時間を確保することができるでしょう。
まとめ

本記事では、不動産の相続登記について概要や申請手続きの方法、費用などを総合的に解説しました。
新たな制度として開始された相続登記の義務化は、私たち消費者の手間やコストが増えますが、所有権関係の透明性を高めるためのものであり、国として重要な法改正です。制度施行以前に相続を受けた人も、早急に取り組む必要があります。
この記事を通じて、相続登記の義務化についての理解を深め、スムーズに手続きを行えるように準備していきましょう。相続登記における個別の事情や疑問がある方は、専門家に相談してみてください。適切なアドバイスを受け、解決策を見つけることができるでしょう。
弊社でも相続登記の相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。




コメント