
マイホームを売却するとき、不動産会社への仲介手数料や引っ越し代などに加えて、「税金」がかかるケースがあります。売却益が出ると課税されるため、知らずにいると大きな負担になりかねません。
ただし、実は条件を満たせば最大3,000万円まで譲渡所得を控除できる「居住用3000万円控除(通称:マイホーム特例)」が利用できます。この制度を使えば、譲渡益が3,000万円以内であれば税金をゼロにできる可能性もあります。
本記事では、マイホーム特例の仕組みや期限、注意すべき3年ルール、手続き方法まで、なるべくわかりやすく解説していきます。
不動産の売却やマイホーム特例の活用について詳しく知りたい方は、ぜひこちらから弊社へお気軽にお問合せください。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- マイホーム特例(居住用3000万円控除)とは?
- 制度の概要
- どんなときに使える?
- マイホーム特例の適用条件
- 居住用財産であること
- 売却相手の条件
- 居住していた期間
- 住まなくなってから3年間の猶予(3年ルール)
- 期限の数え方
- よくある勘違い
- マイホーム特例を受けるための手続き
- 必要書類
- 申告の流れ
- マイホーム特例のメリットと節税効果
- 譲渡益が3,000万円以内のケース
- 譲渡益が3,000万円を超えるケース
- マイホーム特例と他の特例との違い
- 空き家の3000万円控除との違い
- 買換え特例との関係
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除との関係
- マイホーム特例に関するQ&A
- Q1. マイホーム特例は何回でも使えるの?
- Q2. ローンが残っている家を売った場合でも使える?
- Q3. マイホーム特例と住宅ローン控除は同時に使える?
- まとめ
マイホーム特例(居住用3000万円控除)とは?

まず、「マイホーム特例」がそもそもどんな制度なのかを確認しましょう。
難しい法律用語に聞こえますが、仕組みを理解すればとてもシンプルな内容です。
制度の概要
マイホーム特例とは、所得税法第33条の2に定められた「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」のことです。
これは自宅を売却したときの譲渡所得(売却価格-取得費-譲渡費用)から、最大3,000万円を控除できるという特例です。
通常、家を売って利益が出ると、その利益に対して「所得税」と「住民税」がかかります。売却金額が大きいと、納める税金も数百万円になることがあり、「せっかく高く売れたのに思ったより手元に残らない…」というケースも少なくありません。
課税される対象額を大幅に減らせるため、税負担が軽くなる非常に大きなメリットがあります。
転勤や住み替え、ライフスタイルの変化などでやむを得ずマイホームを手放す人が、余計な税負担を背負わずに次の生活を始められるように配慮された制度です。
どんなときに使える?
この制度が使えるのは、「自分が住んでいた家を売却したとき」です。建物だけでなく、建物と一緒に売却する敷地(土地)部分も控除の対象に含まれます。
たとえば「持ち家を売却して住み替える」「相続した家に住んでいたが売却する」といったケースでよく利用されます。
マイホーム特例の適用条件

節税効果が高くとてもありがたい制度ですが、この制度の適用を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは基本的な条件を整理します。
居住用財産であること
本制度を利用するための大前提の条件は「実際にその家に居住していた事実があること」です。これは、住民票上の住所だけでなく、実際に生活の拠点として利用していたかどうかが判断されます。
申請時には、電気・ガス・水道など公共料金の使用明細書の提出を求められることがありますが、「使用実績が乏しい」という理由から否認されるケースもあるようです。
また、税務調査で近隣住民からの聞き取りが行われることもあります。その結果、住民票だけを置いて実際には生活していなかったと判断されれば、特例は認められません。
別荘やセカンドハウスなど、そもそも生活実態のない物件は対象外です。
実際に、国税庁のホームページでも、以下のように記載されています。
【適用除外】
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋
売却相手の条件
控除を受ける物件を売却した相手、つまり買主にも制限があります。
規定では「譲渡の相手方が一定の特別な関係者である場合は対象外」とされています。
具体的には、
- 配偶者
- 直系血族(親・子・孫など)
- 同居の親族または生計を一にする親族
で、親子や夫婦といった特別な関係者への売却は特例の対象外となっています。
これは身内同士で税負担を軽減する「節税スキーム」を防ぐためです。第三者に売却した場合のみ利用できます。
居住していた期間
意外かもしれませんが、「何年以上住んでいた」という期間要件はありません。
極端に言えば、短期間でも実際に居住していた事実があれば「対象」にはなり得ます。
ただし、前述のとおり「税負担を軽減するための節税スキーム」と判断されるかどうか、がポイントです。
短期間しか居住していない場合、「課税を逃れるため」と判断されてしまうと、否認されてしまう可能性もゼロではありません。
また、一度でも他人に貸してしまうと「居住用」ではなくなるため、原則として対象外になります。実際に居住していたことを証明できるかがポイントです。
住まなくなってから3年間の猶予(3年ルール)

マイホーム特例は、実際に住んでいない家でも一定期間なら使うことができます。その期限を「3年ルール」と呼びます。
ただし、この期限の数え方を間違えると控除を受けられないこともあるため注意が必要です。
期限の数え方
マイホーム特例の期限は「住まなくなった年の翌年1月1日から3年目の12月31日まで」です。
たとえば、2022年3月に引っ越した場合は、2023年1月1日から起算して2025年12月31日が期限となります。
このルールの特徴は「暦年ベース」で計算する点です。転居した日から単純に3年間ではなく、翌年1月1日からカウントされるため、本ケースでは実際には3年9か月ほどの猶予がある場合もあります。
よくある勘違い
よく誤解されますが、「転居から丸3年以内に売らなければ特例は使えない」と思い込んでしまう人が少なくありません。
たとえば「2022年3月に引っ越したから、2025年3月までが期限」と勘違いしてしまうケースです。
実際には「翌年1月1日から3年目の12月31日まで」が期限なので、この例でいえば2025年12月31日まで利用できることになります。
つまり、「2025年4月から12月末までに売った場合でも、特例は適用できる」のです。
もし期限が迫っているかどうか不安なときは、早めに不動産会社や税理士に相談して正しく確認しておくと安心です。
不動産の売却やマイホーム特例の活用について詳しく知りたい方は、ぜひこちらから弊社へお気軽にお問合せください。
マイホーム特例を受けるための手続き
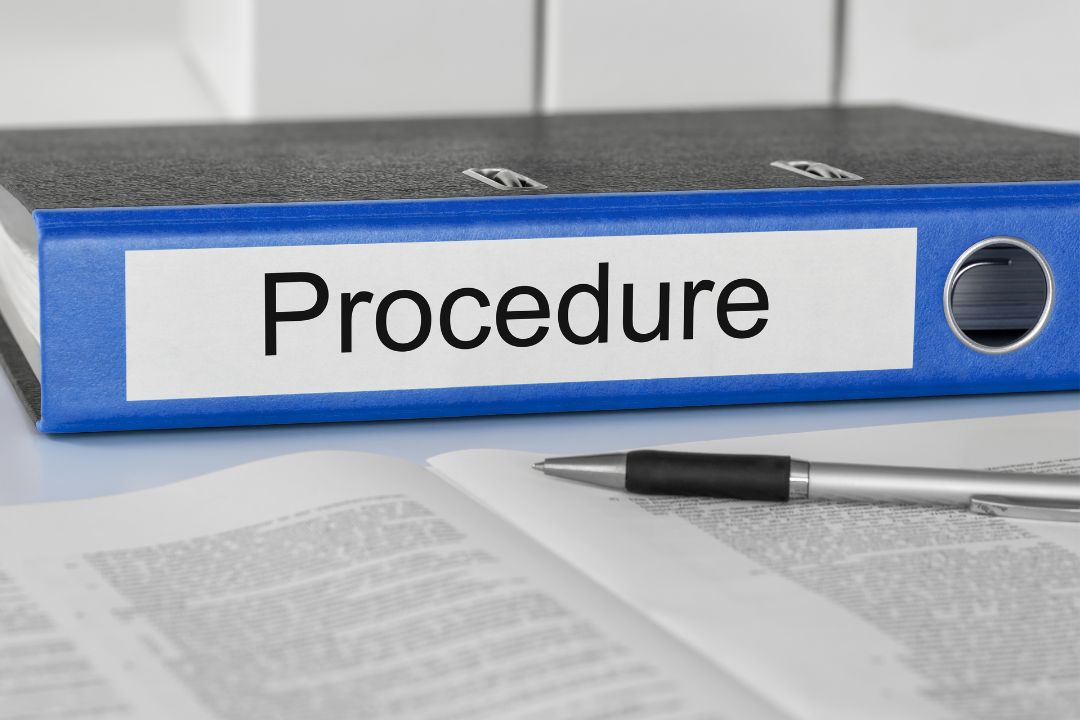
実際にマイホーム特例を利用するためには、確定申告で手続きを行います。
会社員の方は「年末調整を済ませているから申告不要」と思い込みがちですが、マイホーム特例を使う場合は自己申告が必須です。確定申告を忘れると、控除を受けられないので注意しましょう。
必要書類
特例を受けるにあたり、準備すべき書類は意外と多くあります。
代表的なものは次のとおりです。
- 譲渡所得の内訳書(付表)
土地や建物の売却額や取得費を整理した明細書です。確定申告書に添付して提出します。 - 登記事項証明書
売却した家屋やその敷地が確かに本人の所有物だったことを示すものです。法務局で取得できます。 - 居住の事実を確認できる資料
たとえば住民票と物件所在地が一致していない場合には、戸籍の附票の写しや過去の住所履歴がわかる資料を添付して、実際に居住していたことを示します。 - 売買契約書のコピー
売却の金額や日付を確認するために必要です。 - 本人確認書類
住民票の写しやマイナンバーカードなど、本人を証明できる書類も添付します。
これらは売却後に慌てて探すと見つからないことも多いので、売却を検討し始めた段階で整理しておくのがおすすめです。
住民票や登記事項証明書などは役所や法務局での手続きが必要になり、取得までに数日かかることもあるため、余裕を持って準備しておくと安心です。
申告の流れ
確定申告を行う時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間です。(※休日の関係で申告期間は前後することがあります)
①譲渡所得の計算
「売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)」で譲渡所得を計算。
※取得費が不明な場合は「概算取得費(売却価格の5%)」を使うことも可能。
②譲渡所得の内訳書の作成
「土地・建物用の内訳書(付表兼明細書)」を作成し、譲渡所得の計算根拠をまとめます。
③確定申告書の作成
確定申告書B様式に、譲渡所得の内容を転記。
「特別控除の額」欄に3,000万円控除を記載。
④必要書類の準備と添付
売買契約書、登記事項証明書、住民票(または戸籍の附票)、本人確認書類などを準備。
⑤提出方法
紙で税務署に提出、または e-Tax(電子申告)で提出。
e-Taxは自宅からでも申告が可能ですが、初めてだとマイナンバーカードやICカードリーダーの準備が必要になりますので、早めに取り掛かるようにしましょう。
マイホーム特例のメリットと節税効果

確定申告というと、会社員の方にはあまりなじみがなく、「自分には関係ない」「難しくて面倒くさそう」と感じる人も多いと思います。
しかし、マイホーム特例を活用すれば、税金がゼロになることもあります。手続きは少し大変かもしれませんが、自分の手元に残るお金に大きな差が出る、とてもお得な制度です。
譲渡益が3,000万円以内のケース
【売却の条件】
- 売却価格:4,000万円
- 取得費:2,000万円
- 譲渡益:2,000万円(4,000万円-2,000万円)
たとえば、上記のケースでは譲渡益2,000万円が発生しています。通常であれば、この金額に対して所得税と住民税がかかります。
課税方法 | 税額 | |
長期譲渡所得の場合 | 2,000万円×20.315% | 約406万円 |
短期譲渡所得の場合 | 2,000万円×39.63% | 約792万円 |
マイホーム特例を使うと、このケースでは利益が2,000万円出ていますが、控除の枠である3,000万円以内に収まっています。そのため、この利益はまるごと差し引かれて、課税対象となる金額がゼロになります。
譲渡益が3,000万円を超えるケース
【売却の条件】
- 売却価格:8,000万円
- 取得費:4,000万円
- 譲渡益:4,000万円(8,000万円-4,000万円)
上記のケースでは譲渡益が4,000万円発生しています。この場合、通常であれば以下のように課税されます。
課税方法 | 税額 | |
長期譲渡所得の場合 | 4,000万円×20.315% | 約812万円 |
短期譲渡所得の場合 | 4,000万円×39.63% | 約1,585万円 |
長期譲渡所得でも、800万円以上の税金が徴収されることになります。
では、ここでマイホーム特例を使ってシミュレーションしてみましょう。
このケースでは、譲渡益4,000万円のうち3,000万円までが控除されますので、課税対象は「4,000万円-3,000万円=1,000万円」になります。
課税方法 | 税額 | |
長期譲渡所得の場合 | 1,000万円×20.315% | 約203万円 |
短期譲渡所得の場合 | 1,000万円×39.63% | 約396万円 |
つまり「課税されるはずの3,000万円分」が丸ごと差し引かれ、長期譲渡所得では約609万円、短期譲渡所得ではこの制度の上限である約1,188万円の節税が可能ということです。
不動産の売却やマイホーム特例の活用について詳しく知りたい方は、ぜひこちらから弊社へお気軽にお問合せください。
マイホーム特例と他の特例との違い

マイホーム特例とよく似た名前の制度や、過去には存在していたけれど今は使えない特例もあります。
ここでは、誤解されやすい制度との違いを整理し、正しく理解しておきましょう。
空き家の3000万円控除との違い
まずは、相続した空き家を売却した場合に使える「相続空き家特例(空き家の3,000万円特別控除)」。金額が同じなので、マイホーム特例と混同されやすい制度です。
両者の違いを簡単にまとめると、
- マイホーム特例:自分や家族が実際に住んでいた自宅を売却したときに使える
- 相続空き家特例:親などの親族が住んでいた家を相続し、その後に売却したときに使える
という区別になります。
さらに、相続空き家特例にはマイホーム特例にはない条件がいくつかあります。
「相続した家屋が 昭和56年5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準の木造住宅など)」かつ「相続の時点で被相続人が一人暮らしで住んでいたこと」などが要件に含まれています。
また、売却時点までに耐震改修を行っているか、更地にしているか、といった条件も課されます。
つまり、マイホーム特例が「現役で自分が住んでいた家の売却時に利用できる制度」であるのに対し、相続空き家特例は「親などが住んでいた空き家を相続した場合に限定して利用できる制度」で、対象や要件がまったく異なるのです。
買換え特例との関係
次に「買換え特例」、正式名称は「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」です。
かつては、自宅を売却して新しい家を買った場合に譲渡益への課税を繰り延べできる制度で、売却益が大きくてもすぐに税金を払わずに済むメリットがありました。実際には「売却額より高い新居を購入すること」や「一定の居住要件を満たすこと」などが条件とされていました。
ただし、この制度はすでに廃止済みであり、マイホーム特例と併用もできません。現在は「マイホーム特例を使うかどうか」を検討する形になります。
居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除との関係
最後に「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」 という制度です。
マイホームを売却したとき、必ずしも利益(譲渡益)が出るとは限りません。むしろローン残債が多い場合や、市場価格が下がってしまった場合には「譲渡損失」が発生することも多いでしょう。そんな時に使えるのがこの特例です。
制度の概要
- 自宅を売却して損失が出た場合、その損失を給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できる
- その年に控除しきれない損失は、翌年以降最長3年間繰り越して控除できる
- 適用を受けるには、売却した自宅に住宅ローン残債があることなど、一定の要件を満たす必要がある
マイホーム特例は自宅を売却して利益が出た時に使える制度です。一方で、本制度は売却によって損失が出た場合に利用できます。
つまり、売却結果に応じて、どちらの制度を使うかを判断することになります。
マイホーム特例に関するQ&A

マイホーム特例について、実際によく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. マイホーム特例は何回でも使えるの?
A. 基本的には「同じ人が同じ年に何度も使う」ことはできません。
そもそも「実際に生活していた自宅」を前提とした制度なので、頻繁に繰り返し利用できるものではありません。
ただし、翌年以降に別の家を売却する場合には、再度条件を満たせば利用できます。
Q2. ローンが残っている家を売った場合でも使える?
A. 住宅ローンの有無は関係ありません。売却して利益が出た場合には特例を使えます。
むしろローン残債の返済に売却代金を充てるケースが多いため、税負担が軽減できるメリットは大きいです。
Q3. マイホーム特例と住宅ローン控除は同時に使える?
A. 住宅ローン控除は「購入時」、マイホーム特例は「売却時」に使う制度なので、タイミングが異なります。
そのため、そもそも1つの対象物件について、同じ年度で同時に使うことはできませんが、それぞれの場面で活用することは可能です。
まとめ

マイホーム特例(居住用3,000万円控除)は、自宅を売却する人にとってとても心強い節税制度です。正しく理解して準備すれば、数百万円単位の税金を減らせる可能性があります。
最後に、特例を活用するためのポイントを整理しておきましょう。
マイホーム特例を活用するためのチェックリスト
- 自宅として実際に住んでいた家・土地の売却である
- 売却相手が親族や配偶者などの「特別関係者」ではない
- 住まなくなった年の翌年1月1日から数えて3年後の12月31日までに売却できる
- 一度でも賃貸に出していない(居住用として使っていた)
- 売却の翌年に必ず確定申告を行う
- 必要書類(売買契約書・登記事項証明書・住民票の除票など)を早めに揃えておく
また、「相続空き家の3,000万円控除」や、すでに廃止された「買換え特例」と混同しやすい点にも注意が必要です。現在利用できるのは「マイホーム特例」であり、他の制度との併用はできません。
もし売却を検討している方は、早めに不動産会社や税理士に相談し、確実に特例を活用できるようにしておくと安心です。





コメント