
「家賃収入にも税金がかかるのだろうか」「家賃収入の税金を抑えるには、どんな対策があるだろう」と、悩んでいないでしょうか。
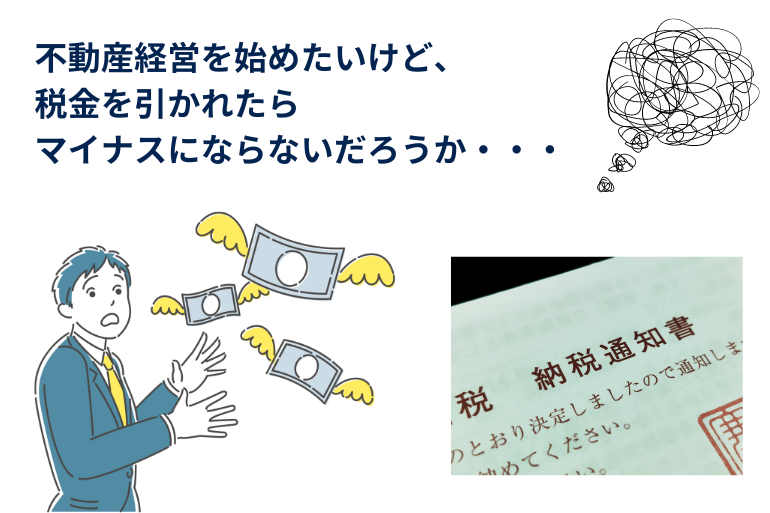
家賃収入には所得税・住民税などの税金が課される可能性があります。所得の増加によって税金も増えますが、青色申告で経費を計上する、小規模企業共済の加入などの方法で税金対策も可能です。
この記事では、家賃収入の税金対策について具体的に解説します。税金対策で法人化するメリット、デメリットについても分かる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
家賃収入に関する税金対策や物件選びに不安がある方は、収支バランスを踏まえたご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- 家賃収入とは
- 家賃収入を得られる仕組み
- 家賃収入と不動産所得の違い
- 家賃収入で課される4つの税金の種類
- 1. 所得税
- 2. 住民税
- 3. 消費税
- 4. 個人事業税(年間利益が290万円を超える場合)
- 家賃収入で課される税金の計算方法
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 家賃収入の代表的な税金対策6選
- 対策1. 青色申告を行う
- 対策2. 必要経費を計上する
- 対策3. 小規模企業共済に加入する
- 対策4. 課税所得が900万円を超えたら法人化を検討する
- 対策5. 赤字が発生したら損益通算をする
- 対策6. 減価償却で節税効果が高い物件を購入する
- 税金対策で法人化するメリットとデメリット
- 法人化のメリット
- 法人化のデメリット
- 家賃収入による税金を納めるには確定申告が必要
- 確定申告が必要な人とは
- 確定申告の申請
- 家賃収入の節税対策効果がある人とは
- 課税所得が900万円以上の人は節税効果が高い
- 課税所得が900万円以下の人は節税効果が低い
- まとめ
家賃収入とは

家賃収入は、自分が所有する不動産を他人に貸し出すことで得られる収入のことです。
たとえば、アパートやマンション、一戸建て住宅などを所有していれば、それらを借りたい人に貸し出すことで、毎月安定した家賃収入を確保できます。
家賃収入を得られる仕組み
家賃収入を得られる仕組み、流れは以下の通りです。
- 物件を購入する
- 入居者を募集する
- 入居者から家賃が入金される
家賃収入を得るためには、物件の立地や間取り、設備など、入居者に選ばれるための工夫が必要です。家賃収入は、物件が持つ価値や需要によって変動します。
たとえば、駅近や人気のエリアにある物件は、家賃収入も高くなる傾向があります。また、設備が充実している物件や、セキュリティがしっかりしている物件も、入居者に選ばれやすく、家賃収入が安定しやすいでしょう。
家賃収入と不動産所得の違い
家賃収入と類似した言葉に「不動産所得」がありますが、両者は明確に異なる意味合いを持っています。
- 家賃収入:物件を貸すことで得られる収入
- 不動産所得:家賃収入から物件の管理費や修繕費、固定資産税などの経費を差し引いた収入
たとえば、家賃収入が100万円で、必要経費が30万円だった場合、不動産所得は70万円です。不動産所得70万円に対して、所得税や住民税などの税金が課されます。
家賃収入と不動産所得の違いの理解は、特に確定申告の際に重要です。家賃収入を得ている場合、通常は毎年確定申告し、不動産所得を計算する必要があります。確定申告を怠ると、延滞税などのペナルティを科せられる恐れがあるので注意しましょう。
家賃収入で課される4つの税金の種類

個人が家賃収入で課される税金は、以下の4つが考えられます。
- 所得税
- 住民税
- 消費税
- 個人事業税
家賃収入や不動産所得の金額によっては、課されない税金があります。
ここでは、家賃収入で課される4つの税金の種類について解説しましょう。
1. 所得税
所得税とは個人にかかる税金で、1月1日から12月31日の所得に対して課されます。家賃収入は、給料と同じように税金の対象です。家賃収入以外に給料収入がある場合、不動産で得た所得と、給料に対する所得を合計して税金を計算します。
日本では所得が多いほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みを採用しているため、家賃収入が増えると、税金も増加する可能性があります。
2. 住民税
住民税は、個人が住んでいる市区町村に納める税金で、所得税と同様に家賃収入も課税対象となります。
住民税は、前年の所得をもとに計算されるので、所得が増えると翌年の住民税も上がります。住民税の税率は、原則として一律10%です。
3. 消費税
消費税は、モノやサービスを購入する際に支払う税金です。家賃収入の中でも、内容によって消費税の取り扱いが異なります。
| 非課税の家賃収入 | 課税の家賃収入 |
|
|
家賃収入の内容が、住宅の貸付である場合、消費税はかかりません。
消費税は2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税を納める必要はありません。たとえば令和6年の消費税の納税義務は、令和4年の課税売上高で判断します。
しかし、インボイス制度の関係で、適格請求書発行事業者に該当する場合は、2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務があるため注意しましょう。
4. 個人事業税(年間利益が290万円を超える場合)
個人事業税は、個人で事業を行っている人が納める税金です。家賃収入が事業的規模とみなされる場合、個人事業税の課税対象となります。事業的規模は、市区町村ごとによって少し異なりますが、一般的には5棟10室以上です。
ただし、年間の所得が290万円以下の場合は、個人で事業を行っていても個人事業税を納める必要はありません。
家賃収入に関する税金対策や物件選びに不安がある方は、収支バランスを踏まえたご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
家賃収入で課される税金の計算方法

家賃収入で課される税金は、種類によって計算方法が異なります。
ここでは所得税、住民税、個人事業税の税金の計算方法について解説します。
所得税
所得税の計算方法は以下です。
|
所得金額とは、給与所得や不動産所得など年間のすべての所得を合計した金額を指します。所得から差し引かれる金額は、基礎控除や社会保険料控除などです。
家賃収入は「不動産所得」に分類され、給与所得や事業所得などと同様に、所得税の課税対象です。所得税を計算する基となる不動産所得は、以下の方法で計算します。
| 不動産所得 = 総収入金額 ― 必要経費 |
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上~695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上~900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上~4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
(参考:国税庁「所得税の税率」)
住民税
住民税は、「所得割」と「均等割」の2種類があります。所得割は、所得金額に応じて課税される税金です。均等割は、所得金額に関係なく、一律に課税されます。
住民税の計算式は以下の通りです。
| 住民税額 = 所得割 + 均等割 |
所得割は課税所得金額に、10%を乗じて計算されます。
所得税と住民税では、基礎控除や扶養控除などの所得から差し引かれる金額が違います。所得税で計算した課税所得金額で計算すると、実際の住民税の金額と異なるため注意しましょう。
個人事業税
個人事業税は以下の方法で計算されます。
個人事業税額 =(事業所得 ― 290万円)× 税率 |
事業所得金額は、家賃収入から必要経費を引いた金額です。税率は事業内容によって異なり、不動産貸付業の税率は5%です。
家賃収入に関する税金対策や物件選びに不安がある方は、収支バランスを踏まえたご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
家賃収入の代表的な税金対策6選
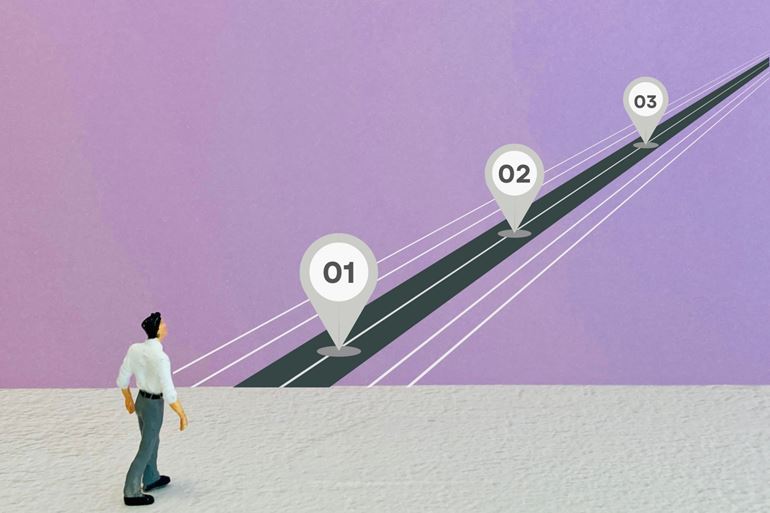
家賃収入の代表的な税金対策は、以下6つが考えられます。
- 青色申告を行う
- 必要経費を計上する
- 小規模企業共済に加入する
- 課税所得が900万円を超えたら法人化を検討する
- 赤字が発生したら損益通算をする
- 減価償却で節税効果が高い物件を購入する
ここでは、家賃収入の税金対策について、内容ごとに解説します。
対策1. 青色申告を行う
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、種類によって作成する書類などが異なります。白色申告は、比較的簡単に作成できますが、節税メリットはほとんどありません。
一方、青色申告は白色申告に比べて帳簿の作成方法が複雑ですが、最大65万円の控除や赤字を3年間繰り越すなどのメリットがあります。
また、青色申告専従者給与を用いると、さらに税金対策が可能です。個人事業主は、生計を一にする家族に対して給料を支払っても経費にできません。しかし、青色申告は「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すると、生計を一にする家族の給料を経費にできます。
対策2. 必要経費を計上する
家賃収入にかかる税金は、収入から必要経費を引いた金額に対して課税されます。必要経費をしっかり計上すると、税金対策が可能です。
必要経費として認められるものは、家賃収入を得るために直接かかった費用です。たとえば、建物の修繕費や火災保険料、広告費などが考えられます。経費計上する領収書や請求書は、大切に保管しておきましょう。
対策3. 小規模企業共済に加入する
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が加入できる積立型の共済制度です。小規模企業共済の掛金は全額所得控除の対象となるので、節税効果があります。
掛金は月々1,000円から70,000円まで自由に設定でき、収入やライフプランに合わせて、無理のない範囲で加入できます。
将来の生活設計を考えながら、小規模企業共済への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
対策4. 課税所得が900万円を超えたら法人化を検討する
家賃収入が多い場合は、法人化を検討するのも一つの手です。
家賃収入が順調に増えて、課税所得が900万円を超える見込みがあるなら、法人化を検討しましょう。法人化すると、所得税率が下がるだけでなく、社会的な信用度も向上する可能性があります。
ただし、法人化には設立費用や運営費用がかかるため、慎重に検討する必要があります。税理士などの専門家に相談しながら、自分に合った選択が大切です。
法人化のメリットやデメリットについては、後述します。
対策5. 赤字が発生したら損益通算をする
不動産投資では、修繕費や空室などで赤字が発生する可能性があります。不動産所得で発生した赤字は、損益通算度を利用して他の所得と相殺することができます。
損益通算とは、赤字を他の所得から差し引いて、課税対象となる所得を減らす制度です。たとえば、不動産所得の損失と給与所得の相殺です。
損益通算すると所得が減り、税負担を軽減できる可能性があります。
対策6. 減価償却で節税効果が高い物件を購入する
減価償却費とは、物件の価値が経年劣化による減少を考慮して、経費として計上できる金額のことです。減価償却できる金額が増えるほど経費が増え、これによって所得額を抑えることで税金対策が可能です。
減価償却で節税効果が高い物件は「建物価格の高い物件」「耐用年数の短い物件」が、考えられます。減価償却は建物価格が高いほど、経費にできる金額も増えます。
また、減価償却は耐用年数と呼ばれる期間を用いて計算し、耐用年数が短いほど経費にできる金額が大きいです。耐用年数は財務省令で定められており、構造や用途などで異なります。たとえば建物でも、構造が木造と鉄筋コンクリートでは耐用年数が違います。
一般的には木造アパートや築年数が古い物件は、耐用年数が短く、節税効果が期待できるでしょう。物件選びの際には、減価償却についての検討が大切です。
確定申告が必要な人とは
税金対策で法人化するメリットとデメリット

税金対策で法人化すると節税できるメリットがあります。しかし、設立費用や税理士報酬などの費用がかかるデメリットがあるため、法人化は慎重にしましょう。メリットが少ない場合、法人化すると税金対策以上の費用が発生する恐れがあります。
ここでは税金対策で法人化するメリットとデメリットを解説します。
法人化のメリット
法人化する最大のメリットは節税です。法人と個人事業主では、税金の計算方法や経費の種類が違います。
個人事業主の場合、累進課税制度により、所得が増えれば増えるほど税金も増えます。一方、法人の場合は、基本的には一定の税率が適用されるので、所得が増えても税率は変わりません。
法人化すると、個人事業主では経費として認められない費用も経費にできるようになります。
- 役員報酬
- 退職金
- 生命保険料
例えば、上記のような経費です。これらの費用を経費に計上することで、税金対策になるでしょう。
また、法人化は、節税以外にも社会的信用度が向上したり、資金調達がしやすくなったりするメリットがあります。事業承継もしやすくなるので、将来を見越した事業展開も可能です。
法人化のデメリット
法人化のデメリットは費用がかかることです。
会社設立には、登録免許税や定款認証手数料、司法書士への報酬など、様々な費用がかかります。法人化した後は、毎年の法人税の決算など、様々な手続きが必要です。法人決算は、専門的な知識が必要な場合もあり、自分で行うのが難しい場合は、税理士や会計士に依頼する必要があります。
また、法人化すると、社会保険に加入する義務が生じます。社会保険料は、会社と従業員が折半して負担することになりますが、個人事業主の時にはなかった負担が増えるかもしれません。
法人化は、メリットとデメリットをしっかりと理解した上で、慎重に検討する必要があります。税理士や会計士などの専門家に相談し、最適な選択をしましょう。
家賃収入に関する税金対策や物件選びに不安がある方は、収支バランスを踏まえたご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
家賃収入による税金を納めるには確定申告が必要

家賃収入が発生した場合、申告を怠ると延滞税などのペナルティを課される恐れがあるため注意しなくてはなりません。
ここでは、家賃収入の確定申告について解説します。
確定申告が必要な人とは
確定申告が必要な人は、以下が考えられます。
- 給料の収入金額が2,000万円を超える人
- 医療費控除を受ける人
- 初年度の住宅ローン控除を受ける人
- 副業の所得が年間20万円を超える人
- 年金収入が400万円を超えている人
家賃収入がある人は、基本的に確定申告が必要です。家賃収入は不動産所得という所得に分類され、所得税や住民税の課税対象です。サラリーマンなど給与所得がある人は、年末調整で税金が精算されますが、不動産所得は確定申告で税金を計算し、納める必要があります。
しかし、不動産所得が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です。また、不動産所得が赤字で損益通算する場合も、確定申告は必要です。
確定申告は、1月1日~12月31日分の所得に対して翌年2月16日~3月15日までに申告し、税金を納付します。令和6年分の確定申告は、令和7年3月15日までに忘れずに申告、納付しましょう。
確定申告が必要かどうか迷った場合は、税務署や税理士への相談をおすすめします。
確定申告の申請
確定申告の申請方法は、以下の手順でスムーズに実施できます。
- 必要書類の準備
- 確定申告書と決算書の作成
- 確定申告書の提出と納付
確定申告をスムーズに行うには、必要書類を事前に準備しておきましょう。必要書類は以下が考えられます。
- 所得金額がわかるもの
- 生命保険料控除証明書などの各種控除証明書
- 確定申告書
- 本人確認書類
確定申告は青色申告か白色申告のどちらかで申告します。青色申告は青色申告特別控除や青色専従者給与など、税制上の優遇措置を受けることが可能です。
しかし、複式簿記による帳簿作成や「所得税の青色申告承認申請書」の提出などが必要です。
一方、白色申告は青色申告に比べて帳簿の作成が簡単、申請書の提出は不要ですが、青色申告特別控除などの税制上の優遇措置を受けることはできません。
確定申告書の提出方法は主に3つです。
- e-Tax(イータックス)で提出
- 税務署に直接持参
- 郵送による提出
e-Taxは、自宅から手軽に申請できるのがメリットですが、操作が難しいと感じる人もいるでしょう。税務署に直接出向く場合は、職員に相談しながら申請できるので安心ですが、混雑している時期は待ち時間が長くなることがあります。
家賃収入の節税対策効果がある人とは

家賃収入の節税対策の効果は、誰もが実感できるわけではありません。具体的には課税所得が900万円以上の人は節税効果を感じるでしょう。
本章では、家賃収入の節税対策効果がある人について解説します。
課税所得が900万円以上の人は節税効果が高い
課税所得が900万円以上の人は、家賃収入の節税対策で効果を実感しやすいでしょう。先述の通り、個人の所得税の税率は、所得が増えるほど高くなる累進課税制度によって決定します。
課税所得が900万円以上の場合、所得税率は33%になります。課税所得が1800万円以上の場合、所得税率は40%以上です。高所得者ほど、家賃収入にかかる税金が高くなるため、節税対策の効果が実感できます。
たとえば、課税所得1000万円の人が100万円の損失が発生した場合、所得税が約33万円減少します。適切な節税対策で、税額を減らすことが可能です。
ただし、不動産所得が赤字になるからといって、むやみに物件を購入したり、修繕費をかけすぎたりするのは注意が必要です。節税効果ばかりを追い求めると、かえって損をしてしまう恐れがあります。
課税所得が900万円以下の人は節税効果が低い
一方で、課税所得が900万円以下の人は、家賃収入の節税対策の効果を実感しにくいでしょう。900万円以下の人の税率は最高でも23%なので、節税できたとしても、その効果は少なめです。
たとえば、課税所得が500万円の人が家賃収入で100万円の赤字を出した場合、単純計算で23万円の節税です。もちろん、23万円も節税できれば嬉しいですが、年収に対する家賃収入の赤字額の方が気になってしまいます。
課税所得900万円以下の人は、家賃収入の節税対策は他の方法と比べて優先度は低いかもしれません。無理に節税対策にこだわるよりも、家賃収入を安定させる方法を考えた方が、結果的に得をする可能性があります。
まとめ

家賃収入の代表的な税金対策は、以下6つが考えられます。
- 青色申告を行う
- 必要経費を計上する
- 小規模企業共済に加入する
- 課税所得が900万円を超えたら法人化を検討する
- 赤字が発生したら損益通算をする
- 減価償却で節税効果が高い物件を購入する
所得税は所得が増えるほど税率が高くなるため、課税所得が900万円以上の人は税金対策の効果を実感できるでしょう。
また、法人化すると役員報酬や生命保険料などを経費にできるため、税金対策に有効な方法の一つです。
しかし、税金対策ばかりに気をとられ、むやみな物件の購入はやめましょう。税金以上に損失になる恐れがあるため、慎重な物件選びが大切です。





コメント