
「未登記のまま放っておいて大丈夫?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
未登記建物には、見過ごせないリスクやトラブルの火種が潜んでいます。相続時の混乱、売買での支障、さらには法的トラブルに発展するケースも…。
この記事では、未登記建物の基本から放置するリスク、相続・売買時の注意点、そして登記までの流れをわかりやすく解説します。
大切な財産を守るために、今こそ知っておくべき知識を身につけましょう。
未登記建物に不安がある方は、早めの対策が重要です。ご相談はこちらからお気軽にどうぞ。
| この記事で分かること |
|---|
|
目次
- 未登記建物とは?
- 建物を登記していないとはどういう状態?
- なぜ未登記建物が存在するのか?よくある原因
- 未登記建物のまま放置するとどうなる?
- 売却・相続・賃貸のトラブル事例
- 法的リスクと固定資産税の扱い
- 解体や再建築時の支障
- 未登記建物の相続における注意点
- 相続登記義務化との関係
- 必要な手続きと登記の流れ
- 相続放棄・遺産分割との関係
- 未登記建物の売買は可能か?
- 売却時に起こるリスクと注意点
- 買主・金融機関からの評価は低い
- 未登記建物を登記する手続きと費用
- 登記の種類(表題登記/所有権保存登記)
- 登記に必要な書類一覧
- かかる費用の目安と依頼先(司法書士・土地家屋調査士)
- 未登記建物に関するよくある質問(FAQ)
- 未登記建物に固定資産税はかかる?
- 建て替えるにはどうすればいい?
- 古い建物は登記できない?
- まとめ|未登記建物は放置せず、早めに対処を
未登記建物とは?

建物や土地を持ったときは、「登記」という手続きを法務局で行う必要があります。これは、誰がその建物の持ち主なのかをきちんと記録に残して、万が一のときに自分の権利を主張できるようにするためのものです。
しかし、中には建てたあとに登記の手続きを忘れてしまったり、「そういう手続きがあるなんて知らなかった」という理由で、何年もそのままにしてしまっている建物があります。
こうした、登記されていない建物のことを「未登記建物」と呼びます。
建物を登記していないとはどういう状態?
建物を登記していないとは、見た目には自分の家でも、法律上は「誰のものかわからない」状態のことです。
登記がなければ、売却や相続の場面で所有者として認められず、トラブルになる可能性があります。
また、登記されていないと資産として評価されにくく、不動産をローンの担保としても使えません。こうした不都合を避けるためにも、登記は早めに済ませておくことが大切です。
なぜ未登記建物が存在するのか?よくある原因
未登記の建物は意外と多く、気づかないうちにそのままになっているケースもあります。
建物が未登記である主な原因
- 登記の必要性を知らなかった
┗建てた当時に登記の知識がなく、手続きをしないまま放置されたケース。 - 建て替え後に手続きを忘れた
┗建て替え時に登記し直す必要があることを知らず、手続きが漏れたままになっているケース。 - 相続後に何もしていなかった
┗相続はしたものの、登記をせずにそのまま使い続けているケース。 - 手間や費用を避けたかった
┗登記にかかるコストや書類準備が面倒で、先送りにされたケース。
いずれにしても、放っておくと後々のトラブルにつながるため、早めに確認と対応を進めておくことが大切です。
未登記建物に不安がある方は、早めの対策が重要です。ご相談はこちらからお気軽にどうぞ。
未登記建物のまま放置するとどうなる?

「今は特に困っていないから」と登記を後回しにしていると、思わぬところで大きな問題が起こることがあります。将来的に家を売却したいときや相続、建て替えなど、さまざまなシーンで手続きがスムーズに進まなくなってしまいます。
以下では、実際によくある事例をもとに、未登記によるリスクについて見ていきましょう。
売却・相続・賃貸のトラブル事例
- 家を売ろうとしたら、不動産会社から「登記されていないと売れません」と言われてしまった
- 親の家を相続することになったけど、兄弟で話し合いがまとまらなかった
- 自分名義になっていない家を貸そうとしたら、契約書が作れず、借り手がつかなかった
このように、登記がされていないと、たとえその建物を使っていても、自由に売ったり貸したりできない状態になってしまいます。
法的リスクと固定資産税の扱い
たとえば、登記していない古い家でも、役所が存在を確認していれば固定資産税の請求はきます。
毎年しっかり税金を払っているのに、いざ家を売ろうとしたとき「登記がないので、あなたのものとは証明できません」と言われてしまうケースもあるのです。さらに、登記していないことを理由に法務局から指導が入ることもあります。
「お金は払っているのに、権利ははっきりしていない。」そんな矛盾が大きなトラブルの元になりえます。
解体や再建築時の支障
他にも、解体や再建築をするときにも未登記の状態が問題になることがあります。たとえば、古くなった家を壊そうとしたら、「登記がないと解体届が出せません」と言われてしまうケース。
また、新しい家を建てる手続きでも、登記情報がないせいで必要な書類の申請が通らず、何度もやり直すことになった例もあります。
役所の手続きでは「登記情報があるかどうか」が基本になっているので、未登記の状態だと何かと手間が増えてしまいます。
こうしたトラブルは、すべて登記をしておけば避けられることばかりです。「まだ大丈夫」と思っている今こそ、確認しておくことが大切です。
未登記建物の相続における注意点

相続の際に登記されていない建物があると、手続きが一気に複雑になります。
ここでは、未登記建物の相続に関する注意点や、実際の手続きの流れ、事前に確認すべきポイントを整理して解説します。
相続登記義務化との関係
2024年4月から、土地や建物を相続したときには、名義を変更する「相続登記」が義務になりました。これは、誰がその土地や建物を引き継いだのかをきちんと記録するための法律です。
ただし、この新しいルールは、もともと登記されている土地や建物が対象で、登記されていない建物(未登記建物)は含まれていません。だからといって、未登記のままで良いわけではありません。
そのまま放っておくと、相続人どうしで「誰のものか」がはっきりせず、話がまとまらなくなったり、家が使えないままになってしまうこともあります。
早めに登記をしておくことで、将来のトラブルを防ぐことができるのです。
【参考記事:【2024年】不動産の相続登記(名義変更)が義務化!手続きや費用を徹底解説】
必要な手続きと登記の流れ
未登記の建物を相続したときは、まず「この場所に、この建物がありますよ」という記録をする「表題登記」から始めます。
次に、「この建物は〇〇さんのものです」とする「所有権保存登記」を行い、最後に相続人の名義にする「相続登記」をして完了です。
準備する書類としては、亡くなった方の戸籍や、誰がどの財産を相続するかを決めた「遺産分割協議書」、それに建物の価値がわかる「固定資産評価証明書」などがあります。
順番を間違えると手続きが止まってしまうこともあるので、不安がある場合は司法書士や土地家屋調査士など専門家に相談するのが安心です。
書類の内容は市区町村によって少し違うこともあるので、事前に確認しておくとスムーズでしょう。
相続放棄・遺産分割との関係
「相続放棄」とは、「自分は財産を受け取らない」とする手続きのことですが、放棄した人の名前が建物の名義に残ってしまっていると、あとで権利の整理がとてもややこしくなります。
また、未登記の建物では「この人が何割の持ち分を有している」というふうに登記することができないため、相続人全員で話し合って決めた「遺産分割協議書」が必要になります。
こうした話し合いがきちんとできていないと、後々の世代にまで大きな問題を残してしまうこともあるので、注意が必要です。特に、建物の価値が高い場合は、相続税の申告にも影響することがあります。
未登記建物に不安がある方は、早めの対策が重要です。ご相談はこちらからお気軽にどうぞ。
未登記建物の売買は可能か?

未登記の建物でも、不動産の売買自体は可能です。
ただし、法的な所有者を証明できないままでは、さまざまなリスクや注意点が伴います。
売却をスムーズに進め、安心して取引を行うためには、事前に登記を済ませておくことがとても大切です。
売却時に起こるリスクと注意点
未登記建物をそのまま売ろうとすると、以下のようなトラブルが起こりやすくなります。
- 「本当にあなたの家ですか?」と疑われる
┗登記がないと、法律上の所有者が誰なのか証明できず、買主に不安を与えてしまいます。 - 買ってもらえない、または安く買い叩かれる
┗登記されていないというだけで、買主が避けることが多く、契約自体がまとまらないことも。売れたとしても、価値が低く見られて価格が下がる可能性があります。 - 銀行から融資が受けられない
┗住宅ローンや投資ローンを使う場合、銀行から登記情報を求められます。登記がないと融資承認を得られず、購入を断念されてしまうこともあります。 - 投資物件として敬遠される
┗特に投資目的で物件を探している人にとって、未登記は「面倒な物件」として見られ、買い手が付きにくくなります。
これらのリスクを避けるためにも、売却前には登記を済ませておきましょう。
買主・金融機関からの評価は低い
買主の立場から見ると、未登記の建物は本当にこの人の持ち物なのか分からないため、避けたいと感じる人が多いです。
また、前章のとおりローンを使って購入する場合、登記されていない建物はリスクがあると判断されて、融資が通らないことがほとんどです。登記がないということは、所有者が誰なのか書類で示すことができません。これは金融機関にとっても不安要素になり、担保として使えないことが多いのです。
そのため、売ろうとしてもなかなか買い手がつかず、価格を大きく下げざるを得ない場合もあります。
未登記建物を登記する手続きと費用
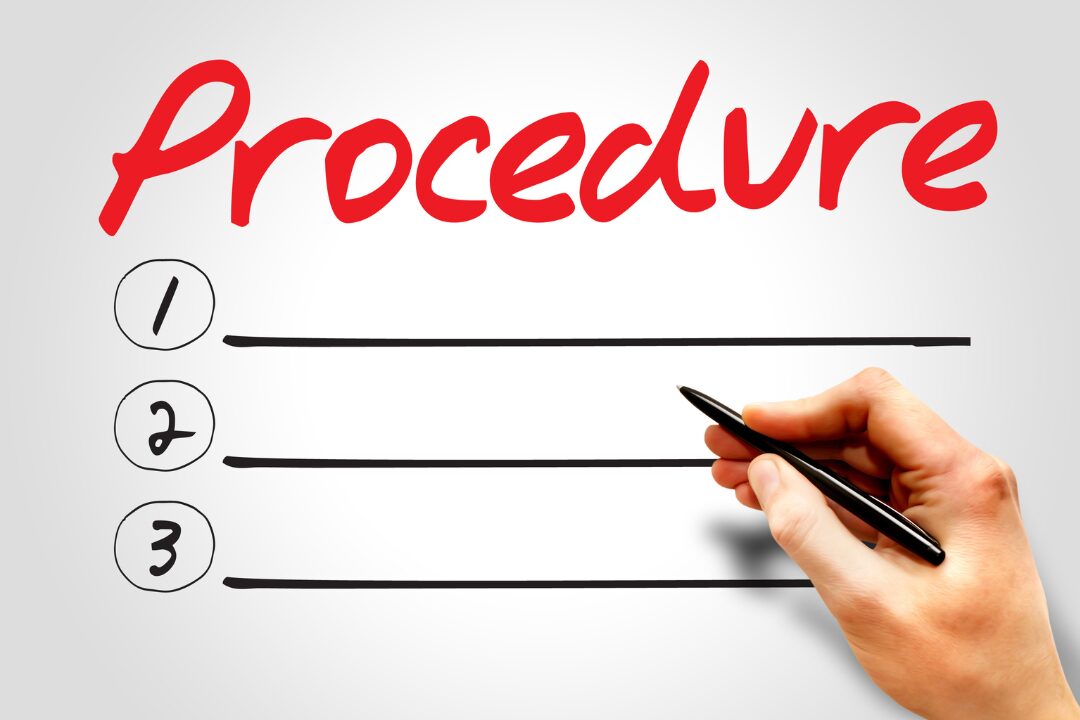
未登記の建物を正式に登記するには、いくつかの専門的な手続きが必要になります。
本章では、具体的な手続きと費用について解説します。
登記の種類(表題登記/所有権保存登記)
未登記の建物を正式に登録するためには、まず「表題登記」という手続きから始めます。
これは、「表題部」といわれる登記簿謄本の最上部にくるもので、建物の住所や構造・面積などの情報を登録する作業です。通常は土地家屋調査士が行います。
| 所在 | 建物が建っている土地の地番・住所など(○○市○○町○丁目○番○号 など) |
| 家屋番号 | 登記上、建物を特定するために付けられる番号(※土地の地番とは異なる場合もあり) |
| 種類 | 建物の用途(例:居宅、共同住宅、事務所、店舗、倉庫など) |
| 構造 | 建物の構造と屋根の種類(例:木造瓦葺2階建、鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 など) |
| 床面積 | 各階ごとの床面積(1階・2階それぞれの広さを記載) |
| 建築年月日 | 建物が完成した年月日(※登記には完了検査済証などで確認することが多い) |
| 所有者の氏名・住所 | 誰の所有物なのかを明示(個人の場合は氏名と住所、法人なら法人名と本店所在地) |
| 登記原因およびその日付 | 建物が新築された、あるいは新たに登記された原因(「新築」など)とその年月日 |
次に行うのが「所有権保存登記」です。通常、登記簿謄本では表題登記の下に情報が載ってきます。
| 不動産の表示 | すでに表題登記で登録された建物の情報(所在地、家屋番号、種類、構造、床面積など) |
| 登記の目的 | 「所有権保存」と記載(所有権を新たに公示する登記であること) |
| 原因およびその日付 | 所有権が発生した理由とその日付(例:「新築 令和7年4月1日」など) |
| 権利者(所有者) | 所有する人の氏名・住所(個人の場合は氏名と住所、法人なら法人名と本店所在地) |
| 申請人 | 通常は所有者自身(代理人による申請も可能) |
| 登録免許税 | 登録時に支払った税金額(不動産の固定資産評価額に基づいて計算) |
これをすることで、「この建物は自分のものです」と法的に証明できるようになります。この2つの登記を済ませておくことで、ようやくその建物に対する自分の権利を、他人にもはっきり示せるようになります。
表題登記は本来、新築時に行うものですが、時間がたってしまっていても後から申請することは可能です。これらの登記によって、建物が正式な「資産」として認められることになるため、きちんと手続きを進めておくことが重要です。
登記に必要な書類一覧
建物を登記するには、手続きごとにいろいろな書類をそろえる必要があります。
まず、「表題登記」では、建物の平面図や配置図、建築確認通知書などが必要です。これらは建物の構造や場所を示すための書類で、市区町村や建築を担当した会社などから取り寄せることができます。
次に、「所有権保存登記」では、所有者の住民票や、建物の固定資産評価証明書、工事完了引渡証明書などが必要となります。
書類に不備があると手続きがストップしてしまうこともあるので、準備は丁寧に進めることが大切です。特に、建ててから年数が経っている建物では、建築時の書類が残っていないこともあります。その場合は、現地調査を行ったり、補足資料を出したりして対応できますが、追加の時間や費用がかかることもあるので注意しましょう。
かかる費用の目安と依頼先(司法書士・土地家屋調査士)
登記にかかる費用は、手続きの内容によって異なります。一般的には、表題登記でおよそ5万〜10万円、所有権保存登記で5万〜15万円くらいが目安です。
登記を行う際は、土地家屋調査士や司法書士といった専門家に依頼するのが一般的です。自分で手続きしようとする人もいますが、必要書類が多く、ミスがあるとやり直しになることも。結果的に時間もお金も余計にかかってしまうことがあります。
登記に慣れていない場合は、最初から専門家に相談したほうが、安心でスムーズに進められます。少し費用はかかっても、後々のトラブルや無駄な出費を防げると考えると、結果的に経済的ともいえるでしょう。
未登記建物に不安がある方は、早めの対策が重要です。ご相談はこちらからお気軽にどうぞ。
未登記建物に関するよくある質問(FAQ)

未登記建物について調べていると、「固定資産税はどうなるの?」「古い家でも登記できるの?」など、具体的な疑問がいくつも出てくると思います。ここでは、そんな疑問に対してわかりやすく答えていきます。
実際によくある質問をまとめていますので、同じような悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。
未登記建物に固定資産税はかかる?
登記がされていない建物でも、固定資産税がかかることがあります。市町村が現地調査などで建物の存在を把握していれば、登記の有無に関係なく課税される仕組みです。
ただし、未登記だと建物面積などの詳しい情報が役所に伝わっていないこともあるため、実際の価値と違った評価になることがあります。高く評価されすぎたり、逆に低く見られたりすることもあるのです。
固定資産税の通知が届いていても、それは登記が完了しているという意味ではありません。税金の手続きと登記の手続きはまったく別物なので、両方をきちんと進めることが大切です。
建て替えるにはどうすればいい?
未登記の建物を建て替えるには、まず古い建物を取り壊して、解体証明書をもらう必要があります。その後、新しい建物を建てるために建築確認申請を行いますが、ここで問題になるのが登記です。
登記がされていないままだと、こうした手続きがスムーズに進まないことがあります。特に、建て替えに合わせてローンを組もうとする場合は、登記がされていないと金融機関の審査に通らないことも。
家を建て直す前には、まず今の状況をしっかり確認して、必要があれば先に登記を済ませておくと安心です。そうすることで、建て替えの計画もスムーズに進みやすくなります。
古い建物は登記できない?
古い建物でも、建物の形や構造がはっきりしていれば、登記は基本的に可能です。ただし、昔の建物では、建築時の書類や図面が残っていないことも少なくありません。その場合は、土地家屋調査士が現地で調査を行い、状況に応じては確定測量が必要になることもあります。確定測量には50万〜100万円程度かかることもあり、土地の形状が複雑なほど登記にかかる費用負担が大きくなります。
建物が古いという理由だけで登記ができないということはありませんが、手続きが少し複雑になることがあります。スムーズに進めるためにも、専門家のサポートを受けながら進めるのがおすすめです。
また、建物が現在の耐震基準や建築基準に合っているかも、あわせて確認しておくと安心です。
まとめ|未登記建物は放置せず、早めに対処を

未登記の建物は、現在は特に困っていなくても、将来になって大きな問題につながる可能性があります。相続や売却の場面では「誰の建物なのか」を書類で証明できず、話が進まないこともありますし、買い手や金融機関からの信頼を得られずに取引が止まってしまうケースも少なくありません。
また、未登記のままだと建て替えや融資の際にも支障が出やすく、せっかくの資産をうまく活用できなくなる恐れがあります。固定資産税の通知が届いていても、それは登記とは別の話。法務局での登記手続きをしっかり済ませておくことが、法的にも実務的にも大切な一歩です。
こうしたリスクを防ぐためにも、未登記の建物は早めに現状を確認し、必要に応じて登記を行うことが大切です。手続きが複雑そうに感じるかもしれませんが、専門家に相談すれば、スムーズに進められます。
将来の安心と財産を守るためにも、今のうちから対策をしておきましょう。





コメント